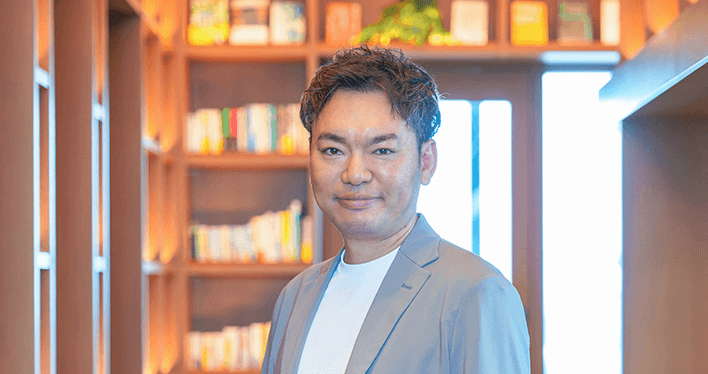正解は自分で決める|チャンスを柔軟に受け止めた先に切り拓いた充実のキャリア

ジョイゾー 代表取締役社長 四宮 靖隆さん
Yasutaka Shinomiya・1976年東京生まれ。東海大学文学部卒業後、1999年にシステム開発会社へ新卒入社。社内インフラ業務に従事し、ネットワークなどの基礎知識を習得後、2003年に独立系SIerに転職。インフラの知識を活かして「サイボウズ ガルーン」の構築や移行の案件に多く携わる。独立後、2010年にジョイゾーを設立、以降現職。翌年にサイボウズ社がリリースした「kintone」に大きな可能性を感じ、自社のメインビジネスとする。2014年6月には、kintoneをベースにした対面開発サービス「システム39」をリリース。2021年「御社にそのシステムは不要です。」を出版
やりたくない仕事から逃げなかったことがキャリアの転機に
学生時代は文学部史学科に在籍し、歴史の勉強をしていました。大学には真面目に通い、3年生のうちに単位を取り終わっていたので、公務員試験でも受けようかと漠然と考えていた時期もあります。
ITとは無縁の学生だったわけですが、いざ就職活動の時期に「これからはITの時代だろうし、そっち系の仕事が良いよな」とものすごく漠然と考えて就職活動をしていました。メールもろくに使えない状態でしたが、イチからモノを作るのが好きで、小さい頃から都市開発シュミレーションゲームであるシムシティで遊んでいたり、プログラミングも遊びで使っていたりなど、興味自体はあったのだと思います。
さらに1990年代の終わり、商用インターネットが始まったばかりの頃ということもあって、就職活動ではシステム開発に携わることができる会社を検討。複数社の説明会には出かけましたが、最初に受けた会社にたまたま受かったことで早々に就職先を決めました。
その会社は従業員300名ほどの規模でしたが、私の代では50人近くの学生を採用していました。全員で3カ月間の新人研修をして、成績が良かったら好きな配属部門にいけると噂で聞いていたので、研修は必死に頑張りましたね。実際に良い成績を残せたので「Web制作の部門に入りたい」と伝え、多分大丈夫だと言われていたのですが、いざ配属されたのは意に反してネットワークインフラの部門でした。
後になってわかったことですが、これは常務直轄のプロジェクトで、研修のなかで成績の良かった新人3人が選ばれた形だったそうです。ただ当時はそんなことは知らなかったですし、配属されてすぐに会社を辞めようとすら思いました。しかし「何事も経験だ、1年やってみてそれでも嫌だったらやめよう」と思い直し頑張ることを決意。結果的にこの経験が私のキャリアになくてはならない財産になり、キャリアにおける最初のターニングポイントとなりました。

新人時代の学びは「足し算」で。できることを増やす姿勢を心掛けよう
プロジェクトは、社内ネットワークの全面的な入れ替えを目指してスタートしました。一人ひとりに細かい業務が割り当てられ、私はグループウェアである「Lotus Notes」の管理を担当。新人ながらいきなり実践でバリバリ仕事をさせてもらえたことで、ネットワークやLinux、グループウェア関連の基礎知識をひと通り身に付けることができました。
同期の皆が定時退社しているなかで、我々3人だけが水曜を除いて22時半退社という状況でしたが(笑)、ほかの同期が3年かけて経験するような仕事を1年でやり切れたことの手応えは大きかったです。
1年ほどでネットワークの入れ替え業務は完了し、そのタイミングでプロジェクトにアサインしてくれた最初の上司が退社。2年目からは別の上司が来てくれましたが、基本的に若手3人だけで社内システムの面倒を見る日々が始まりました。皆で試行錯誤しながらいろいろなトラブルを乗り切ったことでスキルも自信もつきましたし、本当に良い経験をさせてもらった実感があります。
この経験から、何も考えずに目の前の仕事に没頭して業務量をやり切ることが、一番自分を成長させてくれる近道だと考えるようになりました。当社にいる新人のメンバーたちにも「最初は質は気にせず、量をこなすと良いよ」とアドバイスしています。
楽天グループの仲山進也さんの著書『組織にいながら、自由に働く。』で紹介されている「働き方には『加減乗除』の4つのステージがあり、最初は足し算、次に引き算、掛け算、割り算という順序で意識すると良い」という話を聞いた際には、非常に腹落ちしましたね。詳しくは書籍を参照いただければと思いますが、要点だけ紹介します。
キャリアのスタート時期にはとにかく足し算の意識で「量」をこなす。しばらくしたら引き算の意識で、自分がやらなくて良いと思う作業を手放し、得意なことに注力して「強み」を作る。次は掛け算の意識で、得意なことや能力を掛け合わせる。最後は割り算の意識で、それらを最適化させていく、という流れです。

私にとって一社目は、まさに足し算の時期でした。新しいことを勉強しまくり、量をやり切りました。そして入社3年目になる頃には「やっぱりお客様向けの開発案件をやりたい」「プログラミングをやってみたい」という次のステージへの思いが膨らんできました。
キャリアの核となる会社に出会えたのは「偶然の誘い」から
社内の状況が変わったタイミングで転職の意思を固め、2社目に選んだのはイアスという会社です。最初の就職活動と同様、多くの会社を見たわけではありません。直感的に決めました。
面接では、当初志望していたところと違う部署の上司が「うちに来てほしい」と声をかけてくれました。やりたかったこととは少しずれていましたが、上司の人柄にもひかれましたし、仕事もおもしろそうだと思えたので行ってみることに。たまたまその部署が必要としているスキルセットにハマる人材だったのだと思いますが、「人に応えたい」という気持ちは割とあるほうなのかもしれません。
そしてこの決断により、2つ目のターニングポイントが訪れます。それはサイボウズとのかかわりが生まれたことです。1社目では取引先が扱っていた「Lotus Notes」の導入支援などをしていたのですが、その取引先が私が転職してすぐくらいのタイミングでサイボウズ社の「サイボウズ ガルーン」というポータル型グループウェアを取り扱うことになり、このビジネスを一緒にやっていくことになりました。「C#」などの開発案件をやりながら、1社目で培った知識を活かしてサイボウズガルーンの導入にかかわる構築案件に従事し、数千名規模のガルーン構築やNotesからの移行案件など、多くの構築実績を積むことができました。
2008年にはリーマンショックが起こり、イアスも例に漏れず影響を受けました。プレイイングマネジャーとしてチームの面倒を見ながら立て直しに協力していたのですが、会社の方針に共感できないところがあり、再び転職を考えるように。しかし当時の上司から「サイボウズとのつながりをなくすのはもったいないのでは?」と助言をもらい考え直すことにしました。
会社の業績は急に傾くことがあるとわかった。1社目も2社目もそうだったなら、3社目でも結局同じことが起きるかもしれない。それなら自分で独立してもリスクは同じだし、自分でやったほうがリターンは大きいだろう。そんな結論を出し、独立を決意しました。
序盤は1社目の上司だった優秀なエンジニアの方の会社に入り一緒にやっていましたが、自分のペースで判断できないもどかしさを感じるようになり、1年後にはそれぞれの道を歩むことに。そして2010年12月に当社ジョイゾーを立ち上げました。
国産クラウドサービスに出会い「SI業界を良くできる」と確信を持った

起業をした頃にはIT業界にクラウドという言葉がでてきました。特に日本上陸前のAWSを触ったときのインパクトは相当に大きく、「ボタン一つでサーバーが構築できてしまう。これはすごいぞ、このビジネスを手掛けてみたい」と思い調べてみたところ、日本でもすでにAWSのビジネスに着手している会社がいくつかあったため、AWSをビジネスにするのは早々に辞めました。
そうこうしていると2011年11月に、サイボウズ社のクラウドサービス「kintone(キントーン)」が世に登場します。もともとkintoneが出ることは聞いていたのですが改めて発表を聞いて「これは絶対に世の中に広がるぞ」という確信を持ちました。
サイボウズの青野慶久社長も「残りの人生をkintoneに賭ける、全振りでシフトしていく」と宣言していて、国産クラウドサービスをインフラから作り出すという本気度と気概が伝わってきました。ここまでやる日本のベンダーはほかにいないことにも感銘を受け、一緒に心中する気持ちで「うちはkintoneのビジネスしかやらない会社にする」と決意。ここがキャリアにおける3つ目のターニングポイントです。
kintoneに魅力を感じたのは、長年感じてきたSI業界のネガティブな側面を改善できると感じたことも大きな理由です。SIはブラックな3Kの業界というイメージがはびこっていて「本当のSIはそういうものではない。ITを通して人々に便利になったと喜ばれるものを作り出している、すごくやりがいのある仕事なのに」と長年思いつつ、それを改善に導く具体的な方法は思いつかずにいました。しかし、kintoneならば、自分がやりたいことと業界全体の改善を実現できそうだと感じたのです。
そうして宣言通り、kintone専業のSI会社としてkintoneを活用したシステム開発の案件を手掛けていきました。2014年6月には、kintoneをベースにした「来店型」「定額」「初回無料」という特徴を持たせた対面開発サービス「システム39」をリリース。ここが直近で一番のターニングポイントです。
類似のサービスがその後に次々と出てきたことからも、kintone業界に新しい仕組みを作れた、インパクトを残せたという手応えを得ています。今では「Mr.kintone」という光栄なニックネームもいただきました。
「アクションを続ける」「人から学ぶ」ことが活躍への道
あっという間に起業から15年が経ち、現在は生成AIの時代が来ています。当社も今期から社内業務では生成AIをあらゆる場面で活用すると宣言しています。そしてSI業界も生成AIをいかに活用し、ビジネスにするのか、本格的に検討していくフェーズに入ったと実感しています。
先の予測がまったくつかない業界なので、今後のキャリアのビジョンについて明確な思いはありません。一つのことをやりきった実感もないですし、これから先も今までと同様、広くアンテナを立てて、自分の好奇心に基づいてフットワーク軽く行動していきたいです。
ちなみに「行動」というと、体を使って動くイメージがありますが、私が指しているのは広い意味でのアクションのことです。エンジニア的には「自分の手を動かし続ける」という言い方になるかと思いますが、黙々とPCに向かって情報収集することだって立派なアクションの一つ。何かしらのアクションを取り続けることは、業界を問わず社会で活躍する人材の特徴ではないかと思いますね。

また、私はキャリアのなかでずっと上司に恵まれてきたと思っているのですが、それは「その人から学ぶべきもの」をそのときどきで認識できていたからかもしれません。
1社目の最初のプロジェクトについた上司は個性が強い人で、社内から「鬼軍曹」と呼ばれている方でした。キャラクターは名前から察してもらえればと思いますが(笑)、なんだかんだ「この人は自分にはないものを持っているな、ここがすごいな」と思うポイントがありました。
発言に振り回されることはありましたし、大変だと思った瞬間は何度もありますが、「1年間この人を信じてついていってみよう」と思っていましたし、仕事自体のやりがいが大きかったこともあり、つらいと思ったことは一度もありません。そして実際に1年間を通じて、多くの学びをいただいたと感謝しています。人を見抜く力に長けているわけではないのですが、「こういうとらえ方もあるかも?」と視点をずらすことが得意なタイプなのかもしれません。
これから社会に出る皆さんも、もし上司のことで悩んだときには「でも、この人から何か学べるところがあるかも?」という目線でいったん考えてみることをおすすめします。
ただし、あからさまなハラスメントをするなどアウトな上司に当たってしまったときは、すぐに会社から逃げてください。会社がなにも対処してくれないならば、転職などのアクションを取って自分の身を守ってほしいです。
ハードワークに関しても、私は体が丈夫だったので耐えられたのですが、そうではない人もいるでしょうし、全員が全員、同じストレスに耐えなければならないわけではありません。逃げ出してもかまわないという感覚は持っておきつつ、もうちょっと頑張れそうだと自分が思えるなら頑張ってみたらとアドバイスしますね。
仕事はやってみなければわからない。正しい選択だといったん決めてみる
最後に、良いキャリアを歩むためには、柔軟であることが非常に重要だと思います。
私は割と頑固な人間ですが、会社選びの際にあまり迷ったり悩んだりしてこなかったのは、「何が正しいかは自分で決めれば良い」「やってみなければわからない」という考え方だからかなと思います。会社なんて入ってみなければ自分に合うかどうかはわからないものだし、いったんこれが正解だと信じてやってみれば良い。大人なのだから自分で決めたことを正解にして良い。ダメだったら次の会社に行けば良いだけ。そんなスタンスです。
インターネット上に情報が氾濫する時代になり、調べれば調べるほど就職先の正解がわからなくなってしまうといった声をよく聞きますが、そういう人には「自分で判断した決め手を信じて」と伝えたいですね。
あわせて、入社後は頑固になり過ぎないことをおすすめします。いろいろな職種を経験してから「自分は絶対にこの仕事をやりたい」という方向性を定めるのは良いと思いますが、新卒入社の場合はいずれの職種の経験もない状態です。たとえば「絶対にマーケティングをやりたい」と思っても「本当にそれがやりたいことなの?」と自問してみると、「実際のところよくわからない」という答えになることもあると思います。
仮にマーケティング志望でセールス部門に配属されたとしても、やってみたら意外と適性を発揮するかもしれないし、将来マーケティング部門に行ってから役立つスキルが身に付く可能性は大いにあります。頑固になるべきところはあって良いと思いますが、「やりたくない仕事をやらされている」とクサクサしていても良いことはありません。とりあえず目の前の仕事は一生懸命やってみたほうが、自分の将来につながると思います。
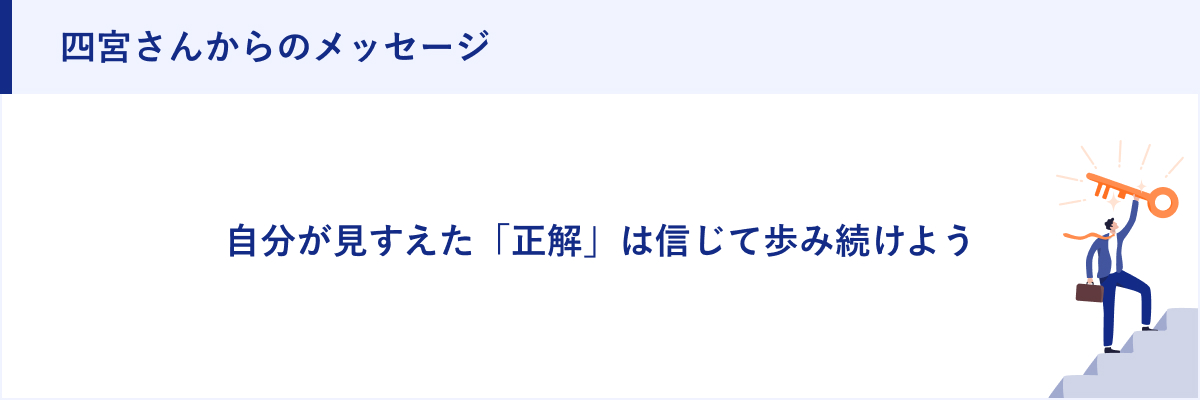
「自分の可能性や強みはどこに落ちているかわからない」ということも頭の片隅に置いておくと良いと思います。やりたくないことが自分の才能や強みになる場合もあることは、私のキャリアからもわかる通りです。やってみて「やっぱり嫌い、苦手だ」と気づいたら、別のフィールドを探せば良いと思いますが、やる前から拒否するのはもったいないです。頑なに選り好みをしていると自分の可能性やチャンスを狭めてしまうと思います。
私はそれがインフラ領域だったわけですが、やってみたら意外と好きなポイントがあった、という感覚です。ゲームでもまちづくりや戦国大名の国づくりなどのシミュレーション系が好きなのですが、インフラ構築にはそれと似たゼロから作り上げていくおもしろさがありました。コンピュータ内の事象には必ず原因があり、それを探り当てられた瞬間も気持ちが良く、やっていくうちにハマることができた感覚です。
柔軟さはIT業界に入ろうと思っている人は特に必要だと思います。クラウドや生成AIの登場がそうでしたが、IT業界ではときどき大きなゲームチェンジが起きるシーンがあります。そういった瞬間に柔軟であれるかどうかで、キャリアの様相は大きく変わってきます。
これからの時代であれば、AI(人工知能)と一緒に仕事をしていく意識を持ち、ゼネラリストを目指していろいろなことを経験しながら、自分は何が得意かを見つけ出していく。そんなスタンスがベストな気がします。
自分が得意なことがわからなければ、「こういうことをやっていると幸せだな、楽しいな」というものをピックアップしてみてください。そこにヒントがある可能性は大です。自分のパーソナリティや過去の経験を打ち込んで、AIに「私の得意なことは何ですか?」と聞いてみても良いと思いますね。AIを上手に使いこなせば、就活のサポーターやメンターにもなってくれると思いますよ。

取材・執筆:外山ゆひら

 キャリアパーク就職エージェントは、東京証券取引所グロース市場に上場しているポート株式会社(証券コード:7047)が運営しているサービスです。
キャリアパーク就職エージェントは、東京証券取引所グロース市場に上場しているポート株式会社(証券コード:7047)が運営しているサービスです。