目次
- GPSテストは対策方法がわかれば突破できる! 3軸の対策法を押さえよう
- まずは基本情報を押さえよう! GPSテストの概要
- 概要:就活でよく使われる適性検査の一つ
- 内容:思考力・基礎能力・パーソナリティが問われる
- 特徴①:音声や動画で出題される問題がある
- 特徴②:選択式と記述式に分かれる
- 特徴③:ビジネスシーンに即した事前対策しにくい問題が多い
- 超重要! GPSテストを突破するための3つの対策方針
- 対策①:企業がGPSテストを実施する「意図」を理解する
- 対策②:具体的な例題を押さえて解き方に「慣れる」
- 対策③:突破のカギとなる思考力の訓練を「習慣化」する
- 問題の意図を理解しよう! GPSテストで問われる4つの要素
- ①批判的思考力:情報を抽出し論理的に解釈する力
- ②協働的思考力:他者との違いを理解して人とかかわる力
- ③創造的思考力:問題を見出し解決策を生み出す力
- ④問題解決に必要な姿勢:立ち直りの早さやリーダーシップ
- 実際にはどんな問題が出る? GPSテストの例題と解説
- 例題①批判的思考力を問う問題
- 例題②協働的思考力を問う問題
- 例題③創造的思考力を問う問題
- 音声+動画で思考力を問う問題
- 思考力を上げる! GPSテストのスコアアップを狙う3つの対策方法
- ①批判的思考力:問題を明確化し批評するトレーニングをする
- ②創造的思考力:新しい経験をして普段話さない人と話す
- ③協働的思考力:人との違いと共通点を把握し自分の意見をまとめてみる
- 基礎能力を上げよう! さらにGPSテスト対策を万全にする5つの対策方法
- ①玉手箱やSPIの参考書で基礎能力対策をする
- ②公式サイトで問題傾向を把握する
- ③ニュース記事などで速読の練習をする
- ④就活サービスに登録して受検する
- ⑤自己分析をして性格テストに備える
- GPSテストについてよくある質問に回答!
- GPSテストはどのようなテストですか?
- GPSテストは対策が難しいと聞きますが対策すべきですか?
- GPSテストの内容を理解して問題イメージを固めておこう!
GPSテストは対策方法がわかれば突破できる! 3軸の対策法を押さえよう
こんにちは。キャリアアドバイザーの北原です。よく就活生から
「GPSテストは具体的にどのようなテストなのですか? 」
「GPSテストに出題される問題や対策方法を教えてください」
といった質問が寄せられます。GPSテストは一部の企業で採用されており、おもに思考力を測るテストなので難しそうなイメージがあるかもしれません。
ただ、GPSテストは必ずしも対策できないものではなく、効果的な対策をすることで検査結果や採用の合否に大きな影響をもたらします。
この記事では、GPSテストの概要や例題、対策方法などを解説するので、これからGPSテストを受けるという人はぜひ読んでみてください。
【完全無料】
大学生におすすめ!
本選考前に活用したい資料/ツール
1位:WEBテスト模試
本番形式のWEBテスト模試が、スマホやパソコンでいつでも受けられます
2位:玉手箱模試
玉手箱の模試がお家で受けられます!本番さながらの環境で実力を試しましょう
3位:WEBテスト対策問題集
SPI、玉手箱、TG-WEBなどの頻出問題をこれ1つで効果的に対策できます
4位:TG-WEB対策問題集
TG-WEB対策にはもう困りません!対策しにくいTG-WEBにも完璧に対応
【選考を控えている就活生必見!】
ツールを活用して選考通過率を上げよう!
①自己PR作成ツール
自己PRが思いつかない人は、ツールを活用して自己PRを完成させよう
②志望動機作成ツール
5つの質問に答えるだけで、AIが志望動機を自動で作成します
③自己分析ツール
選考で使えるあなたの強み・弱みがわかります
まずは基本情報を押さえよう! GPSテストの概要


就活生

キャリアアドバイザー
就活ではさまざまな適性検査が実施されますが、たしかにGPSテストはあまり知られていないかもしれませんね。

就活生
対策は無理だから、もうぶっつけ本番でやるしかないよ、と言っている友人もいたのですが……。

キャリアアドバイザー
そんなことはありませんよ。まずはどのようなテストなのか、概要を理解することから始めましょう。
GPSテストの対策に入る前に、GPSテストはどのような目的でおこなわれるのか、どのような問題があるのかなど、基本的な情報を理解しておくことが大切です。まずはGPSテストの概要や特徴を解説していきます。
概要:就活でよく使われる適性検査の一つ
GPSテストはベネッセi-キャリアが作成・運営しているWebテストです。GPS-Academic(GPSアカデミック)とGPS-Business(GPSビジネス)の2種類があり、測定する能力や対象者が異なります。就活で活用されるのは、主にGPSビジネスです。
GPSテストでは、Webテストとして広く知られている玉手箱やSPIにはない思考力が問われる問題が多い傾向にあります。
問題形式が特徴的だからか、実際にGPSテストを受検した人の中には「制限時間があるので焦ってしまった」「制限時間に対して設問数が多く、時間が足りなかった」などと感じた人もいるようですね。Webテストに慣れている人でも、事前に何らかの対策をしておいたほうが取り組みやすいでしょう。
ちなみに、運営元のベネッセi-キャリアの調査によると、2021年時点の平均スコアは40前後とされています。スコアが52を超えると優秀で全体の約14%、58を超えると非常に優秀で全体の約7%しかいません。
最もよく使われる適性検査の一つであるSPIの勉強方法はこちらの記事で解説しています。
関連記事
7つの手順で必ず高得点! SPI勉強法を分野別・形式別に徹底解説
SPIは手順を踏んだ練習が高得点のカギ こんにちは、キャリアアドバイザーの北原です。選考では、適性検査としてSPIを受検することもしばしば。そんなときに、 「SPIってどうやって勉強したら良いですか?」「そもそもSPIに […]
記事を読む

内容:思考力・基礎能力・パーソナリティが問われる
GPSテストの項目は「思考力」「基礎能力」「パーソナリティ」にわかれています。それぞれの特徴は以下のとおりです。
- 設問数:35問
- 制限時間:45分
- 内容:批判的思考力・協働的思考力・創造的思考力
3つの思考力を評価することで、問題解決能力の有無を測定します。必要な情報を抽出して冷静に比較検討ができるか、他者との共通点や違いを理解して適切にかかわれるか、情報を整理して問題の解決策を生み出せるかなどを確認します。
- 設問数:30問
- 制限時間:25分
- 内容:言語処理能力・非言語処理能力
文章を理解して読み取れるか、自分の考えを言語化できるか、グラフや表の読み取りができるかなどを確認します。
- 設問数:23問
- 制限時間:10分
- 内容:レジリエンス・リーダーシップ・コラボレーション
ストレスに対する耐性の有無、自主性、協調性など、どのような人物なのかを確認します。
それぞれの項目の内容を見ると、制限時間に対して設問数が多いことがわかりますよね。問題が長文なうえに自分なりに考える時間が必要になりますが、1問ずつじっくり考える時間はないかもしれません。

キャリアアドバイザー
スムーズに回答できるよう、しっかり対策をしておきましょう。
特徴①:音声や動画で出題される問題がある
一般的なテストのように文章で出題される問題が多いものの、思考力を測定する項目では音声や動画で出題される問題されるケースもあります。音声や動画の問題は、流れてくる音声を聞いて回答するケースと、音声に動画が付いている2パターンです。
複数人で会話する様子を聞いたり、アニメーションで見たりして問題に答えますよ。チュートリアルや練習問題が用意されていますが、いずれも制限時間があります。また、設問ごとの制限時間も設けられており、制限時間が過ぎると自動的に次の設問に進んでしまうので注意しましょう。

キャリアアドバイザー
これまであまり音声や動画の問題を経験していない場合は、音声による問題に慣れておくと安心して挑めますよ。
特徴②:選択式と記述式に分かれる
回答方法は、選択式と記述式があります。選択式の問題は問題文が長い反面、限られた時間内で内容を理解しながら最後まで読み切り、適切な回答を選ばなければなりません。
記述式は文章を読んだうえで自分の考えを記載する、小論文のような形式ですね。どのような部分を測定するのかは問題によって異なりますが、思考力をアピールするだけでなく、わかりやすく自分の考えを伝えられるかどうかもポイントです。
記述式は選択式のように明確な答えはありませんが、評価基準表の採点ルーブリックにもとづいて評価します。たとえば、比較して考えられているか、問題点を自分なりにとらえようとしているか、など問題によって基準が定められています。

キャリアアドバイザー
選択式のみの問題が出題されることもあるので頭に入れておきましょう。
特徴③:ビジネスシーンに即した事前対策しにくい問題が多い
GPSテストの内容は、ビジネスシーンに即した出題形式が多いため、事前対策がしにくい点も特徴です。事前対策しにくいとその人本来の思考力を測定しやすくなるため、正確な能力を見極めたい企業側にとってはメリットとなります。
とはいえ、就活生側からすると、事前に対策しにくいといわれると不安になってしまいますよね。さらにGPSテストは玉手箱やSPIほどオーソドックスなテストではないため、過去問や対策本なども少ない傾向にあります。そこで日頃から思考力を上げられるよう、意識しておく必要があります。
キャリアアドバイザーコメント長尾 美慧プロフィールをみる
実際にGPSテストを実施している企業は多くありません。まだGPSテストを導入している企業と出会ったことがない学生もいるのではないでしょうか。GPSテストを利用している企業の特徴として、人材系の企業が挙げられます。人材系を中心に選考を受ける学生は、事前に対策をしておいて損はないかもしれません。
また、関西電力や、GPSテストの運営元のグループであるベネッセコーポレーションもGPSテストを実施しています。関西電力株式会社は、音声問題や動画問題も出題されるGPSテストを選考に含んでいると言われています。これら2社を受ける予定の学生は、早めの段階から対策しておくと安心ですね。
本番で焦らないために!スマホで簡単にWEBテスト模試を試そう
書類の準備や面接対策に時間を割いて、WEBテストの対策まで手がまわらない人は多いです。
「WEBテスト模試」なら、スマホやパソコンで簡単に頻出問題の対策をすることができます。言語と非言語の問題を網羅的に出題。テストを受け終わったら、解説を見ながらすぐに復習して苦手分野の対策ができますよ。
WEBテストの対策は効率的に進めながら、他の対策に力を入れて選考を突破しましょう!
超重要! GPSテストを突破するための3つの対策方針


就活生
GPSテストは事前対策が難しい問題もあるとのことで、難易度が高そうです。どのように対策するのが良いのでしょう。

キャリアアドバイザー
たしかに難易度が高いといわれることもありますが、まったく対策できないわけではありませんよ
GPSテストを突破するためには、きちんとした方針に基づいて対策する必要があります。GPSテストを突破するための3つの対策方針を解説します。
対策①:企業がGPSテストを実施する「意図」を理解する
GPSテストを突破するには、まず企業の意図を理解する必要があります。先述したようにGPSテストでは思考力が問われる問題が多く、課題を発見・解決する力や違いに気付ける力など、一人ひとりの思考力がスコア化されるのが特徴です。
一般的なテストや面接で思考力の高さを測ろうとすると見極めが難しかったり、面接官によって評価が異なったり、正しく評価できないこともあります。そこで企業は思考力を活かして活躍できそうな学生を見つけるために、客観的に評価できるGPSテストを活用するのです。
GPSテストを導入している企業の特徴としては、「課題の発見や解決ができる人を探している」企業や、「提案力やコンサル力を重視する」企業などが挙げられます。

キャリアアドバイザー
ベネッセコーポレーションや関西電力の採用試験で導入されていると言われています。
対策②:具体的な例題を押さえて解き方に「慣れる」
GPSテストの形式は独特なので、具体的な例題を確認して解き方に慣れておくこともおすすめです。例題はGPSテストの公式サイトにも記載されています。また、この記事内でも紹介しているのでチェックしてみてくださいね。
まったく同じ内容ではなくても解き方や問題の雰囲気、出題の形式がわかっているだけで、落ち着いて対応できますよ。

キャリアアドバイザー
志望している企業とは別にGPSテストを実施しているところがある場合は、その企業の選考に参加して、実際にテストを受けてみる方法もおすすめです。
対策③:突破のカギとなる思考力の訓練を「習慣化」する
GPSテストでは思考力が試されますが、思考力は意識すればすぐに身に付くものではありません。特に自分で「解決策を生み出すのが苦手」と感じている場合は、思考力を訓練しましょう。思考力を訓練するには以下のような方法があります。
- 目の前の出来事に疑問を持ってみる
- 疑問を持ったら対処法や解決策を考えてみる
- 表面的なことだけでなく、見えない部分も確認してみる
- 本を読む習慣をつける
普段は意識しないような小さな出来事にも疑問を持ち、「なぜそうなったのか」「それで本当に良いのか」などを考える癖をつけましょう。また、仮にそのままにしていても自分に影響がないことでも、対処法や解決策を考えるにすることで、思考力が磨かれるでしょう。
また、いつもおこなっている作業をしているときにも、より効率的にできる方法や改善できる方法を考えてみるのもおすすめです。思考力を鍛えるために、さまざまな分野の本を読み、読後に要点をまとめてアウトプットするのも良いでしょう。
キャリアアドバイザーコメント塩田 健斗プロフィールをみる
GPSテストは比較的マイナーなテストなため、事例が少ない傾向にあります。加え、思考力が問われるテストのため、対策してもしょうがないと考える人もいるかもしれません。確かに出題形式が特徴的ですが、内容自体が難解ということではありません。基本的に問題のパターンは同じであり、繰り返し問題を解くことで慣れてきて、素早く解けるようになっていきます。
SPIなどの有名なWebテストと比較すると、参考書なども限られており、対策のバリエーションが少ないかもしれません。しかし「とにかく問題形式に慣れること」を重視して繰り返し問題を解くことで、十分高得点が狙えます。
GPSテストでは、対策方法が少ないからといって対策を諦めるのではなく、対策手法の多さに捉われず、慣れるまで同じ問題に取り組むことを意識しましょう。
もうWEBテスト模試は受けた?
スマホで実力をチェックしよう
問題集だけで対策すると、本番の時間制限などに慣れず焦る場合もありますよね。
「WEBテスト模試」なら、簡単に本番を想定した対策ができます。スマホやパソコンで、実際のテストを想定した模試を受けることができますよ。
今すぐWEBテスト模試を受けて、自分の実力をチェックしてみましょう。
問題の意図を理解しよう! GPSテストで問われる4つの要素
GPSテストでは「批判的思考力」「協働的思考力」「創造的思考力」のほかに、「問題解決に必要な姿勢」も問われます。それぞれどのような力が測定されるのか、問題の意図を理解しておくことも大切ですよ。
とはいえ、批判的思考力や協働的思考力などといわれてもピンときませんよね。そこでGPSテストで問われる4つの要素を一つずつ解説します。
①批判的思考力:情報を抽出し論理的に解釈する力
批判的思考力は、表面に出ている部分だけで物事を判断するのではなく「いま見えている情報が本当に正しいのか」「それで良いのか」を見抜けるかどうかが問われます。
たとえば、問題文で主張している内容の背景を見抜いて、選択肢の中から答えを選ぶ問題などです。主張と暗黙の前提・根拠をわけて考えたうえで、さまざまな視点から情報を分析する必要がありますよ。
情報を論理的に分析して判断し結論を導き出せると、何かに取り組むときにリスクを考慮したり、問題を解決したりできます。

キャリアアドバイザー
現代はあらゆる情報が手に入る環境にあるからこそ、企業も正しい情報を見抜く力を持った人に入社してほしいと考えています。
②協働的思考力:他者との違いを理解して人とかかわる力
協働的思考力は自分と他者との共通点だけでなく、異なる価値観や意見、背景などを理解できるか、さらにそれを取り入れつつ自分なりの答えを導き出せるかが問われます。
他者との違いを理解して物事を考えるということは、コミュニケーションにおいても大切なポイントです。社会人になれば自分とは異なる価値観や意見を持つ人ともかかわらなければなりません。
自分なりの意見や価値観を持って相手に伝えることも大切ですが、自分の意見を主張するだけではチームワークは構築できませんよね。
協働的思考力があれば問題が発生した場合も建設的な議論ができますし、お互いの意見を受け入れ合うことで新しいアイデアが生まれる可能性もあります。

キャリアアドバイザー
チームワークを重視する企業は多く、協働的思考力を高めることは就活においてとても重要ですよ。
自己PRでチームワークをアピールする際の条件はこちらの記事で確認してみてくださいね。
関連記事
「自己PRでチームワーク」が評価される絶対条件とは? 例文付き
自己PRでチームワークが評価されるための重要な3つの要素を紹介します。キャリアアドバイザーが、チームワーク力をアピールする4つのステップやチームワーク力をアピールする例文も紹介しているのでぜひ参考にしてみてください。
記事を読む

③創造的思考力:問題を見出し解決策を生み出す力
創造的思考力は、課題をさまざまな視点から考えて解決策を生み出す力が問われます。柔軟な考え方ができるか、独創的な考え方ができるかなどもポイントです。創造的思考力は新しいアイデアの生成やアイデアの応用にも役立ちますよ。
ビジネス市場は日々変化し続けているからこそ、「こういう場合はこうしなければならない」という枠にとらわれた考え方では解決できない課題もあります。まったく関係ない事柄が解決策につながったり、一見難しそうな課題も新たな視点で考えると独自の解決策につながったりするケースも珍しくありません。

キャリアアドバイザー
新しい商品やサービスを生み出すイノベーションにも創造的思考力が欠かせませんね。
④問題解決に必要な姿勢:立ち直りの早さやリーダーシップ
問題解決に必要な姿勢は、GPSテストの内容で解説したパーソナリティの部分です。パーソナリティの項目で問われるレジリエンス・リーダーシップ・コラボレーションの意味や測定内容は以下のとおりです。
- レジリエンス:精神的なストレスに対する耐性や回復力のこと。情緒安定性や立ち直りの早さ、状況に応じた対応ができるかなどが問われる
- リーダーシップ:自主性やチャレンジ精神を持って推進する力のこと。先頭に立って物事を進められるか、新たなことに挑戦していけるかが問われる
- コラボレーション:周囲の人と協力して物事を進める力のこと。他者と積極的にかかわったり相手の立場に立とうとしたりできるかが問われる
いずれも問題を解決するには欠かせない力です。失敗や問題に直面した場合、いつまでもくよくよしてはいられません。また、ある程度ストレスに耐性があったり、自分なりの回復方法があったりすれば、問題が発生しても早めに立ち直れます。
問題解決をだれかがやってくれるだろうと人任せにするのではなく、自ら先頭に立ち周囲と協力しながら解決に取り組む姿勢も求められています。
リーダーシップを効果的にアピールするための言い換え表現はこちらの記事で解説しています。参考にしてみてくださいね。
関連記事
例文13選|リーダーシップを言い換えて強みを効果的にアピール!
リーダーシップをアピールする際は、言い換えることでより効果的に伝えることができます。企業がなぜリーダーシップのある人材をもとめるのかを理解したうえで、例文を参考に是非作成してみてください。
記事を読む

また、問題解決能力を鍛えるための方法もこちらの記事で詳しく解説しています。対策とあわせて以下の記事も確認してみましょう。
関連記事
就活で使える問題解決能力を鍛えるには|3つの方法や例文から解説
問題解決能力が備わっている人は選考でも高評価を得やすいです。 この記事では、問題解決能力が必要とされる理由、向上させる方法などをキャリアアドバイザーが解説します。 解説動画、自己PR例文、おすすめ本も参考に能力を鍛えおきましょう!
記事を読む

実際にはどんな問題が出る? GPSテストの例題と解説
GPSテストは2024年現在、過去問などがほとんど出回っておらず出題形式も独特なため、具体的にどのような問題が出題されるのか心配になってしまいますよね。
GPSテストをイメージできるよう、思考力に関するテキスト問題の例題を紹介します。あくまで一例ですが、それぞれどのような考え方をすれば良いのかも解説するので、参考にしてみてくださいね。
例題①批判的思考力を問う問題
批判的思考力を問う問題として紹介されているのは、たとえば以下のような問題です。
次の主張には言葉にはされていないものの前提となっている考え(暗黙の前提)があります。暗黙の前提として最も適切なものを(A)~(D)の中から1つ選び、記号で答えよ。
(主張)
交通渋滞を解消するには、新しい高速道路を建設することが望ましい。
(A)高速道路を建設すれば、多くの人は一般道よりも高速道路を選ぶ。
(B)交通渋滞は道路が不足していることが原因である。
(C)高速道路を建設すると、市民の生活が快適になる。
(D)新たな道路の建設で地域経済の活性化も狙いたい。
この問題の回答は(B)です。交通渋滞の原因が道路不足と考えているため、道路を増やすことが有効な対策であると結論づけているからです。初めて挑戦すると難しく感じてしまうかもしれませんが、正解がわかると考え方をイメージできるのではないでしょうか。

キャリアアドバイザー
最初は選択肢のどの部分が暗黙の前提なのかを想像するのが難しいかもしれませんが、問題に慣れることと、トレーニングをすることで批判的思考力を上げられます。
例題②協働的思考力を問う問題
協働的思考力を問う問題では、会話文を読んだうえで問いに答える形式があります。たとえば以下のような問題です。
旅行に行く約束をしている2人が旅行中のスケジュールについて話し合っている内容を読み、問題に答えよ。
ミナ「〇〇は観光スポットがたくさんあるみたいだよ」
ユア「いいね! その中でここだけは行っておきたいっていう観光スポットはどこ?」
ミナ「ここだけはっていうより、効率的なルートを考えて時間が許す限り行けるところは全部行きたいかな」
ユア「旅行中はホテルに戻るまで観光スポット巡りをしたいっていうこと? 」
ミナ「うん! 遠くてなかなか行けない場所だし、知らない土地で非日常を楽しみたいな」
ユア「いろいろ行くのもいいけど、何個かに絞った方が時間にゆとりができて焦らず楽しめるんじゃない? 」
この会話でユアが伝えたかったことを、以下の(A)~(D)の中から1つ選び、記号で答えよ。
(A)観光スポットはのんびり楽しみたい
(B)行く場所が少ない方がスケジュールを立てやすい
(C)旅行中のスケジュールは自分が主導権を持って決めたい
(D)観光スポット巡りはめんどくさい
この問題の解答は(A)です。ユアは時間にゆとりがあった方が楽しめると考えており、スケジュールの立て方が気になったり、観光スポット巡りがいやなわけではないからです。会話のキーワードとなりそうな言葉を見つけて、言葉の裏にはどのような気持ちが隠れているのかを想像してみましょう。

キャリアアドバイザー
限られた時間で回答しなければならないため、発言している人の気持ちを想像しながら会話文を読めるように練習してみると良いですね。
例題③創造的思考力を問う問題
創造的思考力を問う問題では2つの物語が提示されており、選択肢の中から答えを選ぶ形式があります。
物語1と物語2を読み、問いに答えよ。
(物語1)
稲作が盛んな村で、ある年干ばつが発生して田んぼに水を引いていた川が枯れてしまいました。田んぼに必要な水を確保するのが難しくなったことで、わずかな水を巡り村人たちは口論が絶えなくなります。しかし、水が欲しいのはどの村人も同じです。見かねた村長は村人みんなで井戸を堀り、村の中で水が確保できるようにしようと提案します。村人たちははじめは面倒に感じながら、村長の提案だからとしぶしぶ協力して井戸を掘り続けると、水が湧き出し村中に歓喜の声が響き渡りました。井戸のおかげで村中の田んぼに水が行き渡るようになり、無事どの田んぼも豊作になりました。
(物語2)
ある町で同じ時期にパン屋が2軒オープンしました。どちらも町1番のパン屋を目指しています。はじめはお互いを認め合い切磋琢磨しながら腕を磨く良い関係だったものの、やがて相手の評判を落として自分の店に客を呼び込もうとするようになりました。どちらのパン屋も好きな住民がその様子を見て「どちらも腕は確かなのだから、この町の特産品を使って新しいパンを共同開発してはどうでしょうか? 」と提案します。そこで2軒は知恵を出し合い、協力して新しいパンを作ってどちらのお店でも販売することにしました。共同開発したパンはたちまち人気になり、パンを求めて町を訪れる観光客が増えたため、パン屋はもちろん町全体が豊かになりました。
物語1と物語2には共通する教訓があります。次の(A)~(D)から2つの物語に共通する教訓を選び、記号で答えよ。
(A)問題が生じたら誰かにアドバイスをもらうべきである
(B)争いごとは短期間で解決するべきである
(C)争いごとはできる限りさけるべきである
(D)問題を解決するには争うのではなく協力することが大切である
解答は(D)ですね。それぞれの物語は短いものの、文章の難易度が高めで2つの物語の本質を読み取らなければならないため読解力が必要です。

キャリアアドバイザー
2つの物語を読まなければならず、さらに比較検討しながら考えなければならないため、ペース配分も考慮しながら解くように意識してみてくださいね。
音声+動画で思考力を問う問題
音声や動画で思考力を問う問題は、短音声動画と音声+動画のパターンがあります。
短音声動画は会話のみが流れる形式で、短い日常会話を聞いて違和感に気付けるかどうかが問われます。音声のみなので、だれがどの発言をしているのか自分なりに想像しながら聞いてみましょう。倫理的におかしいところや矛盾がないかを考えながら聞くこともポイントです。
音声+動画では、日常的に起こり得る場面が出てきます。映像は実写やアニメーションで、動画の最後に問題文と選択肢が表示される形式です。
3つの思考力「批判的思考力」「協働的思考力」「創造的思考力」のうち、いずれかが問われます。

キャリアアドバイザー
音声のみのパターンも音声+動画のパターンも、会話の内容を聞き漏らさないように注意するとともに、頭の中で内容を整理しながら聞くように意識しましょう。
思考力を上げる! GPSテストのスコアアップを狙う3つの対策方法


就活生
GPSテストで必要な思考力は、練習すれば上げられるものなのでしょうか?

キャリアアドバイザー
練習することも大切ですが、GPSテスト対策のためだけに練習するだけでなく、日常生活の中で意識する癖をつけておくことも大切ですよ
GPSテストで問われる思考力は、トレーニングによって鍛えることができます。批判的思考力、創造的思考力、協働的思考力それぞれについて、対策方法を解説します。
①批判的思考力:問題を明確化し批評するトレーニングをする
批判的思考力を上げるには、以下のようなトレーニングが向いています。
- 問題を明確にする癖をつける
- テレビ番組や映画、本の批評をしてみる
- 社会問題について考えてみる
- 自分の思考を理解する
問題が生じたときに漠然と考えて対処するのではなく、何が・いつ・どこで・何があったのかを明確にしたうえで解決策を生み出す癖をつけます。また、テレビや映画を観るときには、なぜこの表情をしているのか、登場人物はなぜそう考えたのかなど、疑問に感じた点や気付いたことについて考えながら鑑賞してみましょう。
実際に発生している社会問題について、なぜそのような問題が発生しているのか原因を考え、さらに自分ならどのように解決するのかを考えるのもおすすめです。
また、自分では当たり前だと思っていたことが実は思い込みだった、偏見だったということもあります。自分の思考に先入観や偏見がないかを客観的にとらえておくと、これまでとは異なる視点から問題解決策が生まれる可能性がありますよ。
②創造的思考力:新しい経験をして普段話さない人と話す
柔軟な考え方や独創的な発想ができないという人は珍しくありません。特にテストや面接など重要な場面では、なるべく間違いのないようにと無難な答えを出しがちです。
創造力を高めるには、あらゆることに興味関心を持ち新しいことに挑戦することや、インプットとアウトプットがうまくできるようになることが大切です。
新しい経験をすると刺激になるだけでなく、視野が広がり新しい視点から物事をとらえられるようになります。さらに、普段話さない人と話すと、伝え方を考えながら話すため情報処理のスピードを上げられたり、これまでにはない新たな価値観を知ったりすることもできますよ。

キャリアアドバイザー
新しい体験や考え方を通して、インプットを増やすことで、新しいことやものを生み出す創造的思考力が鍛えられます。
③協働的思考力:人との違いと共通点を把握し自分の意見をまとめてみる
協働的思考力を高めるには、人との違いと共通点を把握するとともに、自分の意見をまとめてみるようにするのが効果的です。協働的思考力は、その場の空気を読んでみんなに合わせるということではありません。自分と人との違いや共通点を把握したうえで、周囲に合わせるわけでもなく、自分の意見を押し通すわけでもなく、お互いの意見や考えを尊重しながら問題を解決するための答えを導き出すことです。
そこで、家族や友人との会話中に意見や考え方が違ったときは、自分とは違う部分と共通している部分を見つけ出し、なぜ違いが生じるのかを考える癖をつけておきましょう。違いを把握したら、自分なりの意見をまとめてみます。ニュースを見て「自分ならこうする」と意識して考え、意見をまとめるようにするのも効果的です。

キャリアアドバイザーコメント堀内 康太郎プロフィールをみる
思考力を鍛えると、GPSテストの対策だけでなく、就活全般、また社会人になってからも非常に役に立ちます。
たとえば面接において、事前対策が難しいような、即効的な論理的思考力が問われる質問を投げかけられることもあります。「○○についてどう思うか」「なぜそのように考えるのか」など、思考能力の高さや価値観を知るための質問が多いです。こういった、一つの質問を深掘るような回答は、日常的に「なぜそう思ったのか」と考える癖をつけておかないと、面接の場でも発揮できません。
社会人になっても、この「なぜ」思考は重要です。たとえば、営業職では「なぜこの商品が顧客にとって役に立つのか」といった考えをもって営業できれば、顧客の購入意欲につながりやすくなります。社内でも、自分自身の考えを同僚や上司に理解してもらう際など「なぜそう思ったのか」という裏付けが必須になります。
これらはあくまで一例で、就活や社会人生活において思考力が問われる場面が非常に多いです。GPSテストの対策を通して思考力を鍛えられるのは、良い機会かもしれませんね。
基礎能力を上げよう! さらにGPSテスト対策を万全にする5つの対策方法

GPSテストでは思考力を鍛えるだけでなく、基礎能力を上げることでよりしっかりと対策ができます。基礎能力を上げる対策方法は主に5つです。GPSテスト対策を万全にするための5つの対策方法をチェックしておきましょう。
適性検査で落ちる人が必ずおこなうべき対策はこちらの記事で解説しています。
関連記事
適性検査で落ちる人が絶対やるべき6つの対策|原因や回答法も解説
適性検査で落ちる理由はさまざまありますが、能力検査で落ちたのか、性格検査で落ちたのかでまた理由は変わってきます。この記事ではキャリアアドバイザーが適性検査で落ちる理由でよくあるものと、その対策を詳しく解説します。
記事を読む

①玉手箱やSPIの参考書で基礎能力対策をする
GPSテストでは基礎能力も問われます。基礎能力を上げるのにおすすめなのが、玉手箱やSPIの参考書を活用することです。
玉手箱は日本エス・エイチ・エル(SHL社)が運営するWebテスト、SPIはリクルートマネジメントソリューションズが運営するWebテストです。いずれも制限時間があり、言語問題や非言語問題などが出題されます。
思考力の点ではGPSテストと異なりますが、基礎能力の部分は似ているといわれているため、これらの参考書で対策するのも良いでしょう。問題集も多数出版されており、手に入れやすいはずです。
長文問題もあるので、繰り返し練習することで読解力も身に付きます。練習する際は、制限時間をタイトにしておくのも1つの手段ですね。

キャリアアドバイザー
玉手箱やSPIのテストがある企業も受検する場合は、効率良く対策ができますよ。
SPIと玉手箱の違いはこちらの記事で詳しく解説しているので、ぜひチェックしてみてくださいね。
関連記事
玉手箱とSPIの違いは? 難易度や優先順位を徹底検証|各3つの対策
玉手箱とSPIは適性検査の一種ですが、取るべき対策は異なります。 この記事では検査内容の違いから、対策方法、難易度や勉強の優先順位などについてキャリアアドバイザーが解説します。 それぞれの違いを理解し、どちらが実施されても高得点を目指せるよう対策を進めましょう。
記事を読む

②公式サイトで問題傾向を把握する
先ほど例題を紹介しましたが、より具体的な問題を確認したい場合は、ベネッセのGPSテストの公式サイトを確認してみましょう。問題文や音声、動画が掲載されています。文章の長さや話す速度など、問題傾向を把握しておくと雰囲気もつかみやすくなります。
また、公式サイトには、項目ごとに詳しい測定内容も記載されています。たとえば創造的思考力は「問題をとらえ、解決の道筋を切り拓く力」、協働的思考力は「コミュニケーションを客観的にとらえ、共に解決に向かう力」などです。
何が測定されるのか内容の詳細を把握できると、より対策しやすいですよね。ぜひ一度目を通してみてくださいね。
③ニュース記事などで速読の練習をする
長文が多いGPSテスト対策では、限られた時間で問題や文章、選択肢を正しく読み、理解しなければなりません。そこでおすすめなのが速読の練習です。
- 1文字ずつ見るのではなく、10文字程度のかたまりとして見る
- かたまりとして見られるようになったら、視野を広げてさらに多くの文字をかたまりとして見る
- 慣れてきたらスピードを上げてみる
文字を1つずつ流して読むのではなく、かたまりとしてとらえることで、文章を読むスピードは格段に上がります。本が苦手な場合は、ニュース記事やコラムで練習するのもおすすめです。
また、知らない言葉や意味をあいまいに覚えている言葉が出てきたら調べておくことも大切ですよ。本番で知らない言葉が出てくると問題を正しく理解できず、誤った読み取り方をしてしまう可能性があるためです。正しく使える言葉が増えれば、記述式の回答で表現の幅も広がりますよ。
④就活サービスに登録して受検する
GPSテストを運営しているベネッセでは、「dodaキャンパス」というサービスを提供しています。dodaキャンパスは逆求人型の就活サイトです。スマートフォン用のアプリもあり、就活に関する情報を入手できるだけでなく適性検査(GPSテスト)も受けられます。
たとえばdodaキャンパスの適性検査の結果で弱い部分があったなら、その部分を強化できるように意識するなどできます。サービスに登録するのは無料なので、弱みを把握するためにも利用を検討してみてくださいね。
⑤自己分析をして性格テストに備える
就活では、性格テストを実施する企業も少なくありません。性格テストでは、企業が求める人物像と学生の人物像が合っているか、自社に合う学生かどうかを確認するだけでなく、採用後の配属先を決める際に活用することもあります。GPSテストは受かったのに性格テストで落ちた、というのは避けたいですよね。
性格テストでは企業が求める人物像と合っていない、矛盾がある、答えるのに時間がかかる、あいまいな答えが多いという場合、良い印象につながりません。

キャリアアドバイザー
自己分析をして自分の価値観や考え方を整理しておき、矛盾やあいまいな答えがないように備えておきましょう。
性格適性検査で落ちる原因はこちらの記事で詳しく解説しているので、あわせて対策を進めましょう。
関連記事
性格適性検査で落ちる6つの理由|実施理由から対策まで解説
性格適性検査で落ちてしまう人には6つの理由があります。 今回は性格適性検査を突破するために押さえておきたいポイントや、落ちてしまう理由、対策などをキャリアアドバイザーが紹介していきます。性格適性検査の理解を深め、就活を有利に進めていきましょう。
記事を読む

キャリアアドバイザーコメント高橋 宙プロフィールをみる
GPSテストを含めた適性検査の対策は非常に重要ですが、自己分析や企業分析、面接練習にかける時間も確保しなければなりません。それぞれの対策にかける時間の配分を間違えないよう、事前にある程度計画を立てておくようにしましょう。
基本的に、適性検査の対策として最低30時間程度は確保することをおすすめします。30時間確保するためには、1ヵ月前から対策を始めた場合、1日1時間勉強することになります。もちろん、適性検査がどれほど得意かによってかけるべき時間は異なります。もし苦手分野が多い場合は、1日プラス30分取り組むなど、柔軟に調整しましょう。
もし、1日1時間の確保が難しく、自己分析や面接練習の時間がなくなってしまう場合は、適性検査の練習に取り組み始める時期を早めて、1日30分に縮めるのがおすすめです。
適性検査や面接練習は、一気に取り組むのではなく、毎日コツコツ取り組むことで身に付きやすくなります。それぞれの対策にかかる時間を考え、就活の対策で使える時間から逆算し、対策時間の配分を決めるようにしましょう。
GPSテストについてよくある質問に回答!
GPSテストはほかの適性検査と比べると実施している企業が限られているため、詳しく知らない人も多いテストです。参考書や過去問もほとんどないことから、GPSテストを受けることになり、不安に感じる人もいますよね。
そこで、GPSテストを知った学生から寄せられるGPSテストに関するよくある質問に回答していきます。
GPSテストはどのようなテストですか?
GPSテストは適性検査の一つで、Web上で実施されます。テキスト問題のほかに音声や動画による問題も出題され、制限時間も設けられています。測定項目は大きくわけると「思考力」「基礎能力」「パーソナリティ」の3つです。
試験会場でおこなうわけではないため監視されることはないものの、管理者は受検者をランダムに見ることができます。
特に思考力に関する部分は一夜漬けではスコアを上げられないため、日頃から鍛える習慣を身に付けましょう。制限時間に対して問題数が多く、時間が足りないという感想を持つ人もいます。事前の対策だけでなく、本番では時間配分にも注意することが大切です。
GPSテストは対策が難しいと聞きますが対策すべきですか?
GPSテストは問題の型式が特徴的なうえに、過去問や回答集などがないため対策が難しいと言われています。制限時間に対して問題数が多いことや、音声・動画問題があることも難しいといわれる理由の一つかもしれません。
とはいえ、できる対策をしておくことで、気持ちにゆとりができます。特に独特な形式の思考力に関する問題は例文や音声・動画を確認すれば雰囲気や傾向がわかりますし、考え方も理解できます。日頃から思考力を上げるよう意識して物事を考えることも効果的です。
基礎能力が問われる問題もあるため、玉手箱やSPIの参考書を活用して練習するなど、できる限りの対策をしておきましょう。
GPSテストの内容を理解して問題イメージを固めておこう!
GPSテストは企業が学生の思考力を測定するために実施する適性検査の1つです。対策が難しいといわれていますが、何もできないわけではありません。テストの内容を理解して、効果的な対策をおこなうことでスコアアップが期待できます。
ただし、GPSテスト対策は短期間では納得できる成果が得られないものばかりです。特に思考力を上げるには日々意識することが大切なので、受検しなければならないとわかった時点でできることからはじめてみましょう。
「WEBテストの対策をする時間がない…」そんな人におすすめの対策方法
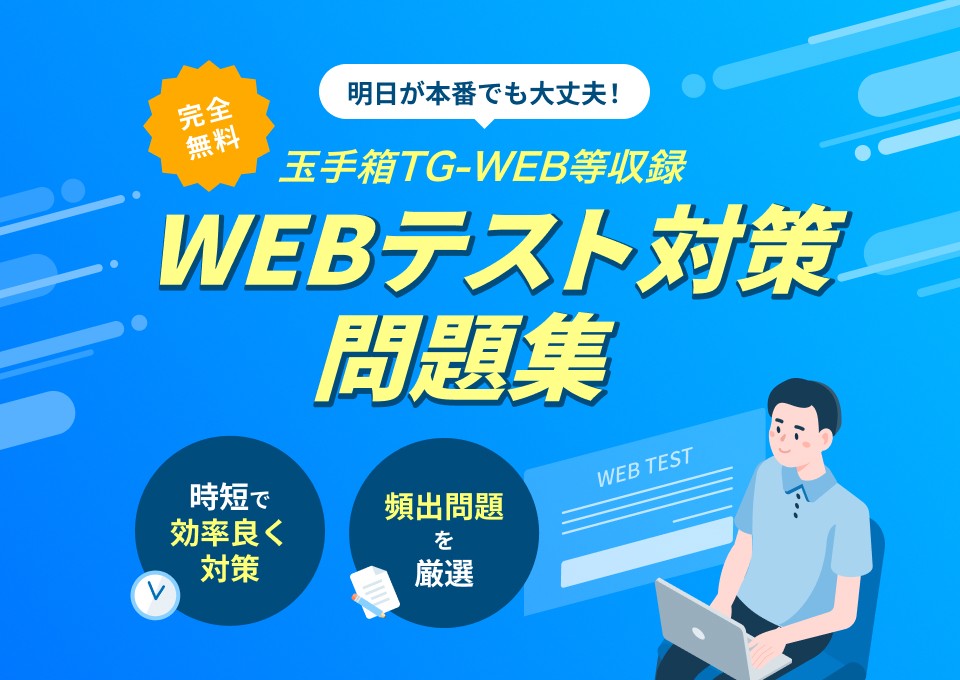
多忙な就活中、WEBテストを対策する時間がないと悩む人は多くいます。
そこで活用したいのが「WEBテスト対策問題集」です。頻出問題に絞って対策できるので、時間をかけずにWEBテスト対策ができます。
WEBテスト対策に時間が取れない人は、ぜひ活用することをおすすめします。

 キャリアパーク就職エージェントは、東京証券取引所グロース市場に上場しているポート株式会社(証券コード:7047)が運営しているサービスです。
キャリアパーク就職エージェントは、東京証券取引所グロース市場に上場しているポート株式会社(証券コード:7047)が運営しているサービスです。











GPSテストを受けることになったのですが、名前しか聞いたことがなくて不安です。