目次
- 二次面接が最終面接の新卒採用はアピール内容の深さで差をつけよう!
- 企業によって二次面接が最終面接になることはある!
- 企業が二次面接を最終面接にする4つの理由
- ①新卒採用担当者の負担を減らすため
- ②学生の確保率を上げるため
- ③書類選考を重視しているため
- ④リクルーター面談を選考フローに組み込むため
- 二次面接が最終面接の企業は、一次面接の合格率が高い可能性がある
- すべての企業で「二次面接が最終面接=内定を取りやすい」というわけではない
- 面接回数が少ないからこそ回答を深掘りされやすい!
- 書類選考の合格ラインはむしろ高めに設定されやすい!
- 二次面接が最終面接だと、他選考より2つの機会が少ない!
- そもそもアピールする機会が少ない
- 選考としての企業理解の機会が少ない
- 二次面接が最終面接の場合に企業が重視しているポイント
- 一次面接で重視している3つのポイント
- 二次面接(最終面接)で重視している3つのポイント
- 周りに差がつく! 最終面接となる二次面接の前にすべき事前準備
- 一貫性を意識! 一次面接の内容を細かく振り返ろう
- 現状から課題まで! より詳しく企業研究をしよう
- これで完璧! 二次面接が最終面接の際の頻出質問対策
- 自己PR:強みは1つに絞ってとことん深掘りしよう
- 志望動機:その企業だけの価値をエピソードに盛り込もう
- ガクチカ:独自性を意識して行動のプロセスからアピールしよう
- キャリアプラン:長期的な目線でなりたい姿を伝えよう
- 逆質問:社員だからこそ答えられる質問を2~3個用意しておこう
- 二次面接が最終面接の企業について学生からよくある質問に回答!
- 二次面接が最終面接の新卒採用は、エピソードを深めて内定を勝ち取ろう!
二次面接が最終面接の新卒採用はアピール内容の深さで差をつけよう!
こんにちは。キャリアアドバイザーの北原です。面接を控えた学生から
「新卒採用で、二次面接が最終面接になることはありますか? 」
「3回以上面接がある企業と比べて、評価しているポイントは変わりますか? 」
という質問をもらうことがあります。
新卒採用でよくイメージされる選考フローは「一次面接・二次面接・最終面接」ですが、企業によっては二次面接が最終面接というフローを採用している場合もあります。面接回数が少ないので、簡単に内定がもらえると思ってしまいがちですが、企業は選考を短くしたいという理由だけでフローを変えているわけではありません。
この記事では、二次面接を最終面接にする企業の目的や対策を解説します。対策は、事前準備とよくある質問に対する回答の2つに分けて紹介するので、しっかり準備をして挑みましょう。
【完全無料】
大学生におすすめ!
面接前に必ず使ってほしい厳選ツール
1位:面接力診断
40点以下は要注意!面接を受ける前にあなたの面接力を診断しましょう
2位:自己PR作成ツール
自己PRがまとまらない人は、AIツールを活用して自己PRを完成させよう
3位:志望動機作成ツール
5つの質問に答えるだけで、AIが受かる志望動機を自動で作成します
4位:最終面接マニュアル
通常の面接対策では不十分!最終面接は個別に対策が必要です
5位:面接回答集60選
見るだけでOK!面接でよく聞かれる質問と模範解答をまとめました
6位:逆質問例100選
面接官から「志望度が高い」と思われる逆質問例を厳選しています
7位:採用基準丸わかりシート
面接官が実際に使う評価シートで面接時の注意点を確認してください
企業によって二次面接が最終面接になることはある!

就活生

キャリアアドバイザー
そうですね。一般的にはあまりイメージがないかもしれませんが、二次面接を最終面接としている企業もありますよ!
結論から言うと、新卒採用でよくある選考フローとは異なり、二次面接が最終面接という企業もめずらしくはありません。特に中小企業では、この選考フローを採用している企業が多い傾向にあります。
また企業規模以外にも、技術職や医療関係など、専門的なスキルや知識を有しているかを重視して新卒採用をしている企業も面接回数が少ない場合が多いでしょう。すべてが当てはまるわけではないので、会社説明会などで選考フローをしっかり確認してから、対策をはじめましょうね。
企業が二次面接を最終面接にする4つの理由

一般的に企業が面接を複数回おこなうのは、学生と会う機会を増やして能力や性質、相性などを見極めたいという理由があります。では、二次面接が最終面接の企業はなぜ面接回数を減らしているのでしょうか。
ここでは、企業が二次面接を最終面接にする4つの理由を解説します。
①新卒採用担当者の負担を減らすため
二次面接を最終面接にする企業の一番の目的は、新卒採用に割く時間を減らすためです。
先ほども言ったように、面接回数を増やすのは学生を吟味するためですが、もちろん回数を増やせばその分採用担当のリソースが必要になります。採用担当は面接だけでなく、書類選考やメールの対応、そのほかの社内業務なども兼任している人がほとんどなので、企業によっては学生一人ひとりと何度も面接をして判断することが難しい場合もあるのです。
特に小さな会社だと社員数も少ないため、1人が抱える業務の範囲が広いことから、面接回数が増えるほどに、より採用担当の負担が大きくなってしまいます。面接を2回にすれば業務の偏りを少しでも軽減できるので、企業側に大きなメリットがあるといえます。
②学生の確保率を上げるため
採用担当の負担の軽減にもつながりますが、面接回数を減らすことで学生の確保率を上げたいという目的もあります。
一次面接・二次面接・最終面接と進める中で、当然ですが合否を出さなければいけません。つまり面接回数が増えれば増えるほど、不合格の学生の割合は増えてしまいますよね。
採用の倍率が高い企業なら、学生を絞るためにむしろ面接回数を増やしているかもしれませんが、倍率が高くない企業だと、絞ることでほしい人材が確保できなくなる場合があります。そこで二次面接を最終面接にすることで、学生を絞らずに確保できるというわけです。
また、優秀な学生を先に確保しておきたいという意図もあります。先に内定を出した企業が勝ちというわけではありませんが、ほかの企業が一般的な選考フローで面接をしている間に内定を出して、早期に人材を確保したいという目的です。
企業には「今年は〇人採用する」といったような採用目標人数があるので、採用コストを抑えつつ人材も確保するために、面接回数を減らしていると考えられますね。
③書類選考を重視しているため
新卒採用の選考フローの最初には、エントリーシート(ES)を提出する書類選考が設けられることが多いですよね。その書類選考を重視している企業も、二次面接を最終面接にする場合があります。
ESの質問内容は、志望動機や自己PR、ガクチカなど、学生の能力や価値観を判断できる項目がたくさんあります。新卒は特にポテンシャル採用の企業が多いので、書類選考で大体の判断をしてしまうという企業もいるのです。
このように書類選考を重視している企業だと、面接ではESの内容が合っているのか、基本的なコミュニケーション能力はあるのかなどを見ることになるので、回数が少なくても判断は可能になります。書類選考にコストをかけている分、面接が減っているということですね。
④リクルーター面談を選考フローに組み込むため
二次面接が最終面接になるのは、企業の新卒採用フローの組み方による場合もあります。よくあるのは、一次面接合格者にリクルーターがつき、面談を通して判断した後に最終面接へ進んでもらう流れです。
この場合は、一般的に二次面接や三次面接でおこなう判断をリクルーター面談でおこなっているので、二次面接が最終面接だとしても、簡単に最終面接に進めるわけではありません。
面接の間にリクルーター面談を入れるのは、企業への志望度やマッチ度を上げた状態で最終面接に進んでほしいという意図があります。より自社へのマッチ度が高い学生を採用するために、あえてこのフローで判断をしているのです。
三次面接の対策についてはこちらの記事で詳しく解説しています。よく聞かれる質問と回答のポイントについても紹介していますので、あわせて参考にしてみてくださいね。
関連記事
三次面接は最大の正念場! 質問対策と目的理解が合否の分かれ道
三次面接は一次・二次面接よりも念入りな対策が必要です。この記事ではキャリアアドバイザーが三次面接の特徴や対策のポイントを解説します。三次面接でよく聞かれる質問やおすすめの逆質問も紹介しているので、ぜひ参考にしてくださいね。
記事を読む

それ、一次面接の対策です!
最終面接の「ポイント」に気を付けよう
最終面接は一次、二次面接と実施目的が異なります。そのため、これまでのやり方だと落とされる恐れがあるので注意が必要です。
そこでおすすめしたいのが「最終面接マニュアル」です。この資料を活用すれば、最終面接だからこそ気をつけるべきポイントが一目でわかります。
無料で見れるので、今すぐ活用して面接対策につなげましょう。
二次面接が最終面接の企業は、一次面接の合格率が高い可能性がある

就活生
二次面接が最終面接だとすぐに内定をもらえる企業なのかなと思ってしまうのですが、選考も簡単なんですか?

キャリアアドバイザー
簡単とは言えませんが、3回以上面接をおこなう企業との合格率の違いはあります。
二次面接を最終面接にしている目的で「学生の確保率を上げる」というものがありましたが、これを1番の目的にしている企業は採用に困っているケースも考えられます。なぜなら、採用が上手くいっているなら、学生を見極めることができる面接回数を減らしてまで、学生を確保する必要がないからです。
このような傾向は、あまり知名度のない中小企業で見受けられます。そもそもその企業のことを知らなければ、学生も応募することができないため、応募者を集めること自体に苦労をするでしょう。
そのため、限られた応募者数の中から確実に学生を採用するために面接回数を減らし、一次面接の合格率も高めに設定するこどで、より多くの学生の確保するという狙いがあるわけですね。

キャリアアドバイザーコメント石川 愛プロフィールをみる
二次面接が最終面接で選考ハードルが低い企業は、「人がすぐに離職してしまうような危険な企業なのではないか」と不安を感じるかもしれません。しかし、選考ハードルが低いという理由だけで企業と判断することは、魅力的な企業を逃してしまう可能性があるため注意が必要です。
たしかに選考が少ない企業の中には、労働環境が良くない企業があるかもしれません。とはいえ、すべての企業がそうではありません。本文で説明されているとおり、優良企業にもかかわらず、学生の応募が集まらずに採用に悩んでいる企業もあります。このような優良企業を「二次面接が最終面接だから危険な企業だ」と判断してエントリーをしないことはチャンスを逃すことになりかねません。また、選考回数が多い企業であっても、学生によっては悪い労働条件で働く企業と感じることもあります。
選考回数で企業を判断するのではなく、説明会やOB・OG訪問を通じた正しい情報で企業を判断するようにしてくださいね。
すべての企業で「二次面接が最終面接=内定を取りやすい」というわけではない
二次面接が最終面接の企業の合格率が高い傾向にあるのは事実ですが、すべての企業がそうというわけではありません。合格率が高い企業もあれば、面接が2回だからこそ難しい選考もあるのです。
ここでは、二次面接が最終面接だからこそ、一次面接から難しくなる理由を解説します。
面接回数が少ないからこそ回答を深掘りされやすい!
二次面接が最終面接だと、一次面接から厳しく判断されることがあります。
一般的な新卒採用フローは「一次面接・二次面接・最終面接」ですよね。それぞれの面接で、コミュニケーション能力を判断されたり、入社意欲を見られたり、フェーズごとに判断する部分が違います。
つまり、面接回数が1回分減るということは、二次面接で判断していた点を一次面接からもとめられるということになるのです。だからこそ、あまり準備をせず一次面接に挑むと、思わぬ回答を深掘りされることもありえます。
二次面接が最終面接の場合は、一次面接からしっかり回答を準備して、何を質問されても答えられるようにしておきましょうね。
書類選考の合格ラインはむしろ高めに設定されやすい!
二次面接が最終面接の場合、書類選考の時点で厳しく能力や価値観を判断されることもあります。そのため、書類選考の合格ラインが他社より高く設定されやすいのです。
書類選考は企業ごとにフォーマットも異なるので、定番の質問だけでなく企業独自の質問への対策もしなければなりません。その点で、面接に進むこと自体が難しいので、選考全体の難易度も高くなってしまうのです。
二次面接が最終面接の企業のなかで、どの企業が書類選考を重視しているのか選考段階ではわからないので、しっかりES対策をして挑んでくださいね。
自己PRはどんな企業のESでも聞かれる項目です。まずは定番の質問から対策して、書類選考を突破しましょう。
関連記事
エントリーシートの自己PRを書くときのポイントや例文を紹介
エントリーシートの自己PRでは書き方のポイントを押さえて魅力的な文章でアピールしましょう! 今回は自己分析や他己分析など、エントリーシートの自己PRを作成する際の準備のポイントや、作成する際のコツを紹介していきます。学生からよくある質問にもキャリアアドバイザーが回答しているので、自己PR作成に悩んでいる方必見です!
記事を読む

キャリアアドバイザーコメント吉川 智也プロフィールをみる
二次面接を最終面接に設定している企業は、企業規模や業界によっても異なります。この傾向をつかむことで、ESや一次面接に向けた準備でどのように力を入れるべきか判断しやすくなりますよ。
企業規模の観点では、ベンチャー企業の中でも特に数十名規模の場合は面接回数が2回の企業が多いです。小規模の場合は社長と一緒に仕事をする機会もあるため、面接の早期に社長が同席して採用判断をしています。
業界に関しては、建設業界は平均選考回数が少ない特徴があります。建設業界に対して仕事が忙しいイメージを持っている学生が多いため、学生を早期に採用するために面接回数が少なく設定されていますよ。
このように企業規模や業界によって面接の平均回数が異なります。そして本文で説明されているとおり、面接回数が少ない企業ではESや面接で求められるレベルが高い傾向があります。面接回数が少ない傾向がある企業を志望している学生は、より力を入れてES作成や面接対策をするように意識しましょう。
二次面接が最終面接だと、他選考より2つの機会が少ない!

就活生
二次面接が最終面接だと、選考が早く終わって楽なんですよね。学生側にもメリットが多い気がします!

キャリアアドバイザー
たしかに早く終わるのはメリットですが、面接の回数が少ないことにはデメリットもありますよ。
面接回数が少ないことの学生側のメリットとしては、選考が早く終わり、内定が早くもらえるという点が挙げられますよね。しかし、選考が早く終わることには、デメリットもあることも忘れてはいけません。
ここでは、二次面接が最終面接の場合のデメリットを解説します。
そもそもアピールする機会が少ない
面接回数が少ないと、企業に自分の魅力をアピールできる機会も減ってしまいます。また、単純にアピールの時間も少ないので、伝えたいことが思うように伝えられないまま貴重な面接の機会が終わってしまう可能性があります。
また、面接が3回以上ある場合は一次面接で失敗しても二次面接で挽回することができますが、2回だと最終面接で挽回するしかなくなります。最終面接は最終面接で伝えなければいけないことがあるので、一度の失敗が大きな差になってしまうのです。
このように、アピールの機会が少ないと、伝えたいことを伝えきれないというデメリットがあります。
選考としての企業理解の機会が少ない
面接は、選考の場でもあり企業理解の場でもあります。面接の逆質問で社員の生の声を聞くことで、より志望度が高まることもありますよね。
しかし、二次面接が最終面接でその機会が少ないということは、会社を理解するチャンスも減っているということになります。社員の雰囲気や会社の環境も大切な要素なので、社員と触れ合う機会が少ないのは大きなデメリットといえますね。
二次面接が最終面接の場合に企業が重視しているポイント

二次面接が最終面接で面接の回数が少ないということは、それぞれの面接で学生を評価しているポイントも一般的なフローとは異なります。
ここでは一次面接で重視しているポイントと二次面接で重視しているポイントをそれぞれ3つずつ紹介します。
一次面接で重視している3つのポイント
まずは一次面接で重視しているポイントです。面接が3回以上の選考フローでは、一次面接はよく第一印象が重視されると言われています。
もちろん、第一印象も大切ですが、二次面接が最終面接の場合は何が異なるのか確認してみましょう。
①コミュニケーション能力があるか
一般的な選考フローと同じように、やはりコミュニケーション能力があるかどうかは重視されます。
どのような業界・業種だとしても、仕事においてコミュニケーションは不可欠です。そのため面接では、最低限質問に対して適切な回答ができるコミュニケーション能力を持っているのかを判断されています。
仕事におけるコミュニケーション能力があることを示すためにも、まずは結論から話すなど伝わりやすい話し方を意識してみてくださいね。またそのためにも、普段から話し方が上手な人のまねをしてみたり、自分の話し方が分かりやすいかなどを友人などにチェックしてもらうなどトレーニングを重ねて、コミュニケーション能力を鍛えておきましょう。
②基本的なビジネスマナーが身に付いているか
これも一般的な選考フローと同じで、基本的な敬語やマナーも重視されています。完璧な敬語やマナーでなくても大丈夫ですが、面接官に対して敬意を払おうという姿勢は必ず持つようにしましょう。
もし間違った敬語を使っても、それだけで不合格になることはありませんが、目上の人に対して丁寧な対応を心掛けていない姿勢は不合格につながる可能性が高いです。
完璧なビジネスマナーは難しくても、基本的なマナーと礼儀正しさを身に付けて「一緒に働きたい」と思ってもらえる対応を目指してみてください。
③自社とのマッチ度が高いか
二次面接が最終面接の場合は、一次面接の時点で企業とのマッチ度が高いかも判断される可能性が高いです。
企業の社風とマッチしているのか、理念に共感して活躍してくれそうなのかなど、本来なら二次面接以降で深掘りされるエピソードもあるでしょう。そのため、一次面接の時点から、企業がもとめる人物像や、社風、理念や事業の方向性などはチェックしておくとベストですよ。
また、同時に企業理解もアピールできる項目なので、面接機会が少ないからこそ、一石二鳥で伝えられるポイントはどんどんアピールしましょう。
一次面接の対策をおこないたい学生はこちらの記事を参考にしましょう。
関連記事
一次面接の対策はこれで完璧|よくある質問の答え方や入退室のマナー
一次面接は身だしなみや話し方、基本的なマナーなどを完璧にし、好印象を与えることが必要です。 この記事では、一次面接の特徴や重視される項目、よくある質問をキャリアアドバイザーが解説します。 服装やマナーなどイラストも参考にして一次面接を突破してくださいね!
記事を読む

二次面接(最終面接)で重視している3つのポイント
次に、二次面接(最終面接)で重視しているポイントです。二次面接でありながらも、入社への意欲の高さや志望動機の深掘りなどがされるので、3つのポイントを押さえてしっかり準備をしましょう。
①自社への理解度が高いか
企業そのものや事業への理解はマッチ度にもかかわりますが、最終面接でも重視されます。企業側も、会社のことを調べて理解しようとしてくれる学生の方が志望度が高い印象になるので、一次面接を経てより企業の理解度が深まったことをアピールしましょう。
会社ブログ、社員のSNSなどでも会社の雰囲気を想像できるので、最終面接までにさまざまな方法で調べて準備をしておくこともおすすめですよ。
②将来のビジョンが描けているか
最終面接では、将来のビジョンが描けているのかも重視されます。企業で働く中でのビジョンでも仕事の範囲を越えた将来のなりたい姿でも良いので、「どんな人になりたいのか」は考えておくと良いでしょう。
将来のビジョンを言語化できると、志望動機の最後に「その企業で成し遂げたいこと」も具体的に語ることができるので、志望動機もより魅力的になります。深掘りをされても答えられるように、できるだけ細かくイメージしてみてくださいね。
③入社意欲や入社への覚悟があるか
一般的な最終面接でもそうですが、やはり入社意欲や覚悟は重視されます。当然これだけで合否が決まるわけではありませんが、アピールできる機会が少ないからこそ、最終面接では企業に対する想いの大きさは重要なポイントです。
入社意欲は特定の質問で聞かれることもあれば、志望動機や将来のビジョンから判断される場合もあります。面接で定番の質問でも入社への意欲を伝えられるように、「なぜその会社に入りたいのか」を明確にしておきましょう。
キャリアアドバイザーコメント塩田 健斗プロフィールをみる
ここまでの説明を読んで、一次面接は二次面接に比べると入念な準備はいらないと感じた学生もいるのではないでしょうか。たしかに本文で説明されているとおり、二次面接(最終面接)の方がより深掘りされることが多いです。しかし、一次面接でも将来のビジョンについてなど、より深く質問されることがあるため注意が必要です。
一次面接と二次面接の内容に傾向はあるものの、実際にどのような質問をするのかは企業によって異なります。将来のビジョンへの共感を重視している企業であれば、一次面接から深く聞かれることもあります。
そのため、一次面接と二次面接で対策内容を分けるのではなく、一次面接であってもどのような質問をされても答えられるよう入念な対策をするようにしましょうね。
周りに差がつく! 最終面接となる二次面接の前にすべき事前準備

就活生
二次面接が最終面接だと、評価しているポイントも違うんですね! チャンスが少ない分、準備もしっかりしないといけないですよね。

キャリアアドバイザー
そうですね! 最終面接で失敗しないように、準備は入念にしておきましょう。
二次面接が最終面接の場合は、チャンスが少ない分、評価されているポイントでしっかりアピールすることが大切になります。簡潔にアピールするためにも、その場での回答ではなくしっかり準備をしましょう。
ここでは、最終面接の前にすべき2つの準備を紹介します。
一貫性を意識! 一次面接の内容を細かく振り返ろう
最終面接前に忘れずにおこなってほしいのは一次面接の振り返りです。特に二次面接が最終面接の場合は、一次面接でどのような質問をされて何と回答したかは重要になります。
なぜなら一次面接と二次面接での回答の一貫性が大切だからです。同時に何社も面接を受けていると、志望動機が混ざってしまうこともあるかもしれません。しかし、企業からすると、

面接官
志望動機がコロコロ変わっていて、本当に入社したいのかわからないな……。
と疑う要素になってしまうのです。そうならないためにも、志望動機や自己PRのエピソードの一貫性は意識しましょうね。
また、一次面接で聞かれなかったポイント、判断しきれなかった点を二次面接で評価する場合もあるので、一次面接の回答を深掘りされた場合の回答も用意しておくとベストですよ。
現状から課題まで! より詳しく企業研究をしよう
一次面接前に企業研究をしていたとしても、最終面接前にもう一度見直してみてください。特に企業のプレスリリースやSNSなどをチェックして、最新情報もしっかり押さえておくと安心です。
企業研究で調べたことをそのままアピールする場面はありませんが、志望動機や将来のビジョンなど、合否を判断する重要な項目に影響します。そのため、一次面接からの変化をアピールするためにも企業研究を見直して、より深くまで分析してみてください。
おすすめなのは、企業の強みだけではなく弱みや課題も分析することです。課題を分析すれば企業がどのような施策を打っているのかがわかり、その施策から企業の特徴も見えてきます。
施策の方向性で企業と自分の価値観が合っているかも変わるかもしれないので、面接前にあらためて考えてみてくださいね。
最終面接の結果はいつ頃発表されるのかについて、興味のある学生はこちらの記事を是非こちらの記事を参考にしてみてください。
関連記事
最終面接の結果が翌日でなくても心配不要! 結果の通知目安を解説
最終面接の結果に関して適切な情報を知ることで、不安が軽くなり、今すべきことに注力できるようになります。この記事では、最終面接の結果連絡の目安や結果待ちの期間ですべきことを解説します。今できることにしっかりと向き合い、不安を解消しましょう。
記事を読む
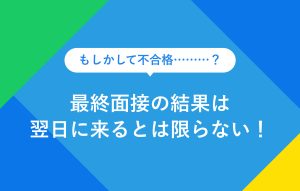
【実録】人気企業の面接で本当に聞かれた質問と回答例
面接で聞かれる質問に答えられるか不安ですよね。ただ、何を質問されるか分からず対策しようにも出来ない人は多いはず。
そこで、活用したいのが無料の「面接回答集」です。この資料があれば、三井住友銀行やソフトバンク、リクルートなどの人気企業の面接でも実際に聞かれたような質問とその答え方が一目でわかります。
どんな質問が来ても確実に回答できるようになれば、面接はもう怖くありません。今すぐ活用し、面接を突破するのに役立てましょう!
これで完璧! 二次面接が最終面接の際の頻出質問対策

二次面接が最終面接だと、アピールしたいポイントを長く話す機会がない可能性が高くなります。そのため、面接でよくある質問への回答も、より簡潔に伝えられるように見直してみましょう。
ここでは、面接の頻出質問の回答をより良くするためのポイントを解説します。
自己PR:強みは1つに絞ってとことん深掘りしよう
自己PRは、どんな面接でもESでも聞かれる、就活では定番の質問です。定番だからこそ、しっかりポイントを押さえることで、限られた時間でもあなたの魅力を伝えることができますよ。
自己PRで意識してほしいことは、1つの強みをとことん深掘りすることです。二次面接が最終面接の場合、たくさんのエピソードや強みをアピールするのは難しいので、その企業に合った強みを1つ選んでアピールしましょう。
どの強みをアピールするか迷ったら、その企業のもとめる人物像に一番近い強みを選んでみてください。もとめる人物像が持っている強みは、その企業で活躍している人が持っている要素であることが多いので、参考にしてみてくださいね。
志望動機:その企業だけの価値をエピソードに盛り込もう
志望動機では、企業研究の成果を発揮して、その企業だけの要素をエピソードに盛り込むことを意識しましょう。
同じ業界で似ている事業を展開している企業だと、どうしても志望動機が似てきてしまいますよね。しかし差別化ができていないまま面接に挑むと、「他社でもできるよね? 」といわれた際にうまく回答できない可能性があります。
そうならないためにも、その企業だけの価値はなんなのか、なぜその企業でなければいけないのかをしっかり言語化するようにしましょう。
面接で志望理由を伝える際にはポイントがあります。こちらの記事でも詳しく解説しているので、是非参考にしてみましょう。
関連記事
11例文|面接官の心をつかむ志望理由は4ステップで作成できる!
説得力のある志望動機を面接で企業に伝えるには、企業の質問の意図を汲み取り、論理的な構成を意識して志望動機を組み立てることが不可欠です。高評価を得る志望動機の作り方や、志望動機の例文をキャリアアドバイザーが詳しく解説します。周りと差がつく志望動機の作り方のコツを押さえて、選考突破を目指しましょう!
記事を読む

ガクチカ:独自性を意識して行動のプロセスからアピールしよう
ガクチカは、自己PRとは違った角度で強みをアピールできる項目です。ガクチカのトピックとしてはアルバイトや部活動、サークルなどが定番ですが、これらのテーマだと周りとかぶってしまうというデメリットもありますよね。
二次面接が最終面接の場合は、アピールの場が少ないからこそ、周りのエピソードに埋もれないようにすることがカギになります。そのためも、ガクチカの内容に行動のプロセスや当時の気持ちを加えて、独自性をプラスしてみましょう。
なぜ頑張ろうと思ったか、息詰まったときにどう感じたのかを書くことで、あなたの価値観のアピールにもなります。よりガクチカでアピールできる要素を増やすためにも、結果だけでなく過程にもフォーカスして伝えてみてくださいね。
ガクチカに悩んでいる学生は例文を参考にすると良いでしょう。こちらの記事で例文を紹介していますので、チェックしてみてください。
関連記事
ガクチカの例文15選! ガクチカがないときの見つけ方と書き方
ガクチカは面接やESの頻出質問 こんにちは。キャリアアドバイザーの北原です。学生から 「ガクチカで話すエピソードが見つかりません」「ガクチカでありきたりなテーマは避けたほうがいいですよね?」 といった悩みが多く寄せられて […]
記事を読む

キャリアプラン:長期的な目線でなりたい姿を伝えよう
最終面接では、キャリアプランのような長期的な目標も聞かれることがあります。
細かなキャリアプランが描けなかったとしても、まずは大枠で想像するだけでも大丈夫です。どのような社会人になりたいのか、3年後どういう先輩になりたいのかなど、想像しやすいところから描いてみましょう。
キャリアプランがしっかりしている学生は、物事を長期的な視点で捉える能力が高いと評価される場合があります。長期的な視点は社会人にとって必要な力なので、選考の時点で持っているのは大きなアピールになりますよ。
逆質問:社員だからこそ答えられる質問を2~3個用意しておこう
面接の最後の逆質問まで、企業理解とアピールのチャンスを逃さないようにしましょう。
逆質問では、ホームページや求人サイトではわからない情報を手に入れることができるので、会社の内部にいるからこそ答えられる質問をするようにしてみてください。そうすることで企業理解にもつながり、ミスマッチを防ぐことができます。
また、入社を見すえた質問やキャリアについての質問も良いですね。その会社で働く人が描くキャリアを知ることで、自分が描きたいキャリアが実現できるのかもなんとなくわかりますよね。このように、会社との相性を調べるためにも、逆質問は2~3個用意しておきましょう。
- 御社への入社を見据えたうえで、学生のうちにしておいた方がよいことがあれば教えていただけますでしょうか?
- 御社で活躍している人には共通点はありますか。また、それはどのようなものでしょうか?
- 御社の事業の中でも、特に商品開発に興味があるのですが、未経験でもチャレンジすることは可能でしょうか?
こちらの記事では最終面接の逆質問について、より詳しく解説しています。
関連記事
最終面接の逆質問一覧45選! 受かる逆質問の4つの共通点を大公開
最終面接の逆質問では企業が自分の軸にマッチするかを確かめると有効ですよ! この記事では最終面接でおすすめの逆質問、注意点などをキャリアアドバイザーが解説します。 面接前にいくつか用意して万全な状態で臨みましょう。
記事を読む

二次面接が最終面接の企業について学生からよくある質問に回答!
新卒の就活で二次面接が最終面接の場合はあるのか、その場合意識することは何かが気になる学生もいますよね。そのような学生の疑問へキャリアアドバイザーが回答します。
-
新卒の就活で二次面接が最終面接の場合はあるのでしょうか?
新卒の就活でも、二次面接が最終面接という場合はあります。特に中小企業は、採用担当者の負担を軽くするために面接を二次面接で終わらせる場合がありますよ。面接回数が多いと、その分採用担当者の負担が大きくなってしまうからです。また学生側も面接回数が多いという理由で企業を敬遠する場合があるので、採用倍率が低い企業のなかには面接回数を減らして学生の負担を軽くするところもあります。
-
新卒の就活で二次面接が最終面接となる場合何を意識すれば良いですか?
二次面接が最終面接となる場合、一次面接での受け答えに対する深掘り質問をされることが多いですね。また最終面接までに何度か面接がある場合は一次面接では簡単な質問をし、ガクチカや長所・短所など自己理解が深められているかどうかを確認されることがあります。
一方で二次面接が最終面接の場合、一次面接の時点で「当社の課題は何だと思うか」「入社後どのように活躍できるか」のような一歩踏み込んだ質問が多い傾向にあるため、業界・企業研究も徹底したうえで挑みましょう。
二次面接が最終面接の新卒採用は、エピソードを深めて内定を勝ち取ろう!
二次面接が最終面接の企業には主に4つの理由があり、理由によって選考が簡単な場合と難しい場合に分かれます。
また、面接が2回だからこそ、一般的な3回以上の企業とは評価のポイントが異なることも紹介しました。基本的なコミュニケーション能力はもちろん、最初からマッチ度が判断される場合もあるので注意してくださいね。
アピールの機会や企業理解の機会が少ない中でも、しっかり準備をしてアピールし、志望企業の内定を獲得しましょう。

 キャリアパーク就職エージェントは、東京証券取引所グロース市場に上場しているポート株式会社(証券コード:7047)が運営しているサービスです。
キャリアパーク就職エージェントは、東京証券取引所グロース市場に上場しているポート株式会社(証券コード:7047)が運営しているサービスです。











次に受ける企業の面接回数が2回だったのですが、二次面接が最終面接の企業ってよくあるのでししょうか?