目次
- 新卒1年目で辞めたい……その後の影響と選択肢を知って冷静に判断しよう!
- 新卒1年目で辞めるのはあり? 実際の退職事情から考えられる影響まで解説
- 新卒1年目で会社を辞める人の割合
- 新卒1年目で会社を辞めるメリット・デメリット
- 新卒1年目だけど辞めたい……決断の前に確認しておきたい7つのこと
- ①辞めたいと感じる原因は具体的に説明できるか
- ②誰にも相談せず勢いで辞めようとしていないか
- ③怒られただけなど一時的な感情に飲まれてないか
- ④辞めるのではなく部署移動などで解決はできないか
- ⑤休職をして落ち着く時間を取ることはできないか
- ⑥退職後の生活費は確保できているか
- ⑦退職後のプランは立てられているか
- 「新卒1年目で会社を辞める」その後に選べる5つの選択肢
- ①自分に合った仕事を探して転職をする
- ②資格や技術取得のために専門学校に通う
- ③実務スキルの取得を目指して職業訓練校を利用する
- ④アルバイトをしながら心の休養をする
- ⑤やりたいことを見つけてフリーランスになる
- これだけはしておきたい! 新卒1年目で辞める際の4つの準備
- ①退職理由を具体的に説明できるように整理する
- ②出来る限り早めに転職の準備を始める
- ③退職に際して必要な社内手続きを調べる
- ④すぐに再就職しないなら利用できる支援制度を調べる
- 新卒1年目で辞めない決断をしたあなたに伝えたいこと
- 一人で抱え込まず相談する
- 心身に不調が出るようであれば転職・退職の決断も大切
- 新卒1年目で辞めたいときこそ客観的な視点で行動指針を立てよう!
新卒1年目で辞めたい……その後の影響と選択肢を知って冷静に判断しよう!
こんにちは、キャリアアドバイザーの阿部です。最近働き始めた新卒1年目の人から、よくこんな相談を受けることがあります。
「新卒1年目だけど辞めたいです」
「辞めたいけど新卒1年目で転職するのは早すぎますか?」
確かに新卒1年目ですぐに会社を辞めてしまうと、その後の転職活動に影響するなどデメリットがあります。しかし新しい挑戦でスキルや経験を磨けたり、心身の不調を整えたりできるメリットもありますよ。
そこでこの記事では、新卒1年目で会社を辞めたい場合、本当に辞めるべきなのかを判断するためのチェックリストや、その後生じる影響も含めて解説します。動き出すために必要な情報が満載なので、ぜひ最後まで読んでくださいね。
【完全無料】
転職活動者におすすめ!
転職活動で使いたい診断ランキング
1位:適職診断
まずはあなたが受けない方がいい職業を確認してください
2位:業界&職種マッチ度診断
興味のある業界・職種とあなたの相性を診断しましょう
3位:自己分析ツール
あなたの基本的な性格から、転職活動で使える強み・弱みを診断します
4位:就活力診断
80点以上が合格!まずは力試しに自分の就活力を測定しよう
5位:マナー力診断
あなたのマナーは大丈夫?診断を受けて自分の苦手分野を把握しよう
【併せて活用したい!】
選考前に必ず使ってほしい厳選ツール
①自己PR作成ツール
自己PRがまとまらない人は、ツールを活用して自己PRを完成させよう
②志望動機作成ツール
5つの質問に答えるだけで、受かる志望動機を自動で作成します
新卒1年目で辞めるのはあり? 実際の退職事情から考えられる影響まで解説
「新卒1年目で辞めてもいいのかな?」そう悩むこともありますよね。新卒1年目という入社して間もないタイミングで退職する具体的なデメリットはイメージできなくとも、なんとなく「まずいかも」と感じるでしょう。
ただ、「ここで働きたい!」と思えるような会社に新卒で出会えたならいいですが、一度の就活で巡り合うのはなかなか難しいもの。多くの人がそうだからこそ、新卒1年目で退職して新たな仕事を探すこと自体はよくあることなのです。
そういった背景を踏まえて、ここからは実情として新卒1年目の退職事情や会社を辞めるメリット・デメリットについて具体的に解説していきます。
新卒1年目で会社を辞める人の割合
新卒1年目で会社を辞めたいと考えるのは、自分だけではないかと不安を抱く人も多いですよね。
厚生労働省が発表している新卒入社した人の離職率についてまとめた「新規学卒就職者の離職状況」によると、2010年以降、毎年約3割の人が新卒入社した企業を3年以内に辞めていることがわかります。
調査結果からみてもわかるように、新卒1年以内に「仕事が自分と合わなかった」と感じて辞める人は決して珍しいことではありません。離職後には前職とは違った職業に就職している人もいるので、まずはそういった実態があることを理解しておきましょう。

キャリアアドバイザー
キャリアアドバイザーが読み解く!働き方そのものが変わってきている
「今」の自分に必要なものが得られる場所でキャリアを積む人が増えている
厚生労働省のデータの通り、新卒で入った企業を3年以内に辞める人は一定数いる状況です。最近はあらかじめ転職を視野に入れたうえで就職活動をする学生も増えており、新卒入社した企業で経験を積んだ後にスキルアップを目指して転職をするケースも多いですよ。
企業側も新卒で総合職として一括採用し、企業内で人材を育て長期的に雇用するメンバーシップ型の雇用から、スキルや経験を持った即戦力人材を採用するジョブ型雇用をする企業が今後も増える見込みです。
社会情勢の変化に合わせて、働き方に対する価値観も変わりつつあります。以前のような終身雇用よりも自分自身に今本当に必要なものは何かを考え、それをかなえられる企業で働く人が増えているのです。今後の自分自身のキャリアについてしっかりと考え、どのようにステップアップしていきたいかを見すえた企業選びをすることが大切ですよ。
新卒1年目で会社を辞めるメリット・デメリット
新卒1年目で会社を辞めたいと考えている場合に確認しておきたいメリット・デメリットは、表のとおりです。
- 新しいことに挑戦できるスキルや経験を積める
- 仕事環境を改善できる可能性がある
- 生活環境や体調を整えられる
- 期間が短いとすぐに辞める癖がつく可能性がある
- 失業手当が貰えない可能性がある
- 新しい仕事が見つかるまで時間がかかるケースがある
会社を辞めるメリットは、新しいことに挑戦できてスキルや経験を積める点や仕事・生活環境の変化から体調を整えられることなどがありますよ。新しく挑戦したことが自分と合っていて、仕事が長続きすることも少なくありません。
一方新卒1年目で辞めてしまうと、経歴上の印象ではすぐに辞めるイメージがついてしまい、その結果転職活動が長引くケースも多いです。
また失業手当や賞与が貰えないリスクがある点も理解しておきましょう。

キャリアアドバイザー
辞める、辞めない、それぞれで絶対の正解はありません。自分のキャリアは自分で構築するものだからこそ、自分なりに考え抜いて判断することが大切です。
キャリアアドバイザーからあなたにメッセージ正解は自分の胸の中にしかない!
メリット&デメリットと現状を天秤にかけて今の自分に必要な選択をしよう!
新卒1年目で会社を辞める場合、その後のキャリアへの短期的な影響という観点ではデメリットの方が大きいといえます。ただし、これがあなたに当てはまるかどうかはあなたの置かれている状況次第です。
「とりあえず3年は同じ企業で働き続ける」そんな考え方にとらわれる必要はありません。新卒1年目で辞めるメリット・デメリットと自分の状況を天秤にかけ、今本当に必要なものは何かを冷静に判断しましょう。
合わない仕事、合わない上司、合わない職場環境で働き続けることは、精神的にも負担がかかります。それらを改善する余地はあるのか、ないとしたら転職で解決できるのか、決断する前に状況を冷静に確認しましょう。
まずはあなたが受けないほうがいい職業を確認しましょう
自分に合った職業・合わない職業を見つけることは、就活の成功に不可欠です。しかし、見つけることが難しいと感じる人も多いでしょう。
そんな時は「適職診断」を活用して、志望する職業と自分の相性をチェックしてみましょう。簡単な質問に答えるだけで、あなたの強みや性格が分析され、向いている職業・向いていない職業が診断できます。
自分の適職・適さない職業を今すぐチェックしてみてください。
また、業界も含めてより向いている職業を知りたい場合は「業界&職種マッチ度診断」がおすすめです。
新卒1年目だけど辞めたい……決断の前に確認しておきたい7つのこと

期待に胸を膨らませて新卒で入社したものの、思った以上につらい日々が続いて仕事を辞めたいと考えている。ただ、それが大きな決断になることを理解しているからこそ、なかなか動き出せない人も多いですよね。
そこでここからは、会社を辞める決断をする前に確認しておきたい7つのことを紹介していきますので、退職を迷っている人はチェックリストとして活用してください。
新卒で仕事を辞めることで、次がないかもしれないと悩む人はこちらの記事を参考にしてみてくださいね。後悔のない選択をするためのポイントを紹介しています。
【アドバイザーが解説】仕事辞めたいけど次がないときの4つの選択肢
仕事を辞めいたい理由に「自分だけ孤立している」と感じている人は、以下の記事も併せて読んで見てくださいね。
職場で孤立したら? 孤立した時期から考える11の対処法を大公開!
①辞めたいと感じる原因は具体的に説明できるか
まず会社を辞めようか考えている人は「辞めたい具体的な理由」を考えてみましょう。会社を辞めたいと感じる原因は特になく、自分に合わない気がして退職を考えているという人も少なくありません。
そのまま勢いで退職してしまうと、実は退職せずとも解決できる悩みであったと知っても手遅れです。
また、たとえば裁量権のなさがストレスになっていたとしても、そもそも新卒1年目の人は会社に慣れてもらうために、雑務や簡単な作業を任されているケースも少なくありません。
これに限った話ではありませんが、継続して勤めることで初めて成果や責任のある業務を任されるので、一定仕事の楽しさを感じられるようになるのには時間がかかるケースも珍しくありません。

キャリアアドバイザー
もう少し働いてみてから仕事が自分に合うか考えてみても良いと感じる場合は、少し様子を見て判断してみるのでも良いですよ。
②誰にも相談せず勢いで辞めようとしていないか
- 退職後に後悔する可能性がある
- 感情的になっていることに気付けないまま判断してしまう
次に考えるべきポイントは「誰にも相談せずに勢いで辞めようとしていないか」という点です。誰にも相談せずに辞めると、実は優良会社で退職後に後悔したなどのケースもあり得ます。
自分一人で決めることも大切ですが、誰かに相談すると客観的な意見をもらうことができます。他の人からみると実は優良会社だったなどのケースは少なくありません。
現在働いている会社が合っているのか客観的に判断・アドバイスをもらえるので、誰にも相談していない場合は、家族や知人に話をしてみると良いですよ。

キャリアアドバイザー
感情的に判断してしまうと、本当は合っていたかもしれないなどの後悔をしてしまう可能性もあるので、冷静になっても辞めたいと感じるか確認して慎重に判断してくださいね。
③怒られただけなど一時的な感情に飲まれてないか
- 理想的な判断が難しい
- 成長を期待して怒られている可能性がある
新卒1年目で辞めたいと考える理由で多いのが「怒られたから辞めたい」です。人に怒られた経験が少ない人は、仕事で強く指摘された際に落ち込んでしまう人も多いですよね。
怒られただけなど一時的な感情に飲まれている状態は冷静さを失っているため、理性的な判断が難しいです。
アルバイトとは違って仕事では責任のある業務にあたるので、業務内容を理解していなければ怒られてしまう可能性も少なくありません。怒られたことが原因で辞めたいと考えている場合は、一度時間を空けてみましょう。

キャリアアドバイザー
冷静になったときにもう一度考えてみたり、誰かに相談してみたりすると冷静に判断できますよ。
キャリアアドバイザーは実際にこうアドバイスしています!感情にのまれそうになったときの処方箋
つらいときは周囲に頼りながら現状を冷静に見つめよう
社会人になる以上は、学生時代よりも多くの責任を負う必要があります。これまでとは違ったものの考え方を強いられることもあるかもしれません。多くの人は正社員として働くことがどういうことかわからないまま社会人になるので、戸惑うのも仕方のないことです。
だからこそ強く叱られたり納得のいかないことで怒られたりすると、とてもつらいことのように思えて気持ちが落ち込むこともあるでしょう。「もう明日から会社に行きたくない」と感じることもあるかもしれません。つらいときは、一人で悩まずにその気持ちを誰かと共有してください。たとえば同期入社した仲間や大学時代の友人に相談すると、気持ちが軽くなりますよ。
今を乗り切れば、仕事の楽しさやできることが増える達成感を得られる余裕ができることもあります。一時の感情で行動せずに、まずは落ち着いて現状を見つめ直してみましょう。
怒られることがとにかくストレスな人は、一度この記事をチェックしてみてください。
関連記事
怒られるのが怖いのは「思考のクセ」が原因! 3類型から対策を導く
仕事で怒られるのは誰しも怖いと感じるものですが、怖いと委縮しすぎてしまうのも成果が出づらくなってしまうため良くありません。怒られるのが怖いという状況を抜け出すための考え方や、怒られないようにするための行動や対処法をキャリアアドバイザーが徹底解説します。
記事を読む

④辞めるのではなく部署移動などで解決はできないか
- 継続していると自分が違う部署に行けていたかもしれない
- 問題がある場合は対象人物が異動する場合がある
会社を辞める方法も一つの手段ですが、上司に相談できる人がいれば部署移動について聞いてみるのもおすすめですよ。人によって仕事でも合う・合わないがあり、現在行っている業務が自分に合っていないだけの可能性もあります。
たとえば上司や先輩・同僚などからの嫌がらせ・パワハラなどが原因で辞めたい場合は部署移動の話も対応してもらえる可能性があります。
ほかにも会社側もすぐに退職されると再び人材雇用に時間や労力を割く必要があるため、部署移動の相談に対して受け入れてもらえるケースもありますよ。
辞めたいと考えている内容によって部署移動も対応してくれるケースもあるので、まだ会社を続けたい意思が少しでもある場合は検討してみてくださいね。

キャリアアドバイザー
会社によっては人間関係で悩まないように、専用の相談室を設けている場合もあるので、活用してみるのもおすすめです。
⑤休職をして落ち着く時間を取ることはできないか
- 心身ともに疲労が蓄積される
- 精神的な病気のリスクがある
新卒1年目でも有給休暇が取れるケースもあるため、休職をして落ち着く時間を確保してみるのもおすすめです。体の疲れや心が疲れている場合は、休職を取ることで回復する可能性があります。
新卒1年目では慣れない仕事・業務をおこなうため、心も体も疲労が蓄積しやすいですよね。無理を続けてしまうと体調を崩してしまい、本格的に病院に通う必要があるケースも出ることもありますよ。
心や身体が疲れていると感じている場合は、休職を取って落ち着く時間を取ってみてください。

キャリアアドバイザー
身体を崩してしまうと、転職する場合にも悪影響が出る可能性があります。無理が続かないためにも、休職などの手段も視野に入れてみてください。
休職中に転職活動をする方法についてはこちらの記事で解説しています。
関連記事
休職中の転職活動はあり? 必須準備と企業からのリアルな印象を公開
休職中に転職活動をするのは法律的には問題ありません。しかし、自分の状況をチェックしないと選考が不利に働いてしまうことも。この記事では、専門家のアドバイスを交えてベストな選択をするためのチェックリストや企業が抱く懸念点などを紹介。自分が転職活動をしてもいいのか、しっかりとチェックしていきましょう。
記事を読む

⑥退職後の生活費は確保できているか
- 退職後の生活が苦しくなる
- 余裕がなくなった状態なので転職活動にも焦りが出やすい
会社を辞めたいと考えている場合は、退職後の生活費の確認をしてみてください。仮に会社を辞めたとしても、生活できない状態になっては意味がないですよね。
退職後にアルバイトをして生活費を補えば良いと考える人も多いですが、すぐに決まる保証もありません。
さらに生活するためにアルバイトを頑張る場合は、転職活動する時間も削られるため、時間が経つほど焦りが出やすいですよ。焦った状態で転職先を決めると、再度自分に合った会社ではなかったなどの状態になる可能性があります。
自分に合った仕事を探したいと考えている場合は、退職後の生活費を確保しながら転職先を探すようにしてください。

キャリアアドバイザー
退職後の生活費が確保されていると、心にも余裕ができますよね。目安として3~6カ月以上生活が送れる状態を確保しておくと良いでしょう。
休職中の給与の支払いについてはこちらの記事でその仕組みを解説しています。
関連記事
休職中に給与をもらえるかは会社次第! 利用できる3つの手当を紹介
休職中の給与がもらえるかは会社にもよりますし、休職の仕方にもよります。休職中の給与についてもらい方からもらえない場合の対策まで、キャリアアドバイザーが徹底解説します。
記事を読む

⑦退職後のプランは立てられているか
- 転職活動に時間がかかる
- 将来設計を立てにくい
会社を辞めたいと考えている場合は、退職後のプランが立てられているかも確認すべきポイントです。一時的な感情やプランを立てていない状態で会社を辞めてしまうと、転職活動がうまく行かなかった場合に生活ができなくなるなど大きなリスクがあります。
退職後のプランが立てられていない場合は、現在の会社で働きながら計画を立て、決まったときに辞めるのでも遅くはありません。
たとえばどうしても現在勤めている会社を辞めたい場合は、すぐに退職するのではなく働きながら転職活動を行い、次の仕事先が決まった段階で退職するのでも良いですよ。

キャリアアドバイザー
退職後の負担が少ない状態を作るためにも、今の会社を辞めた後のプランを計画できるか考えてみてくださいね。
その後どうするかのビジョンがなかなか浮かばない場合は、こちらの記事で解説している方法を実践してみてください。
関連記事
新卒で辞めたい場合の5つの選択肢|後悔しないためのチェックリスト
新卒で辞めたいと感じたときは、とにかく感情に任せた行動をせず、今必要な一手を理解することが大切です。この記事ではキャリアアドバイザーが辞めるべきかの判断軸とその後の選択肢を解説します。
記事を読む

「新卒1年目で会社を辞める」その後に選べる5つの選択肢

さまざまなことをチェックしたうえで「新卒で会社を辞める」と決断した場合、その後どのような選択肢をとることができるのかを事前に理解しておきましょう。今後のプランを立てるうえで役立つ情報になりますよ。
ここからは考えられる5つの選択肢について解説します。
①自分に合った仕事を探して転職をする
- 新しい経験・スキルを積める
- 自分に合った仕事を再確認
- モチベーションが高い状態で仕事に挑める
仕事を続けているなかで「自分に合ったことに挑戦していきたい」「会社を辞めたい」と感じている人も多いですよね。会社を辞めたい場合は、自分に合った仕事を探して転職してみるのも一つの選択肢です。
自分に合った仕事を見つけたい場合は、モチベーショングラフやマインドマップが有用です。自分のやりたいことを言語化して、将来の目標が達成できる仕事に就けるように転職活動をおこなうのが理想的ですね。
自分のやりたいことをできる仕事につけると、モチベーションが高まるため自分のパフォーマンスが高い状態で仕事ができますよ。

キャリアアドバイザー
自分の理想に近づくためにも、自分に合った仕事を探して転職をしましょう。
働きながら転職を成功させる方法については、こちらの記事の解説がわかりやすいですよ。
関連記事
転職活動は働きながらでもできる! 共倒れにならない転職5ステップ
この記事では、キャリアアドバイザーのアドバイスをふまえ、働きながらの転職活動を成功させるステップや働きながらの転職を効率的に進めるためのポイントなどについて解説していきます。仕事と転職活動の両立をしながら内定をつかむためにも、一緒に進め方をチェックしていきましょう。
記事を読む

②資格や技術取得のために専門学校に通う
- 仕事で活かせるスキルを身に付けられる
- 学校を通して新しい仕事に出会える可能性がある
資格や技術取得のために専門学校に通うのもおすすめです。専門的な資格や技術を持っていると、自分のスキルを磨けるだけでなく転職が有利になります。
さらに専門資格や技術を身に付けると、独立開業の道も開きやすいですよ。たとえば看護師や介護系の専門学校は、厚生労働省が指定する教育訓練施設であれば学費を抑えられる教育訓練給付金制度も活用できます。
介護や看護以外にもさまざまな専門資格が教育訓練給付金制度の対象となっているので、退職後の道として専門学校なども検討してみてくださいね。
③実務スキルの取得を目指して職業訓練校を利用する
- 現場で活きるスキル・知識を学べる
- 要件を満たすと給付金が受けられる
退職後の道では、実務スキル取得を目指して職業訓練校を活用するのもおすすめですよ。
職業訓練校とは失業中または求職中の人が、再就職を目指して技術を身に付けられる「職業訓練」を提供する施設になります。
国や自治体が直接運営する施設や、委託を受けた民間の機関が実施しているサービスです。さらに離職者向けや在職者向けの公共職業訓練があり、要件を満たすと給付金も受けられますよ。
下記のリストが具体的に学べる実務スキルの例になるので参考にしてみてください。
- Webデザイン
- プログラミング
- 簿記会計
- 医療事務・介護事務
- 社会保険・経理FP
現場で使えるスキルを学べるため、転職や将来で活きるスキルを身に付けたいと考えている人は職業訓練校の利用も考えてみましょう。下記の記事では職業訓練校の詳細をまとめていますよ。
関連記事
職業訓練校は目指す未来への近道|選び方×使い方がわかる4ステップ
職業訓練校とは、失業中・在職中問わず誰でも目指す未来のためにスキルを身につけられる公の施設。専門家のアドバイスを交えながら、その活用方法を詳しく解説します。
記事を読む

④アルバイトをしながら心の休養をする
- 精神的な負担から開放される
- 次に進むための英気を養える
新卒1年目で会社を辞める場合は、退職後にアルバイトをしながら心の休養を取るのもおすすめですよ。学校を卒業した後に始めての社会経験で、慣れない業務や責任のある仕事をするケースも少なくありません。
心が疲れている状態の場合は、休養を取ることも大切ですよね。しかし心の休養を優先しすぎて何もしていない状態だと、社会復帰のハードルが上がるかもしれません。その点、アルバイトをすると負担を抑えながら心を休養させやすいですよ。
収入がなく貯金が目減りしていくのもメンタルに影響を及ぼすこともあります。心が疲れていると感じる場合は、無理をせずにアルバイトをしながら心の休養を取ることも検討してみましょう。
キャリアアドバイザーからあなたにメッセージ「社会との接点」がメンタルを整える
自己肯定感を上げるためにもアルバイトは大切!
自宅にこもりひたすら休養をとっている時間があると、何かと考え込んでしまい後ろ向きな気持ちになってしまうこともあります。人によっては「こんな自分はダメだ」と自己肯定感が下がってしまうこともあるでしょう。
そんなときに大切なのが、些細なことでも社会の一員としての取り組みに参加することです。
上記で解説したようなアルバイトがおすすめですが、もしハードルが高いようなら習い事やボランティアでも構いません。「自分のためになることをしている」「誰かの役に立っている」そんなふうに思えることを生活に取り入れることで、気持ちが前向きになりますよ。
またそれらの取り組みを通して成功体験を積み重ねていくだけでも、自己肯定感は上がるはずです。新たな一歩を踏み出すときのために、今からスモールステップでできることをしてみましょう。
⑤やりたいことを見つけてフリーランスになる
- 自分のやりたいことに挑戦できる
- やりたいことを続けることで高いモチベーションが維持されやすい
マインドマップやモチベーショングラフを作成したときにやりたいことが見つかった場合は、退職後にフリーランスになる道を選ぶことも一つの方法です。
フリーランスは独立開業と同様で、自分一人で仕事をおこなう必要があります。しかし自分のやりたいことをできるので、モチベーションが高い状態で続けやすいです。
ただしフリーランスになる場合でも最初は収入が不安定になるので、アルバイトをしながらのフリーランスとしての活動を視野に入れてください。

キャリアアドバイザー
フリーランスの収入が安定したタイミングでアルバイトを辞めて、本業として取り組むのも一つの手ですよ。
これだけはしておきたい! 新卒1年目で辞める際の4つの準備

仕事を辞めたいけど、どのような手続き・準備をするべきなのか悩んでしまう人も多いですよね。
準備をしたうえで退職することが大切で、無計画に行動してしまうと想像以上に長引いてしまう状態も起こりやすいですよ。会社を辞める場合は、これから紹介する4つの準備からまず始めていきましょう。
①退職理由を具体的に説明できるように整理する
- 上司に退職したい理由を伝えやすい
- 自分が何をしたいのか明確になる
転職活動をおこなう場合は、退職理由を具体的に説明できる状態を作りましょう。転職先を見つける場合は、必ず前職の退職理由を聞かれます。退職理由は実際に採用した際に、どのような点に不満を抱くのか判断材料として確認されるポイントです。
たとえば「なんとなく会社を辞める」という理由では、採用しても気に入らない場合はすぐに退職されるのではないかなどと考えられてしまい、転職が難しくなります。
できれば退職理由も、将来に対しての転職であることがわかる、ポジティブな内容が良いですよ。自分のやりたいことを明確化し、目標に向かって進みたいため転職活動をしている人であれば、好感を抱いてくれる企業も少なくありません。
転職活動を有利に運ぶためにも、退職理由は具体的に説明できるように整理しましょう。

キャリアアドバイザー
言葉で伝えるのが難しい場合は、手紙やメールで伝えられるようにしてみると、整理しやすいですよ。
退職理由の伝え方についてはこちらの記事の解説がわかりやすいですよ。
関連記事
退職理由で引き止められない4ステップを解説|円満退社のコツも伝授
いざ退職するタイミングで引き止めをおこなう企業は多いです。スムーズに退職したい人向けに、引き留められないための退職理由の作り方や伝え方をキャリアアドバイザーが徹底解説します。
記事を読む

②出来る限り早めに転職の準備を始める
- 時間に余裕を持って転職先を探せる
- 空白期間を減らせる
会社を辞めるときの準備では、早めに転職活動を始める点も意識してください。理想的なのは、会社を辞める際に既に転職先が見つかっている状態です。転職先が見つかっていない状態で辞めてしまうと、空白期間が生まれるので注意が必要ですよ。
空白期間はアルバイトなどが必要になるうえに、必ず面接時に何をしていたのか聞かれます。次の仕事先が決まっていない状態で会社を辞めている状態は、計画性がないと判断されてしまう危険性がありますよ。
自分にあった転職先を見つけるためにも、できる限り早く転職の準備を始めてみてください。いつから準備を始めるべきかはこちらの記事で確認しましょう。
関連記事
退職は何カ月前に伝える? 意思表示~退職の所要時間から逆算しよう
退職は1~3ヵ月までに伝えるのが一般的で、1カ月前程度と就業規則で定めている企業も多いです。退職を伝えるタイミングと流れをキャリアアドバイザーが徹底解説します。
記事を読む

③退職に際して必要な社内手続きを調べる
会社を辞めると決断した場合は、退職に際して必要な社内手続きを調べてください。企業によって退職手続きは異なり、すぐに退職できる会社もあれば、必要手続きが終わるまで勤務する必要がある場合もあります。
たとえば転職先が決まっていても、社内手続きに時間がかかってしまうと内定が取り消される危険性がありますよ。退職に必要な社内手続きの例としては、下記が挙げられます。
- 退職届の提出
- 備品返却
- 書類受取
- 引継業務
退職を伝える目安としては、退職確定日の約1ヵ月前が望ましいです。就業規則に退職をする際に申告する期間が記載されているケースが多いので、確認しましょう。
退職届や退職願の違いなど、手続きに関する必須知識についてはこちらの記事で解説しています。
関連記事
退職願と退職届の違いは提出タイミング! 正しい書き方を見本で解説
退職しようと決意した人は、退職願や退職届についてもルールやマナーを知っておく必要がありあます。退職願と退職届の提出タイミングや書き方をキャリアアドバイザーが徹底解説します。
記事を読む

④すぐに再就職しないなら利用できる支援制度を調べる
すぐに再就職をしない場合は、支援制度など利用できる場所を調べましょう。国や自治体が実施している支援制度を活用すると、会社を辞めた後の負担を抑えられますよ。
下記が、再就職を目指す場合に使える主な支援制度です。
- 再就職手当
- 就業手当
- 常用就職支援手当
- 教育訓練給付制度
- 移転費
- 広域求職活動費
たとえば再就職手当は、雇用保険のなかに含まれている基本手当の3分の2以上を残して早期に再就職をした場合は、基本手当残り日数の70%を受け取れます。
また基本手当の3分の1以上を残して早期に再就職をした場合は、基本手当残り日数の60%の額をもらえます。(※2)
※2参照:ハローワークインターネットサービス
さまざまな支援制度が実施されているため、自分が活用できる制度を探してみてくださいね。失業手当などはハローワークを利用することになるため、こちらの記事もチェックしておきましょう。
関連記事
ハローワークとは? 使い方や就活に役立つ8つのサービスを徹底解説
仕事探しにハローワークを使ってみたいけど、利用のハードルが高く感じてしまう人もいますよね。この記事では、そんなあなたのためにハローワークでできることや上手な使い方、初めてハローワークに行くときに必要なものを専門家のアドバイスを交えて解説。私たちと一緒にハローワークについて学んでみましょう。
記事を読む

あなたが受けないほうがいい職業は?
3分でできる適職診断で確認してみよう
入社後の早期離職を避けるためには、自分に適性のある職業を選ぶことが大切です。しかし、それがどんな職業なのかが分からず悩む人も多いでしょう。
そんな人におすすめなのが「適職診断」です。40の質問に答えるだけで適性のある職業や受けないほうがいい職業を診断できます。
自分に適性のある職業を早めに知って、就活を成功させましょう。
新卒1年目で辞めない決断をしたあなたに伝えたいこと

メリットデメリットなどを比較したうえで、辞めたい気持ちはあるものの、まだ会社を辞めないと決断することもあるでしょう。
その選択をした場合に押さえておきたい2つの注意点を解説するので、自分の身を守るためにもしっかりチェックしてください。
一人で抱え込まず相談する
- 家族や友達
- 同僚や先輩
- 事務・会社で話せる人
- 転職エージェント
現在の会社で働き続けると決断した人でも、一人で抱え込まずに周りの人に相談しましょう。たとえば会社の上司や先輩に言いにくい場合は、同僚や事務の人に伝えてもらうのでも良いですよ。
相談相手がいない場合は、相談先として転職エージェントの活用も検討してみてください。一人で抱え込まずに相談できる場所・相手を作って仕事を続けましょう。
心身に不調が出るようであれば転職・退職の決断も大切
- 体調が崩れる前に次に進める
- ミスが起きにくい
- 心身ともに休められる
「頑張って続けているけれど、最近疲れやすい」などと悩んでいる人も多いですよね。
会社を辞めずに続ける場合で、心身に不調が出た際には無理をせずに転職や退職を決断しましょう。心身に不調が出ている状態は、自分自身のパフォーマンスが下がっています。
また、さらに体や心を崩してしまう危険性があるため、無理して続けるくらいなら転職・退職など環境を変えて自分を守る選択肢は常に持っておきましょう。
継続しようと考えている場合は、心身の不調などにも注目しながら将来を考えてみてください。
転職するかどうかの判断についてはこちらの記事の解説が判断材料になりますよ。
関連記事
転職したいと悩んだら確認必須の5つのポイント|不安の解消法も解説
転職したいときこそ冷静な判断や転職理由の整理が重要です。転職市場の実態から転職したいと考えている人がやるべきことをキャリアアドバイザーが徹底解説します。
記事を読む

新卒1年目で辞めたいときこそ客観的な視点で行動指針を立てよう!
ここまで、新卒1年目でも会社を辞めるべきなのか、チェックポイントや準備方法について解説してきました。
「ここで働きたい!」と思えるような会社に新卒で出会えたならいいですが、一度の就活で巡り合うのはなかなか難しいものです。多くの人がそうだからこそ、新卒1年目で退職して新たな仕事を探すこと自体はよくあることですよ。
チェックポイントを参考に、本当に辞めた方が良いと感じた場合は、早めに行動しましょう。自分の目指したい将来に向けて行動を起こすと、心の負担が減るだけでなくモチベーションが高い状態で仕事ができるようになります。
自分に合った仕事と巡り合うように、ライフプランを設計して希望のキャリアをつかみましょう。

 キャリアパーク就職エージェントは、東京証券取引所グロース市場に上場しているポート株式会社(証券コード:7047)が運営しているサービスです。
キャリアパーク就職エージェントは、東京証券取引所グロース市場に上場しているポート株式会社(証券コード:7047)が運営しているサービスです。





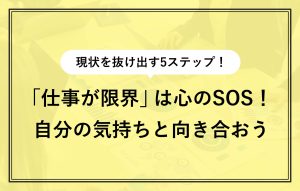

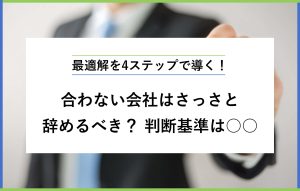






ただし退職を考える場合は、感情的になるのではなく、一度冷静になって会社を辞めるメリット・デメリットを把握しておくことが大切ですよ。自分の将来に関わる話なので、冷静に分析を行って決めるようにしましょう。