目次
- 給料が高い仕事はたくさんある! 探し方×選び方を理解しよう
- 最初に理解しておこう! 「給料」に関する前提知識
- 給料は基本給+各種手当で構成される
- 日本の平均年収は約460万円
- 給料が高い(年収800万円超の)人は全体の約10%
- 給料が高い仕事を目指すなら必ず理解しておきたい3つのこと
- ①給料が高い仕事にはそれ相応の理由がある
- ②高い給料を手にするにはある程度の時間を要する
- ③新卒から給料が高い仕事に就くことにはリスクもある
- 給料が高い仕事に見られる4つの特徴
- ①専門性や希少性が高い
- ②経験が求められる
- ③成果が反映されやすい
- ④安定して高い需要がある
- 給料が高いのはどんな仕事? 高年収の仕事TOP20を紹介
- 専門知識を活かせる! 文理別におすすめの高収入の仕事を厳選して紹介
- 文系におすすめの給料が高い仕事3選
- 理系におすすめの給料が高い仕事3選
- 給料が高い仕事を目指すならライバルとの差別化や適職の見極めが不可欠
- ライバルに差を付けるには? 給料が高い仕事に就くためにできる3つのこと
- ①難易度の高い資格を取得する
- ②専門知識を習得する
- ③語学力を高める
- 「給料が高い」以外の条件も大切! 仕事を選ぶうえで重要な5つの要素
- ①やりがいを感じられるか
- ②社風が自分の価値観と合っているか
- ③無理なく働き続けられる環境か
- ④自分が成長できるか
- ⑤自分の長所やスキルを活かせるか
- 自分に合った給料が高い仕事を見極めるための3つの準備
- ①自己分析:「何をしたいのか」と「何ができるのか」の2軸から考える
- ②OB・OG訪問:高年収の仕事だからこその魅力や大変な部分を聞く
- ③インターンシップ:自分がその環境になじめるか判断する
- 給料が高い仕事の特徴や実態を理解して自分に合った仕事を見つけ出そう
給料が高い仕事はたくさんある! 探し方×選び方を理解しよう
こんにちは、キャリアアドバイザーの北原です。就活を控えた学生から、
「できれば給料が高い仕事に就きたいです」
「給料が高い仕事に就くには、どうすれば良いのでしょうか?」
といった質問をよく受けます。給料が高い仕事は世の中に数多く存在しますが、給料が高いのにはそれ相応の理由があり、誰でも簡単に就けるものではありません。そのため、給料が高い仕事を目指すのであれば、本当に自分に合った仕事を見極めたうえで、入念に準備を進める必要がありますよ。
この記事では、給料が高い仕事の特徴や就くためにできること、適職の見極め方などについて解説していきます。給料が高い仕事を目指している人はぜひ参考にしてくださいね。
まずはあなたが受けないほうがいい職業を確認しましょう
自分に合った職業・合わない職業を見つけることは、就活の成功に不可欠です。しかし、見つけることが難しいと感じる人も多いでしょう。
そんな時は「適職診断」を活用して、志望する職業と自分の相性をチェックしてみましょう。簡単な質問に答えるだけで、あなたの強みや性格が分析され、向いている職業・向いていない職業が診断できます。
自分の適職・適さない職業を今すぐチェックしてみてください。
また、業界も含めてより向いている職業を知りたい場合は「業界&職種マッチ度診断」がおすすめです。
最初に理解しておこう! 「給料」に関する前提知識


就活生

キャリアアドバイザー
給料が高い低いの基準は人によって異なるため、明確な基準はありません。給料の高い仕事を目指すのであれば、自分なりの基準を考えておきましょう。
まずは、給料に関する前提知識について解説します。自分にとっての給料が高い仕事の基準を明確にするためにも、ここで給料の仕組みや実態を押さえておきましょう。
給料は基本給+各種手当で構成される
給料とは厳密には基本給(経験や能力、勤続年数などによって決まる毎月固定額が支給されるもの)のことを指しますが、世間一般では「月収」や「年収」と捉える人が多い傾向にあります。
月収とは、基本給に役職手当や残業手当などの各種手当を加えた金額を指します。さらに月収から税金や社会保険料を差し引いたものを「手取り額」と言い、これが毎月実際に受け取る金額です。

一方の年収とは、その年に勤務先から支払われた総支給額を指し、1~12月の月収に賞与を加えた額が年収となります。
年収=12カ月分の月収+賞与
一口に給料と言っても、それが月収を指すのか年収を指すのかで意味合いが異なります。給料の金額を確認する際は、月収と年収のどちらの金額を指しているのかをチェックするようにしましょう。

キャリアアドバイザー
なお、企業によっては「年俸制」を採用している場合もあります。年俸制では1年間に支払われる金額があらかじめ決まっており、基本的に12分割された金額が毎月支払われます。
日本の平均年収は約460万円
国税庁の令和5年分民間給与実態統計調査によると、日本の平均年収は約460万円となっています。平均年収は年度によって多少の上がり下がりがありますが、ここ数年は450万円前後で推移しています。
なお、年齢別の平均年収は、以下の通りです。
- 20~24歳:約267万円
- 25~29歳:約394万円
- 30~34歳:約431万円
- 35~39歳:約466万円
- 40~44歳:約501万円
- 45~49歳:約521万円
- 50~54歳:約540万円
- 55~59歳:約545万円
- 60~64歳:約445万円
- 65~69歳:約354万円
上記の通り、30代後半から40代前半にかけて、全体の平均年収である460万円に届く人が多い傾向にあります。仮に「給料が高い=日本の平均年収より高い」と定義するのであれば、「40歳前後で500万円前後の年収を目指せる」ことが一つの基準となるでしょう。
給料が高い(年収800万円超の)人は全体の約10%
「高い給料」に明確な基準はありませんが、一般的には年収800万円を超えると給料が高いと捉える人が多い傾向にあります。
ただし、国税庁の令和5年分民間給与実態統計調査によれば、年収800万円を超える人の割合は約10.1%と、全体のわずか1割程度です。
- 100万円以下:8.7%
- 100万円超200万円以下:14.0%
- 200万円超300万円以下:15.0%
- 300万円超400万円以下:16.7%
- 400万円超500万円以下:14.4%
- 500万円超600万円以下:10.1%
- 600万円超700万円以下:6.5%
- 700万円超800万円以下:4.5%
- 800万円超900万円以下:3.0%
- 900万円超1,000万円以下:2.0%
- 1,000万円超1,500万円以下:3.7%
- 1,500万円超2,000万円以下:0.9%
- 2,000万円超2,500万円以下:0.2%
- 2,500万円超:0.3%
もちろん、なかには年収1,000万円やそれ以上を目指したい人もいるでしょうが、年収800万円を超えるのはそう簡単なことではないことは覚えておきましょう。
【完全無料】
大学生におすすめ!
就活準備で使いたい診断ランキング
1位:適職診断
まずはあなたが受けない方がいい職業を確認してください
2位:業界&職種マッチ度診断
興味のある業界・職種とあなたの相性を診断しましょう
3位:自己分析ツール
あなたの基本的な性格から、就活で使える強み・弱みを診断します
4位:エントリーシート作成ツール
業界特有の質問にも対応! そのまま使えるESが作れます
5位:マナー力診断
あなたのマナーは大丈夫?診断を受けて自分の苦手分野を把握しよう
【併せて活用したい!】
選考前に必ず使ってほしい厳選ツール
①自己PR作成ツール
自己PRがまとまらない人は、ツールを活用して自己PRを完成させよう
②志望動機作成ツール
5つの質問に答えるだけで、受かる志望動機を自動で作成します
給料が高い仕事を目指すなら必ず理解しておきたい3つのこと

「給料が高い」というのは、多くの人にとって魅力的です。せっかく社会に出て働くのであれば、なるべく高収入を目指したいという気持ちもあるかと思います。
ただ、給料が高い仕事を目指すのであれば、必ず理解しておきたいことが3つあります。まずはこの3点を押さえたうえで、具体的な目指し方を考えていきましょう。
①給料が高い仕事にはそれ相応の理由がある
最初に理解しておきたいことは、給料が高い仕事にはそれ相応の理由があるということです。
給料は労働の対価として支払われるものであるため、給料が高いということは、それだけ大変な部分や厳しい部分があるということを意味します。
- 高度な知識やスキルが必要だから
- 業務上の責任やプレッシャーが大きいから
- 高いノルマや目標を達成しなければならないから
楽に大金を入手できる仕事があればベストですが、そういった仕事はまず存在しません。給料が高い仕事にはそれ相応の理由があることは、しっかりと認識しておきましょう。

キャリアアドバイザー
インターネットやSNSでは「誰でも簡単に年収○○万円を目指せる」といった仕事もありますが、そういった仕事は詐欺や違法なものである可能性もあるため、十分な注意が必要です。
②高い給料を手にするにはある程度の時間を要する
次に理解しておきたいことは、高い給料を手にするにはある程度の時間を要するということです。
給料が高い仕事は、最初から給料が高いわけではありません。たとえば、高収入と言われることの多いITエンジニアであっても、初任給は一般的な水準と変わらないケースが多く、ある程度の経験を積まなければそれほど給料が上がらないのが一般的です。
また、初任給の高い弁護士や公認会計士であっても、資格を取得するためには数年単位の勉強が必要となります。
このように高い給料を手にするには、ある程度の時間が必要です。最初から高収入を実現できる仕事はごく一部であるため、その点も認識しておきましょう。
③新卒から給料が高い仕事に就くことにはリスクもある
もう一つ理解しておきたいことは、新卒から給料が高い仕事に就くことにはリスクもあるということです。
給料が高い仕事は学生からの人気が高く、競争率も激しくなりがちです。そのため、給料が高い仕事ばかりを狙っていると、なかなか内定を獲得できず、最悪の場合は一社からも内定を得られないリスクがあります。
また、給料の高い仕事には肉体的や精神的な負担が大きいものもあり、一般的な仕事よりも入社後のミスマッチが生じやすいというリスクもあります。
このように、新卒から給料が高い仕事に就くことには一定のリスクが伴います。もちろん、その仕事に対して強い興味や熱意があるのであれば積極的にチャレンジして良いのですが、一定のリスクが伴うことも事前に認識しておきましょう。

キャリアアドバイザーコメント成瀬 遼プロフィールをみる
仕事を選ぶ際に給料を重視することは何も悪いことではありません。ただし、志望理由を「給料が高いから」にするのはおすすめしません。企業はできるだけ会社にマッチし将来活躍する人材を確保したいと思っているため、条件だけで応募する学生を好まない傾向にあります。
また、給料が高いということは記事にもあるとおり「何かしら理由がある」ということを理解しておかなければなりません。高い給料を得るために無理して働き続けるのは心身ともに悪影響を与える恐れがあります。
仕事や企業を選ぶ際には、自分に本当に合っているかを重視するようにしましょう。自分に合っている仕事であれば、成果につながり、結果的に給料が高くなるということもありますよ。
給料が高い仕事に見られる4つの特徴

高収入を目指せる仕事は世の中に数多く存在しますが、給料が高い仕事にはいくつかの特徴があります。
そこでここからは、給料が高い仕事によく見られる4つの特徴について確認していきましょう。これらの特徴を把握しておくことで、給料が高い仕事を見極めやすくなりますよ。
①専門性や希少性が高い
給料が高い仕事の特徴としては、専門性や希少性が高い点が挙げられます。
- 医師
- 弁護士
- ITエンジニア
専門性や希少性が高い仕事は担い手が不足しがちで、社会からの需要が高い傾向にあります。そのため、そういった仕事ができる人材に対しては、企業は給料を上げて確保する必要があり、高収入を実現しやすいのです。
また、専門性や希少性が高い仕事は、資格や特別な知識・スキルが求められるものも多く、それらを得るための努力が評価されて、給料の高さにつながっている側面もあります。

キャリアアドバイザー
専門性や希少性が高い仕事はAI(人工知能)による代替が難しいため、将来性の面でも期待できますよ。
②経験が求められる
給料が高い仕事の特徴としては、経験が求められる点も挙げられます。
- 航空機操縦士
- エンジニア系全般
- マネジメント系全般
経験が求められる仕事は、その経験を積むまでに長い年月を要するのが一般的です。たとえば、航空機操縦士(パイロット)の場合、航空会社に入社してから副操縦士になるまでに3年前後、副操縦士から機長に昇進するまで10年前後かかると言われています。
経験が求められる仕事に就くためには、長年の経験と実績が必要となり、その点が評価されて給料の高さにつながっているのです。
③成果が反映されやすい
成果が反映されやすいことも、給料が高い仕事の特徴の一つです。
- 営業職
- 販売職
- タクシードライバー
業績や売上などの成果が給料に反映されやすい仕事であれば、成果を出した分だけ給料が上がるため、努力や工夫次第では20代で高年収を目指すこともできます。
一方で成果が反映されやすい仕事は、成果を出せなければ給料がまったく上がらない可能性があることも認識しておきましょう。思うような成果が出せなければ、場合によっては採用時の給料で働き続けなければならないケースもありえます。
④安定して高い需要がある
安定して高い需要があることも、給料が高い仕事の特徴の一つとして挙げられます。
- 電気工事士
- 土木作業員
- 電車運転士
たとえば、電気・ガス・水道や道路・公共交通機関、通信・運輸などは、私たちが生活するうえで欠かせませんよね。そういった安定して高い需要がある仕事は、仮に供給がストップすると私たちの生活に大きな混乱をもたらすため、そこで働く人たちに支払われる給料も高い傾向にあるのです。
また、安定して高い需要がある仕事であれば、仮に不況が訪れたとしても需要が大きく減ることがなく、急に給料が下がるといったリスクもほとんどありません。
これから需要が増える仕事については、以下の記事で詳しく解説しています。あわせて参考にしてみてくださいね。
関連記事
これから需要が増える仕事18選|持っておきたいスキルや資格も解説
これから需要が増える仕事に就くには特徴の理解が欠かせません。この記事ではキャリアアドバイザーがこれから需要が増える仕事の特徴や注意点を解説します。7つの領域別にこれから需要が増える可能性が高い仕事も18つ紹介しているので、ぜひ参考にしてくださいね。
記事を読む
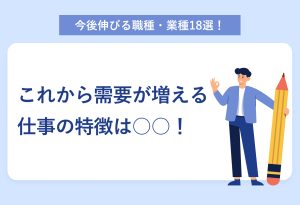
給料が高いのはどんな仕事? 高年収の仕事TOP20を紹介
ここからは、厚生労働省の令和5年賃金構造基本統計調査にもとづいた高年収の仕事TOP20を紹介します。給料が高い仕事には具体的にどんなものがあるのか、ここでイメージを掴んでおきましょう。
- 航空機操縦士:約1,779万円
- 医師:約1,437万円
- 法務従事者:約1,122万円
- 大学教授(高専含む):約1,075万円
- その他の経営・金融・保険専門職業従事者:約948万円
- 歯科医師:約924万円
- 管理的職業従事者:約885万円
- 大学准教授(高専含む):約862万円
- 公認会計士・税理士:約747万円
- 研究者:約740万円
- 輸送用機器技術者:約712万円
- 高等学校教員:約699万円
- 大学講師・助教(高専含む):約692万円
- 電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く):約688万円
- 獣医師:約686万円
- システムコンサルタント・設計者:約685万円
- 小・中学校教員:約661万円
- 企画事務員:約646万円
- 金融営業職業従事者:約637万円
- 建築技術者:約633万円

キャリアアドバイザー
高年収の上位に位置する仕事は専門性や経験が求められるものが多く、高い給料を手にするのは簡単ではないことを示していますね。
高収入を目指せる珍しい仕事についてはこちらの記事でも紹介しているので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
関連記事
珍しい仕事50選! 本当にやりたい仕事を見極める分析3ステップ
「珍しい仕事」という定義は人によって違いますが、あまり知られていないなどといった基準で見れば実はたくさんあります。この記事ではキャリアアドバイザーが、就活生におすすめの珍しい仕事を50種紹介し、就くための対策も解説します。
記事を読む

専門知識を活かせる! 文理別におすすめの高収入の仕事を厳選して紹介

就活生
できれば大学で学んだことを活かしたいと考えているのですが、そういった仕事はあるのでしょうか?

キャリアアドバイザー
もちろん、ありますよ。文理別におすすめの高収入の仕事を見ていきましょう。
ここからは、文系理系それぞれにおすすめの給料が高い仕事を紹介します。大学での専攻を活かしたい場合には、参考にしてみてください。
文系におすすめの給料が高い仕事3選
まずは、文系におすすめの給料が高い仕事を3つ紹介します。
給料が高い仕事は理系向けのものが多いと思われがちですが、文章作成能力や経済・法律の知識といった、文系ならではの強みを活かして高収入を目指せる仕事も数多くあります。
これから紹介する仕事は、そういった特徴を持つ文系におすすめの仕事をピックアップしているので、自分に合うものがないか順にチェックしてみてくださいね。
①歩合制の営業職
歩合制とは、個人の業績や成果に応じて報酬を支払う仕組みのことで、「出来高払制」や「インセンティブ制」などと呼ばれることもあります。
- 保険業界
- 不動産業界
- 自動車業界
営業は売り上げに直結する仕事でもあるため、従業員のモチベーションを上げるために歩合制を採用している企業は少なくありません。歩合制の営業職であれば、成果を出せばその分給料が上がるため、頑張りや工夫次第では早い段階で高収入を目指すことも可能です。
もちろん営業で一定の成果を出すのは簡単なことではありませんが、基本的に営業職は専門知識や経験がなくても始めることができ、文系出身者ならではのコミュニケーション能力や柔軟な発想力を活かしやすいため、文系におすすめの仕事と言えます。
②コンサルタント
コンサルタントは、さまざまな領域で課題を抱えている企業や個人に対し、解決策の提案や支援などをおこなう仕事です。
コンサルティングは案件1件あたりの単価が高額で、知識やスキルを提供するビジネスモデルであるため、コストがあまりかからずその分従業員への給与に還元されやすくなっていることから、業界全体で高い年収水準を実現しています。
コンサルタントには高い専門知識やスキルが求められますが、「経営」「戦略」「人事」などの文系分野の知識を扱うものも多いため、文系におすすめの仕事です。
③システムエンジニア
システムエンジニアは、IT(情報技術)に関する専門的なスキルや知識を活かして、ITシステムの設計や開発、運用や保守などをおこなう仕事です。
近年はさまざまな分野でIT化が進んでいるにもかかわらず、それを進める人材が圧倒的に不足しています。そのため、システムエンジニアに対する需要は年々高まっており、スキルを磨いていけば高収入を目指せる仕事です。
システムエンジニアになるには専門的な知識が必要ですが、文系であっても基礎的なレベルであれば1年前後で習得できます。実務においても文系だからという理由で不利になることはなく、コミュニケーション能力や語学力、文章作成能力などを活かして活躍している文系出身者は数多くいます。
文系でもIT系のエンジニアを目指せる理由については、以下の記事でより詳しく解説しています。あわせて参考にしてみてくださいね。
関連記事
文系でITエンジニアはきつい? 厳しい理由と成功する3つのコツ
ITエンジニアは文系出身でも就職することができます。そのためには、まずITエンジニアのにもとめられるスキルや向いている人の特徴を確認する必要があります。この記事では、キャリアアドバイザーがわかりやすく解説しているため、是非参考にしてみてください。
記事を読む

理系におすすめの給料が高い仕事3選
続いて、理系におすすめの給料が高い仕事を3つ紹介します。
理系の専門知識を必要とする企業は数多くあり、理系の学生は文系に比べて給料の高い仕事に就けるチャンスが多くなっています。
これから紹介する仕事は、そのなかでも特におすすめの理系向けの仕事をピックアップしているので、自分の希望と照らし合わせながらチェックしてみてくださいね。
①研究開発職
研究開発職は、研究成果をもとに新製品の開発やすでにある製品の改良に携わる仕事です。
研究開発職は専門的な知識やスキルが求められることから年収水準が高く、医薬品業界や食品業界、化学業界などの安定した業界で働きやすい点が魅力です。自分の専門分野を仕事に活かせるため、理系におすすめの仕事と言えます。
ただし、研究開発職は大学院卒が優遇される傾向があるため、研究開発職を目指すのであれば大学院への進学も検討する必要があります。
②アナリスト
アナリストは、さまざまな分野のデータや情報を調査・分析する仕事です。
近年はデータの分析結果をもとに意思決定をおこなう企業も多く、データ活用への需要は年々高まっていることから、アナリストは高い年収水準をキープしています。分析の対象は証券やシステム、Webなど多岐にわたるため、活躍の場が広い点も魅力です。
データ分析には統計学の知識やプログラミングスキルが必須となるため、理系におすすめの仕事と言えます。
金融アナリストの目指し方については、以下の記事で詳しく解説しています。あわせて参考にしてみてくださいね。
関連記事
金融アナリストとは? 仕事内容・必須スキルや目指し方を徹底解説
金融アナリストとは金融における調査・分析の専門家です。投資や金融商材に関するアドバイスをするため、企業・業界から国の方針、海外の金融事情など幅広くリサーチし分析します。この記事ではキャリアアドバイザーのアドバイスを交えて、具体的な職種の特徴から求められるスキル、活躍する人の特徴を解説しています。目指すうえでは確認必須の情報ばかりなので、しっかりチェックしておきましょう。
記事を読む
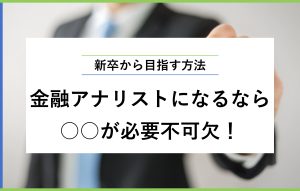
③データサイエンティスト
データサイエンティストは、大量のデータや複雑なデータを解析して、経営に役立つ情報を抽出する仕事です。
データサイエンティストはアナリストと業務内容が似ていますが、AIを用いて高度な分析をおこない、より経営に踏み込んだ情報を導き出します。比較的新しい職種ではありますが、国内外の企業で注目が集まっており、高度な統計学の知識やプログラミングスキルを活かしたい理系の人におすすめです。
ただし、データサイエンティストは成果主義の色合いも強いため、実力によって収入差が生じやすい仕事でもある点は認識しておく必要があります。
キャリアアドバイザーコメント吉川 智也プロフィールをみる
高年収を目指すなら決して無視できないのは「どの業界を選ぶか」という視点です。金融庁の調査「令和4年分 民間給与実態統計調査」によれば、最も年収が高い「電気・ガス・熱供給・水道業」と最も年収が低い「宿泊業・飲食サービス業」では年収に479万円もの差があります。
もちろんこれは業界全体の平均値なので、各企業によって給与形態は大きく異なります。業界の年収平均が低いというだけで高収入を目指すことをあきらめる必要はありませんが、業界平均とかけ離れた年収を得られる会社を探そうとすると、かなり数が減りますし、また競争率が高くなることも考えられます。
自分のやりたいこと、興味のある業界がどれくらいの年収を見込めるのかも業界研究のポイントとして注目しておきましょう。
ちなみに、先の調査において「電気・ガス・熱供給・水道業」の次に年収が高い業界は「金融業・保険業」「情報通信業」です。インフラにかかわるものや成長産業は給与が高くなる傾向があると言えます。
給料が高い仕事を目指すならライバルとの差別化や適職の見極めが不可欠
給料が高い仕事は就活生からの人気も高く、競争が激しくなりがちです。また、給料が高い仕事にはそれ相応の理由があり、実態を知らないまま給料の高さだけで仕事を選ぶことにはリスクが伴います。
そのため、給料が高い仕事を目指すのであれば、ライバルとの差別化や適職の見極めが不可欠となります。就活を進めるにあたっては、この2点をしっかりと意識するようにしましょう。
ここからは、他の候補者と差別化する方法や適職の見極め方について解説していきます。
ライバルに差を付けるには? 給料が高い仕事に就くためにできる3つのこと

給料が高い仕事は競争率も高くなりがちで、内定を得るには他の就活生との差別化が大切です。
そこでここからは、給料が高い仕事に就くためにできることを3つ紹介します。ライバルに差を付けるためにも、自分のできる範囲から取り組んでみましょう。
①難易度の高い資格を取得する
給料が高い仕事に就くためにできることとしては、難易度の高い資格を取得することが挙げられます。
給料が高い仕事は、その仕事に関する専門資格を取得することが大前提となっているケースがあります。たとえば、弁護士や公認会計士などは資格を有していなければ、そもそも弁護士や公認会計士を名乗ることができません。
また、必須の資格でなくても、資格を取得しておくことで自分のスキルを客観的に証明できるため、他の就活生との差別化を図ることができます。難易度の高い資格ほど企業からの評価も高まるため、給料が高い仕事を目指すのであれば積極的にチャレンジしてみましょう。
- IT関連:ITストラテジスト
- 経理関連:日商簿記検定1級
- 不動産関連:宅地建物取引士
資格のアピール方法については、以下の記事で詳しく解説しています。あわせて参考にしてみてくださいね。
関連記事
自己PR「資格取得」でアピールする方法|就活のプロが本音で解説!
自己PRで資格取得について触れるなら、資格そのものよりも、取得に至るまでの「過程」が強力なアピールポイントになりますよ。この記事ではキャリアアドバイザーが資格取得をベースした自己PRの伝え方を例文付きで解説しています。
記事を読む


キャリアアドバイザーコメント堀内 康太郎プロフィールをみる
給料が高い仕事に就くために難易度の高い資格を取得することは有効な手段の一つです。しかし、資格があれば必ずしも希望する仕事に就職できるとは限りません。大切なのは、コミュニケーション能力や、判断力、発想力、適応力といった人間的な力、いわゆる「ソフトスキル」の部分です。
たとえば、最も難易度の高い資格の一つ「公認会計士」を持っていたとしても、面接で志望動機をきちんと伝えられるコミュニケーション能力がなければ、内定を獲得するのは難しいでしょう。
多くの企業で新入社員に求めることとして常に上位に上がってくるのが「コミュニケーション能力」や「主体性」「積極性」「協調性」などです。資格は能力の一部を表すものとして大切ではありますが、企業が注目しているソフトスキルの部分を伸ばすことも給料の高い仕事に就くためには重要な要素なのです。
②専門知識を習得する
給料が高い仕事に就くためにできることとしては、専門知識を習得することも挙げられます。
資格と同様、給料が高い仕事は、その仕事に関する専門知識を習得しておくことが大前提となっているケースは少なくありません。たとえば、ITエンジニアやデータサイエンティストなどは、仕事をするうえで専門知識が必須となります。
企業によっては知識なしの状態から育成をおこなっている場合もありますが、書籍やスクールを活用して専門知識を身に付けておけば、採用選考においても有利に働き、給料が高い仕事に就けるチャンスが広がります。
③語学力を高める
給料が高い仕事に就くためには、語学力を高めるのも効果的です。
昨今はグローバル化が加速しており、語学力の需要は年々高まっています。語学力を高めておけば活躍の場が世界に広がるため、同じ仕事でも高収入を狙えるチャンスが広がります。
なお、就活でアピールできる英語力の目安は、TOEICの場合は600点以上、英検の場合は2級以上と言われています。他の就活生との差別化を図りたいのであれば、それ以上のレベルを目標にしてみましょう。

キャリアアドバイザー
もちろん語学力は英語に限りません。英語に加えて他の言語も扱えるようになれば、企業からの需要はさらに高まりますよ。
「給料が高い」以外の条件も大切! 仕事を選ぶうえで重要な5つの要素

仕事を選ぶ際は、給料の高さ以外の要素にも着目して慎重に検討する必要があります。
ここからは、仕事を選ぶうえで重要な要素を5つ紹介するので、自分にとって重要な要素は何かを考えながら、一つずつチェックしてみてくださいね。
①やりがいを感じられるか
仕事は人生において多くの時間を費やすことになるため、仕事に対してやりがいを感じられるかどうかは非常に重要な要素です。
やりがいを感じられない仕事ではモチベーションの維持が難しく、だんだんと仕事の質も下がり、長期的なキャリア形成にも悪影響を及ぼす可能性があります。
給料の高さをモチベーションにつなげることもできますが、仕事そのものにもやりがいを感じられれば、より前向きかつ長期的に働き続けることができます。

キャリアアドバイザー
高い給料を手にするにはある程度の時間を要することから、高収入の仕事に就くうえで、長く働けるかどうかという点は非常に重要ですよ。
やりがいのある仕事の見極め方については、以下の記事でより詳しく解説しています。あわせて参考にしてみてくださいね。
関連記事
仕事例24選|やりがいのある仕事とは? 適職の見つけ方を徹底解説
やりがいのある仕事に就くためには自分が仕事に求めることを突き詰めて考えることが大事です。この記事ではやりがいのある仕事の特徴を解説したうえで、具体的な職業を20選紹介します。自分ならではのやりがいの見つけ方も解説するので参考にしてください。
記事を読む
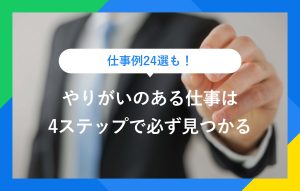
②社風が自分の価値観と合っているか
仕事を選ぶうえでは、価値観も重要な要素の一つです。
社風とは、企業が持つ独自の雰囲気やスタイルのことです。各企業にはそれぞれの社風があるため、事業内容が同じでも職場の雰囲気が全然違うということは珍しくありません。
自分の価値観に合わない社風では、仕事を進めるうえでギャップを感じる場面も多く、働きづらさや居心地の悪さを感じることが多くなります。自分らしく働くためには、社風が合うかどうかも確認しておく必要があります。
社風の調べ方については、以下を参考にしてみてくださいね。
- 公式のホームページやパンフレットに目を通す
- OB・OG訪問をして実際に働いている人の意見を聞く
- 面接で直接質問する
社風を意識した企業選びについては、以下の記事でより詳しく解説しています。あわせて参考にしてみてくださいね。
関連記事
社風を科学しよう! 自分に合った企業が見つかる分析方法を徹底解説
入社後に後悔しないためにも、社風の理解はとても大切です。今回の記事ではキャリアアドバイザーが、なぜ社風を理解することが大切かを解説した上で、社風を把握するための切り口や方法を紹介していきます。業界ごとの社風の傾向も紹介しているので、自分に合った企業探しの参考にしてみてください。
記事を読む

③無理なく働き続けられる環境か
仕事を選ぶ際は、無理なく働き続けられる環境かどうかも確認しておきましょう。
いくら給料が高くても労働環境が悪くては、将来的に心身の健康を損なう可能性が高くなり、長く働き続けるのが難しくなります。
- 一人あたりの業務量が多く、長時間労働を強いられる
- ノルマや目標が厳しく、残業や休日出勤が常態化している
- パワハラやセクハラなどのハラスメントが横行している
仕事そのもののプレッシャーによって感じるストレスと、労働環境の悪さによって感じるストレスはまた別ものです。安定して高いパフォーマンスを発揮するためには、なるべく働きやすい環境が整っている企業を選ぶことが大切です。

キャリアアドバイザー
労働環境の良し悪しを判断する際は、その企業の離職率や実際に働いている人の意見を参考にしてみましょう。
④自分が成長できるか
仕事を選ぶうえでは、自分が成長できるかという点に着目するのも一つの手です。
成長の機会が多い職場であれば、自身のスキルや知識を磨ける機会も多くなり、将来的なキャリアの選択肢が広がることにつながります。
- 研修制度やキャリアアップ制度が充実している
- 意欲があれば年齢に関係なく新たな業務やプロジェクトに参加できる
- 仕事の裁量権が大きい
特に「将来的に独立や起業をしたい」といった目標がある場合には、自身が成長できるかどうかを軸にして仕事を選ぶことをおすすめします。
⑤自分の長所やスキルを活かせるか
自分の長所やスキルを活かせるかどうかも、 仕事を選ぶうえで重要な要素の一つです。
自分の長所やスキルを活かせる仕事の方が、そうでない仕事よりも入社後に活躍できる可能性が高くなります。また、自分の長所やスキルを活かせた方がやりがいを感じやすく、仕事に対するモチベーションも維持しやすいでしょう。
早期から活躍したり高いモチベーションを発揮したりすることで、自然と周囲からの評価も高まり、結果的に仕事に対する満足度も高まっていきます。
得意なことやスキルがある場合には、それを活かせるかどうかを軸にするのも一つの選択肢です。
自分に合った給料が高い仕事を見極めるための3つの準備

給料が高い仕事にはそれ相応の理由があるため、自分に合った仕事を慎重に見極める必要があります。とはいえ、具体的にどうやって見極めていけば良いのかわからず、迷ってしまうこともあるかもしれません。
そこでここからは、自分に合った給料が高い仕事を見極めるための3つの準備について解説します。これらの方法を試しつつ、自分に合った仕事を見極めていきましょう。
①自己分析:「何をしたいのか」と「何ができるのか」の2軸から考える
自分に合った仕事を見極めるためには、自己分析をおこなって自分のことを深く理解することが欠かせません。
自己分析のやり方はいろいろありますが、適職を見極めるには、「何をしたいのか(Will)」と「何ができるのか(Can)」の2軸から考える方法が効果的です。
Willの側面から考えることで「やりがいのある仕事」、Canの側面から考えることで「適性のある仕事」を絞り込むことができます。どちらを重視するかは各人の自由ですが、WillとCanの2つが重なっていれば重なっているほど、モチベーションの維持や成果につながりやすく、より自分に合った仕事である可能性が高くなります。

自己分析の質を上げる方法については、以下の記事で詳しく解説しています。あわせて参考にしてみてくださいね。
関連記事
平均給料が高い仕事20選|給料以外の条件の着眼が適職発見のカギ
給料の高い仕事は、誰にでも簡単に就けるわけではありません。給料以外でその企業を志望する理由の準備は必須です。この記事では、給料の高い20の仕事と給料の高い仕事に就きたい場合に意識すべきことを解説します。
記事を読む

②OB・OG訪問:高年収の仕事だからこその魅力や大変な部分を聞く
自分に合った仕事を見極めるための準備としては、OB・OG訪問も効果的です。
適職を見極めるうえで、実際に働いている人の意見は非常に参考になります。高年収の仕事だからこその魅力や大変な部分を聞くことで、より具体的なイメージがつかめるようになります。
いきなり社会人に話を聞くことに抵抗がある場合でも、OBやOGであれば同じ大学ということもあり、質問もしやすいはずです。OB・OG訪問の相手を探す方法については、以下を参考にしてみてくださいね。
- 大学のキャリアセンターに相談する
- ゼミの教授やサークルの先輩に紹介してもらう
- OB・OG訪問専門のサービスを活用する
OB・OG訪問のポイントについては、以下の記事でより詳しく解説しています。あわせて参考にしてみてくださいね。
関連記事
OB・OG訪問攻略ガイド|企業理解や選考に役立てるコツを解説
OB・OG訪問をして周囲と差をつけよう こんにちは。キャリアアドバイザーの北原です。 「OB・OG訪問って必要なんですか?」「OB・OGってどうやって見つければいいんですか?」 就活生から、こんな声を聞くことがあります。 […]
記事を読む

③インターンシップ:自分がその環境になじめるか判断する
自分に合った仕事を見極めるには、インターンシップに参加するのもおすすめです。
インターンでは仕事を体験したり、その企業で実際に働く人たちと接したりすることで、現場の空気を肌で感じることができるため、自分がその環境になじめるか判断するための絶好の機会となります。
仮にインターンを通じて「想像していたものと違う」「自分には合わない」と感じた場合であっても、それはそれで事前にミスマッチを防止できたことになり、次に活かすことができます。
「百聞は一見にしかず」とも言われている通り、その仕事が自分に合っているかどうかを判断するには、自分自身で実際に体験してみるのがいちばんです。気になる仕事があれば、積極的にインターンに参加してみましょう。

キャリアアドバイザーコメント成瀬 遼プロフィールをみる
OB・OG訪問やインターンシップの良いところは、文字情報だけでは伝えきれないことがわかるということです。たとえばOB・OG訪問で先輩社員から普段の仕事の様子を聞ければ、実際に自分が入社した後の様子が具体的にイメージできます。インターンシップで社員同士がやり取りしている様子を見て、職場の雰囲気を感じることもできるでしょう。
また、OG・OG訪問やインターンに参加すると自分が調べたこと以外の情報を見聞きでき、視野が広がるというメリットもあります。たとえば営業職に興味を持っていた人が、社内の部署や仕事内容を詳しく知り「人とかかわるなら広報・マーケティングもありだな」という気づきを得て、その後の就活に活かすということもよくあります。
OG・OB訪問やインターンは実際に足を運び、時間を投資するという大変さはありますが、その分得られるものもたくさんあるので、ぜひ活用しましょう。
給料が高い仕事の特徴や実態を理解して自分に合った仕事を見つけ出そう
給料が高い仕事にはそれ相応の理由があるため、その仕事の特徴や実態をしっかりと理解したうえで、自分に合った仕事を慎重に見極めることが必要です。
給料が高い仕事は世の中に数多く存在するものの、その仕事に就くための道のりは決して容易ではありません。本記事で解説した内容を参考にしながら、できることから準備を進めていきましょう。

 キャリアパーク就職エージェントは、東京証券取引所グロース市場に上場しているポート株式会社(証券コード:7047)が運営しているサービスです。
キャリアパーク就職エージェントは、東京証券取引所グロース市場に上場しているポート株式会社(証券コード:7047)が運営しているサービスです。












給料の高い仕事に就きたいと考えているのですが、どれくらいの金額であれば給料が高いと言えるのでしょうか?