目次
- 既卒=人生終了ではない! 対策次第で理想の企業への就職がかなえられる
- そもそも「既卒」とは?
- 新卒・中途との違い
- 第二新卒との違い
- リアルな就職実態を把握しよう! 「既卒=人生終了」といわれてしまう理由
- 新卒と比べてエントリーできる企業が限られている
- 空白期間が長くなるほど企業から不安を抱かれやすい
- スキルがない場合は市場価値が上がりにくい
- 悲観する必要は一切ナシ! 「既卒=人生終了」ではない3つの理由
- ①卒業後3年以内は新卒として企業にエントリーできる
- ②既卒を採用する企業は増加傾向にある
- ③人手不足により求人者優位の市場になっている
- 「既卒=人生終了」を払拭! 就職成功への7つの対策
- ①なるべく早い段階で就活をスタートする
- ②既卒という選択肢を選んだ理由を整理する
- ③就職の軸をもとにした志望動機を作成する
- ④長期的なキャリアビジョンを組み立てる
- ⑤最初から選択肢を絞らず幅広く求人をチェックする
- ⑥志望企業の業務で活かせるスキルを身に付ける
- ⑦既卒に特化したエージェントに相談する
- なかなか動き出せないときは「就活の軸」を立ててみよう!
- 既卒ならではの落とし穴に要注意! よくある失敗パターンを回避しよう
- パターン①具体的な就活スケジュールを立てずに行動する
- パターン②既卒である状態に焦って内定が早く出た企業に就職を決める
- パターン③誰にも相談せずに1人で就活を進める
- 正社員採用を狙った就活以外の選択肢も視野に入れておこう!
- 既卒=人生終了と言わせない! 就活の軸を決めて理想の企業に就職しよう
既卒=人生終了ではない! 対策次第で理想の企業への就職がかなえられる
こんにちは、キャリアアドバイザーの阿部です。
既卒という状況についてネガティブな情報を目にしてしまった人から、こういった相談を受けることがあります。

結論から言えば、既卒は人生終了と言われるような状況ではまったくありません。
確かに就活を進めていると壁と感じるような場面にでくわすかもしれませんが、対策次第で自分の理想の企業への就職をかなえられますよ。そのためには、既卒ならではの就活のポイントを押さえて、対策を念入りにおこなうことが大切です。
この記事では、既卒就活の成功へ向けた8つの特化対策を解説します。また、既卒が人生終了と言われてしまう要因も紹介するので、リスクも把握したうえで、理想の企業の内定を獲得するための対策を一緒に進めていきましょう。
【完全無料】
転職活動者におすすめ!
転職活動で使いたい診断ランキング
1位:適職診断
まずはあなたが受けない方がいい職業を確認してください
2位:業界&職種マッチ度診断
興味のある業界・職種とあなたの相性を診断しましょう
3位:自己分析ツール
あなたの基本的な性格から、転職活動で使える強み・弱みを診断します
4位:就活力診断
80点以上が合格!まずは力試しに自分の就活力を測定しよう
5位:マナー力診断
あなたのマナーは大丈夫?診断を受けて自分の苦手分野を把握しよう
【併せて活用したい!】
選考前に必ず使ってほしい厳選ツール
①自己PR作成ツール
自己PRがまとまらない人は、ツールを活用して自己PRを完成させよう
②志望動機作成ツール
5つの質問に答えるだけで、受かる志望動機を自動で作成します
そもそも「既卒」とは?
そもそも既卒とはどのような状態を指すのでしょうか。「中途」「第二新卒」など似たような意味を持つ言葉もあるので、正直よく意味がわかっていないということもあるかもしれませんね。
既卒ならではの特化対策を進めるためにも、まず既卒とはどんな状態のことを指すのか正しい意味を把握しておきましょう。
既卒についての解説はこちらの記事も参考になりますよ。
関連記事
既卒とは? 新卒との違いから既卒者が就活で成功するコツを徹底解説
キャリアアドバイザーが、既卒の定義から、既卒ならではの就活のポイントを詳しく解説します。既卒の就活に欠かせない事前準備もリストでまとめているので、記事を参考にしながら就活の準備を進めていきましょう。
記事を読む

新卒・中途との違い
採用の応募条件として多く掲載されているので、「新卒」「中途」の言葉を聞いたことのある人は多いと思います。「既卒」と「新卒」「中途」との意味の違いを一緒に確認していきましょう。
- 既卒:明確な基準はないが、学校を卒業後就職しておらず、一度も正社員として働いた経験がない人を指す。一般的には卒業後3年以内を既卒として扱う場合が多い
- 新卒:一般的には「今年度中に学校を卒業する見込みで、卒業後就職予定の学生」を指す。在学生だけでなく、入社後の職場内でも「今年度中に学校を卒業し新しく入社した人」を新卒と呼ぶこともある
- 中途採用:就業経験のある人材を採用すること。中途採用では前職での経験やスキルを生かせる人材といった即戦力となる人材が採用されやすい
既卒は、卒業してから正社員経験のない人のことを指します。たとえば、卒業後に就活を継続している人やフリーターなど正社員としての就業経験がない人は「既卒」として就活をすることになります。
中途採用についてはこちらの記事の解説がわかりやすいですよ。
関連記事
中途採用とは? 確認必須の10の基本|攻略の糸口は目的理解にあり
中途採用の就活を成功させるには、企業が中途採用者にもとめることを理解するのが大切です。この記事では、キャリアアドバイザーのアドバイスを交え、中途採用の基本情報からよくある疑問、選考突破のステップまで徹底解説。自分が望む企業へ入社を叶えるためにも、ぜひ参考にしてみてくださいね。
記事を読む

第二新卒との違い

キャリアアドバイザー
- 第二新卒:明確な期間などの決まりはないものの、一般的には「学校を卒業後、企業に入社してから1〜3年で退職をしたり、転職を考えている人」を指す
既存と第二新卒の大きな違いは、「就業経験」の有無です。就業期間がいずれであろうと1度でも正社員として働いていた経験があれば第二新卒となります。第二新卒の人は、「3カ月しか働いてないから就業経験がないのと同様=既卒だ」ととらえてしまわないよう注意してくださいね。
第二新卒では正社員としての社会経験があるので、ある程度のビジネスマナーやビジネススキルが求められることもあります。既卒は正社員としての社会経験はないので、ポテンシャルを重視されることが多いです。
まずはあなたが受けないほうがいい職業を確認しましょう
自分に合った職業・合わない職業を見つけることは、就活の成功に不可欠です。しかし、見つけることが難しいと感じる人も多いでしょう。
そんな時は「適職診断」を活用して、志望する職業と自分の相性をチェックしてみましょう。簡単な質問に答えるだけで、あなたの強みや性格が分析され、向いている職業・向いていない職業が診断できます。
自分の適職・適さない職業を今すぐチェックしてみてください。
また、業界も含めてより向いている職業を知りたい場合は「業界&職種マッチ度診断」がおすすめです。
リアルな就職実態を把握しよう! 「既卒=人生終了」といわれてしまう理由

そもそもなぜ「既卒=人生終了」とまで言われてしまうことがあるのでしょうか?
それは、前提として既卒は就職において厳しい現状があることも影響しています。経歴面を企業に不安に思われたり、新卒や経歴のあるベテランの求職者と比較されて書類選考で落とされてしまうといったことが、事実としてあるのです。
ただ、そういった事実があることをしっかりと理解して対策をしていけば、理想の企業に就職することはできます。決して悲観的になる必要はありませんよ。

キャリアアドバイザー
対策の軸を立てるためにも、ここからは既卒の就職実態についてチェックしていきましょう。
新卒と比べてエントリーできる企業が限られている
既卒の就職実態としては、新卒と比較したときにエントリーできる企業が限られてしまうことがまず挙げられます。
ほとんどの企業では「新卒」「中途の」2つの採用枠を設けており、「既卒採用枠」を設けている企業は少ないです。
既卒は多くの場合、卒業後3年以内は新卒枠、もしくはスキル・職務経験が必要ない中途採用枠で応募し、卒業後3年以上が経過している場合は、中途採用枠で応募することになります。
企業によっては新卒枠での既卒の受け入れをしていないこともあり、中途採用枠は専門スキルや一定の職務経験を求められる場合が多いので、既卒は新卒と比べてエントリーできる企業の数が減ってしまうのです。

キャリアアドバイザー
既卒は中途と比較するとスキルや経験面で差をつけられてしまうケースが多いです。資格やスキルなどを身に付けるとアピール材料を増やすことができますよ。
この記事では、既卒2年目の就活のコツを紹介しているので参考にしてください。
関連記事
既卒2年目は企業の懸念払拭がカギ! 回答例文付きで徹底攻略しよう
既卒2年目で就活をするうえで押さえておきたい基礎知識や、頻出質問に対する回答例などを、キャリアアドバイザーの解説を踏まえながらわかりやすく解説します。求人の探し方から独自の就活対策法もチェックできる、既卒2年目の人は必見の内容です。
記事を読む

空白期間が長くなるほど企業から不安を抱かれやすい
既卒が就職において不利になりやすい点として、働いていない空白期間が長くなることで企業から「働く意欲が低いのではないか」「就職がうまくいかない原因があるのではないか」などの不安持たれやすくなる、ということも考えられます。
そういった事情があるからこそ、なるべく早い段階で就活をスタートすることがおすすめです。
また、資格取得や就職以外で熱心に励んだことなど、空白期間どんなことをしていたのかを説明できるように準備しておくと空白期間の過ごし方に納得感が生まれ、企業の不安を払拭しやすくなりますよ。

キャリアアドバイザー
資格取得をしてから就活をスタートしようと考える人もいるかもしれませんが、勉強と同時並行で就活を進めることをおすすめします。〇〇の資格取得に励んでいると就活のなかで伝えることでアピール材料になりますよ。
キャリアアドバイザーは実際にこうアドバイスしています!経歴への不安要素はこうしてカバー!
既卒期間の過ごし方次第では空白期間がアピール材料になることもある
目的があっての空白期間である場合は、逆に面接時に有利に働くこともあります。たとえば、学生起業を考えていて卒業後もその会社の起業や経営をおこなっていたが、事情により就職を再検討したなど、就職とは別の目標ではありつつも、熱心に励んでいたなどのポジティブな理由は好印象につながります。
そのほかにも、経済的な事情や家族の介護など、人それぞれさまざまな事情があることも企業も把握しています。空白期間の背景を把握することで企業も不安がなくなり採用に踏み切れることもあるので、既卒として過ごしていた期間の説明を明確にできるように準備をしておいてくださいね。
焦る気持ちはあるものの、どうしても働きたくなくて動き出せない……。そんな人はこちらの記事をチェックしてみてください。
関連記事
「働きたくないから死ぬしかない」は間違い! 6つの選択肢を解説
働きたくない、けれど働かないと生きていけないから、死ぬしかない。そう考えてしまっている人は、取れる選択肢を知って、その思考から抜け出すことを最優先にしましょう。この記事では、働かずに生きる方法など、さまざまな対処法をキャリアアドバイザーが解説します。
記事を読む

スキルがない場合は市場価値が上がりにくい
既卒は就業経験がないこと、またそれゆえに業務に必要なスキルが身に付きにくいので、転職市場における自身の市場価値を上げることが難しい傾向にあります。
企業もどんなに自社への志望度が高くても、入社後に業務を通して活躍するイメージができないとなかなか採用に踏み出せないものです。
少しでも活躍イメージにつなげるためには、志望企業や業界に関連するスキルや資格を持っておくと効果的です。

キャリアアドバイザー
スキルや経験がない場合、どうしても市場価値が上がりにくくなってしまいます。工夫次第では市場価値を上げることもできるので、自分に合ったやり方で選考対策をしていきましょう。
悲観する必要は一切ナシ! 「既卒=人生終了」ではない3つの理由

就活に対して既卒者は不利な実態があるために「既卒=人生終了」と言われていますが、現状を悲観する必要はありません。
そもそも就職できなくとも人生が終了するわけでもありません。ただ不安を煽るだけの噂であることはまず理解しましょう。
とはいえ、人生終了とまでいわれてしまうと将来が不安になってしまいますよね。ここからは、既卒就活において必要以上に不安になる必要がない理由を説明していきます。
もし今あなたが就職なんてできないと落ち込んでいるなら、まずこの記事を読んでみましょう。
関連記事
「就職できない」は打開できる! 7つの就活フェーズごとの対処法
対策をしているのに、一向に就職できない……そんな状況で就活を続けるのは苦しいですよね。この記事では、専門家のアドバイスを交えて「就職できない」を打開する方法を解説しています。一緒に希望のキャリア実現に向けて一歩を踏み出しましょう。
記事を読む

①卒業後3年以内は新卒として企業にエントリーできる
まず押さえておきたいのは、多くの場合既卒であっても卒業後3年以内は新卒枠として企業にエントリーできるということ。
以前までは新卒枠へのエントリーができませんでしたが、2010年におこなわれた「青少年雇用機会確保指針」の改正により、「3年以内の既卒者についても、新卒枠で応募受付をするように」と厚生労働省から各企業に周知があったことが関係しています。
ただすべての企業に義務化されているわけではないので、新卒枠としてエントリーが可能であるかは企業の方針によります。企業の募集要項をしっかりチェックしてくださいね。
キャリアアドバイザーから就活に悩むあなたへ既卒だからこその企業の探し方がある!
企業探しをする際には複数の手段を活用して自分に合った企業を見つけよう
大手企業では、新卒・中途以外にも「既卒」「第二新卒」といった採用枠を多く設けている企業が多いです。なので、就職先を探す際には大手の就活サイトを活用するのもおすすめです。
ほかにも、卒業した大学や専門学校のキャリアセンターを頼ってみるのも一つの効果的な手段です。卒業生であることがわかれば、就職先を紹介してくれる場合もありますよ。卒業した学校を訪問する際には、卒業生であることが証明できるように「卒業証明書」などを持参してくださいね。
また、厚生労働省に委託された全国の若者支援の実績や就活ノウハウをもつ民間団体が運営する地域若者サポートステーションなどを利用することで、既卒向けの求人情報や、就職に役立つ情報を得られる可能性もあります。さまざまな手段を組み合わせて、自分に合った企業を見つけてくださいね。
②既卒を採用する企業は増加傾向にある
既卒を採用する企業は増えつつあります。なぜなら、既卒は正社員としての就業経験がないからこそ、どこの企業の文化や仕事のやり方にも染まっていないという大きな魅力があるからです。
新しい文化や業務を柔軟に吸収できる人が多いことから「育成しやすい」「会社になじみやすい」といった理由で、積極的に採用している企業が多くあります。

キャリアアドバイザー
既卒だからネガティブなイメージを持たれるのではないかと考える人は多いですが、既卒ならではの魅力を把握して企業へのアピールにつなげていきましょう!
③人手不足により求人者優位の市場になっている
近年、採用市場は全体的に求職者優位の売り手市場が続いています。厚生労働省の一般職業紹介状況(令和5年4月分)についてによると、発表している令和5年4月の有効求人倍率は1.32倍となっています。
そのため、既卒就活においても、就職先の選択肢が多いというメリットがあります。加えて既卒は入社時期の融通が利きやすいという独自の強みがあるので、特に人手不足の業界からは注目を集めています。

キャリアアドバイザー
人手不足に悩む企業には、専門的なスキルや経験などではなく人柄や成長意欲を重視した採用をおこなう傾向があります。そのため、特に経歴のない既卒もチャレンジしやすい特徴があるのです。
「既卒=人生終了」を払拭! 就職成功への7つの対策

既卒就活を成功させるためには、新卒就活とはまた違った対策や準備が必要です。
理想の企業の内定を獲得するためにも、ここから解説する8つの既卒就活ならではの対策を押さえて、素早く行動を起こしていきましょう。
①なるべく早い段階で就活をスタートする
前述の通り、就職していない空白期間が長くなるにつれて企業に不安感を持たれやすくなるなどのリスクがあります。前提の話になりますが、既卒として就活を始めるベストタイミングは常に「今」です。
リスクを最小限に抑えるためにも、なるべく早めに就活をスタートしましょう。
就活以外に優先すべき物事があるなどすぐに動き出せない事情がある人は、無理のない範囲で少しずつ就活を進めてくださいね。
たとえば、「求人サイトをチェックする習慣をつける」「興味のある業界の主要企業を調べてみる」など今できることから始めましょう。
- 仕事に求める条件と絶対に避けたい条件をリストアップする
- 興味のある仕事にどんなスキルが求められるか調べる
- 面接で聞かれやすい質問への回答を準備しておく
- 就活で必要なアイテムを揃えておく
- 入室・退出など面接時のマナーを押さえておく

キャリアアドバイザー
小さな積み重ねが自分の理想の企業へ就職する大きな一歩になります。勇気のいることかもしれませんが、「まず行動に起こしてみる」ことが大切です。
②既卒という選択肢を選んだ理由を整理する
「選択肢の多い新卒での就職ではなく、どうして既卒という道を選択したのだろう」という疑問を持つ企業は多く、面接で理由を聞かれることがよくあります。
既卒を選んだ理由が、「新卒で就職できなかった」「働く意欲が起きず、就活をしなかった」といったネガティブにもとらえられる理由の場合もあるでしょう。そんな場合は、既卒になった理由を明確にしておくことが大切ですよ。
「なんとなく既卒になってしまった」という状態では、自分のことを振り返るのが苦手という印象につながる可能性があります。
自分の現状をしっかり把握し、就活時の課題を改善しようとする姿勢を伝えることで「課題に前向きに取り組むことができる」という印象につながります。
- なぜ①:なぜ既卒という選択肢を選んだのか→就活へのやる気が起きなかったから
- なぜ②:それはなぜ?→やりたい仕事が見つからなかったから
- なぜ③:それはなぜ?→働く意味が見いだせなかったから
- なぜ④:それはなぜ?→働くことで趣味に使える時間が減ってしまうから
- なぜ⑤:それはなぜ→プライベートを大切にしたいという価値があるから

キャリアアドバイザー
既卒の道を選んだ理由を整理するには「なぜなぜ分析」が効果的です。「なぜ既卒という選択肢を選んだのか」という問いになぜを数回繰り返して思考を深掘りしていくことで、原因がつかめるようになりますよ。
合わせて既卒ならではの面接対策も進めておきましょう。こちらの記事では既卒者がすべき面接対策がまとまっています。
関連記事
既卒の面接はマイナスイメージの払拭が最重要|3つの必須対策を解説
既卒の面接を突破するためには、企業が既卒に抱くマイナスイメージを払拭することが最重要です。この記事では既卒が抱かれやすい印象から、ネガティブな要素もプラスに印象付ける方法を、専門家監修のもと詳しく解説しています。
記事を読む

③就職の軸をもとにした志望動機を作成する
志望動機は採用の決定において、企業が重視している項目の一つです。就活の軸をもとにして志望動機を組み立てることで説得力の高い志望動機に仕上げることができますよ。
就活の軸とは仕事で最も大切にしている価値観であり、就活の軸を指針として企業探しをすることで自分に合った企業に出会うことができます。つまり、就活の軸は企業を志望する理由を裏付ける根拠になるのです。
企業を志望する根拠が明確であれば、納得感のある志望動機になります。自分の軸と企業での仕事や働き方がマッチしていることを表現できれば、企業も入社後のミスマッチなどを心配することなく採用に踏み切れます。
- ステップ①:企業を志望する理由を伝える
- ステップ②:企業選びの指針としている就活の軸について説明する
- ステップ③:就活の軸と企業がマッチしているポイントを伝える
- ステップ④:入社後の展望をアピールする

キャリアアドバイザー
特に既卒は就業経験がないことから仕事に対して求める条件や価値観が明確でない人も多く、ミスマッチが起きやすい傾向があります。そこで、就活の軸を根拠として企業の志望理由を伝えることで、企業とのマッチ度の高さがアピールできるのです。
未経験の状態で志望動機を書く場合はコツがあります。この記事ではそのコツを例文付きで解説しているので、一度目を通しておきましょう。
関連記事
例文9選|未経験の志望動機はポテンシャルを前面に出して選考突破!
未経験就職の志望動機は、入社後どう成長していくのかを示すことが大切です。ポテンシャル面が評価されることに合わせた独自の対策を進めましょう。この記事ではキャリアアドバイザーが、未経験就職の志望動機の作り方から、効果的な伝え方を解説します。
記事を読む

④長期的なキャリアビジョンを組み立てる
既卒での就活は、長期的なキャリアビジョンを組み立てることもポイントです。
あなたのキャリアビジョンをかなえる環境が自社にあれば、目標を達成するために自社でスキルや経験を身に付けて大きく成長してくれるだろうと企業は期待します。その期待が採用の決め手になるかもしれません。
3、5年先に「どんな社会人になっていたいか」「どんな経験やスキルを身に付けておきたいか」などをイメージすると、キャリアを考えるヒントになりますよ。
- 大きな予算を1人で担当する責任のある仕事がしたい
- 多くのメンバーをまとめるリーダーとして活躍したい
- 個人の可能性を最大限に引き出せるようなマネジメントがしたい
- 上流から下流まで一気通貫して担当できるエンジニアになりたい

キャリアアドバイザー
ビジョンが明確なことは、「この先も意欲的に働いてくれそうだ」と早期退職を防げるという企業側の安心感にもつながります。
⑤最初から選択肢を絞らず幅広く求人をチェックする
志望企業・志望業界が定まっていない人は、幅広く求人をチェックしてみてくださいね。最初から選択肢を絞り過ぎてしまうと、自分に合った企業を見逃してしまう可能性があります。
また、人材不足の業界・企業はすぐに入社して企業に貢献してくれるような人を求める傾向があります。
どうしても自分に合った業界が見つからないという人は、人材不足の業界をチェックしてみるのもおすすめです。
- IT業界
- サービス業界
- 運送業界
- 福祉業界
- 建設業界
- スタートアップの企業
- 急成長中の企業

キャリアアドバイザー
人材不足の企業は、1人にかかる仕事の負担が大きかったり、多忙であるがゆえに休みが取りにくかったりする傾向もあります。仕事内容や働き方をしっかりチェックしたうえで入社を決めてくださいね。
⑥志望企業の業務で活かせるスキルを身に付ける
志望する業界に関連性の高い資格を取得したり、業務に活かせるスキルを身に付けておくこともおすすめです。
特に、専門的な知識やスキルを必要とする業界や職種を目指すなら、その企業で働くうえで必要な資格やスキルを身に付けておくことで選考を突破しやすくなります。
また、働く意欲が高いことや継続力があることのアピールにもつながりますよ。資格やスキルは一朝一夕で身に付くものではありません。
将来の仕事を見すえて資格やスキルの勉強をしていたと説明できれば、仕事でも同じように意欲的に取り組んでくれるだろうというイメージにつながります。

キャリアアドバイザー
さらに、資格を取得しようと思った理由や身に付けたスキルを仕事でどのように活かしたいのかまで伝えられると、説得力が高まります。あなたらしさが伝わるチャンスにもなりますよ。
⑦既卒に特化したエージェントに相談する
既卒の人は1人で就活を進めずに、既卒に特化した就職エージェントに相談しながら就活を進めることをおすすめします。
就職エージェントとは自分に合った企業の紹介から、面接や書類作成など就職のサポートを受けることができるサービスのことです。経験豊富な就職の専門家といえるアドバイザーが内定までのサポートをしてくれるので、安心して就活を進められます。
エージェントとのやり取りは、対面やオンライン通話などさまざまな方法で対応していることが多いので、住んでいる場所にかかわらずサポートを受けることができますよ。

キャリアアドバイザー
「既卒の就活のやり方がわからない」「1人で就活するのが不安だ」という人はエージェントを活用してみてくださいね。
- 履歴書・職務経歴書の添削をおこなってくれる
- 自分に合った企業を紹介してくれる
- 就活で悩んだときにすぐに相談できる
既卒就活を成功させる方法の一つとして、ハローワークへの相談もおすすめです。この記事では、ハローワークを活用した就活の方法を紹介しているのであわせて参考にしてくださいね。
関連記事
ハローワークとは? 使い方や就活に役立つ8つのサービスを徹底解説
仕事探しにハローワークを使ってみたいけど、利用のハードルが高く感じてしまう人もいますよね。この記事では、そんなあなたのためにハローワークでできることや上手な使い方、初めてハローワークに行くときに必要なものを専門家のアドバイスを交えて解説。私たちと一緒にハローワークについて学んでみましょう。
記事を読む

なかなか動き出せないときは「就活の軸」を立ててみよう!
既卒は人生終了、と悲観する必要はまったくないものの、ネガティブな情報に触れてモチベーションが下がってしまうこともあるかもしれません。
そんなときは、まず「就活の軸」を立ててみましょう。目指すべきゴールを描くことで最初の一歩を踏み出しやすくなりますよ。
- 周囲の人が気持ちよく働ける環境づくりがしたい
- 人生の転機に携わる仕事がしたい
- 若いうちから裁量がある環境で働きたい
- 興味のある分野を追求したい
就業経験がないとどんな仕事が自分に合っているのかなかなかイメージできないですよね。そこで、まず仕事をするにあたって大切にしたい価値観を明確にすることが、自分に合った仕事を見つける手がかりになりますよ。

キャリアアドバイザー
就活の軸をもとに就職先を決めることで、入社後のミスマッチ防止にもつながります!
キャリアアドバイザーは実際にこうアドバイスしています!就活の軸を立てることのメリット
就活の軸を定めることで就職先とのミスマッチを防止できる!
何の軸もない状態では自分にどんな環境がマッチしているのかわかりませんが、たとえば「自分はチャレンジングな環境に身を置きたい」という軸があれば、若手でも大きな案件を任せてくれる環境や、年功序列な社風ではない環境など、目指すべき方向も見えてきます。就職の軸をもとに就職先を決定することは、入社後のミスマッチ防止につながるのです。
軸がブレた状態で就職活動をおこなうと、入社後に仕事の適性にミスマッチを感じたり、職場環境が結局が自分に適しておらず、早期退職をしてしまうなどの可能性も出てきます。
早期退職となれば、経済的な負担や再度就活をすることなどへの精神的な負担もかかってしまうかもしれません。このような事態を防ぐためにも、自分の就活の軸をしっかりと定めることが重要ですよ。
こちらの記事は転職にフォーカスした内容ですが、仕事探しにおいて大切にしたい軸の例を60個まとめているので、ぜひ参考にしてみてください。
関連記事
転職の軸60選! 自分だけの軸を見出すカギは不満の言語化にあり
転職をするときは、明確な転職の軸を立てて目的意識を持つことが大切です。ただ転職の軸を立てるのが難しかったり、どんなふうに立てれば良いのか悩んでしまうこともありますよね。この記事では専門家のアドバイスを交えて、60の転職の軸の例や作成法を解説していきます。
記事を読む

あなたが受けないほうがいい職業は?
3分でできる適職診断で確認してみよう
入社後の早期離職を避けるためには、自分に適性のある職業を選ぶことが大切です。しかし、それがどんな職業なのかが分からず悩む人も多いでしょう。
そんな人におすすめなのが「適職診断」です。40の質問に答えるだけで適性のある職業や受けないほうがいい職業を診断できます。
自分に適性のある職業を早めに知って、就活を成功させましょう。
既卒ならではの落とし穴に要注意! よくある失敗パターンを回避しよう

就活では、選考対策だけでなく、注意点もセットで押さえておくことで、就活成功にぐっと近づきます。既卒就活にありがちな落とし穴に注意しましょう。
ここからは既卒就活にありがちな失敗パターンを紹介していくので、注意点を押さえて失敗を未然に防ぎましょう。対処法もセットで解説するので、就活に備えてよくチェックしてくださいね。
パターン①具体的な就活スケジュールを立てずに行動する
- いつまでに何をやるべきかがわからず、効果的な対策ができない
- 何をすべきかがあいまいで就活のモチベーションが上がらない
- 気になる企業のエントリー時期を逃してしまう
- ダラダラと就活を続けてしまう
就活を進めていくうえでは、計画的に行動することが大切です。たとえば、〇月までにESを作成するなど具体的な取り組みと期日を決めておくことが大切です。
既卒という状況に焦りを感じていて、「このままではまずい」と思いつつも何も行動を起こせない……ということもあるかもしれません。
しかし、時間が経過するほど就活の難易度は上がってしまうことが考えられます。まずは何をいつまでにするのかスケジュールを決めてしまうのが得策です。

キャリアアドバイザー
まずは就職までにやるべきことを洗い出していきましょう。そのあとで、1つずつ何をいつまでにやるのか具体的なスケジュールを決めていくといいですよ。
- 自己分析
- 業界研究
- 企業分析
- 面接練習
パターン②既卒である状態に焦って内定が早く出た企業に就職を決める
- 入社後に仕事の適性にミスマッチが発覚する可能性がある
- 職場のカルチャーに馴染めず居心地の悪さを感じる
- 想像していた働き方とのギャップを感じてしまう
「既卒は人生終了だ」などといった言葉に不安を感じて、内定が出た会社に焦って就職を決めてしまう人もいますが、内定が早く出た企業に就職を決めるのは避けましょう。
内定を出してくれたからという理由だけで仕事を選ぶと、就職後にミスマッチが起こり早期退職になりかねません。
あくまで「自分に向いている仕事」「頑張れそうな環境」など、条件が自分にマッチしている会社を選ぶことが大切です。

キャリアアドバイザー
就職先に迷った場合は社員面談を依頼したり、社内を見学して会社の雰囲気にマッチしているかなどを確認してみてくださいね。
パターン③誰にも相談せずに1人で就活を進める
- 視野が狭くなり、就職先の選択肢が限定的になってしまう
- 不安な気持ちを1人で抱え込むことで精神的な負担がかかってしまう
- 面接がうまくいかない原因が見つけられずなかなか内定につながらない
既卒の人が陥りがちなのが、悩みを1人で抱え込んで誰にも相談しないで就活を進めること。既卒になると周りは就職している人が多く、自分と同じ境遇の人が少なくなり周囲に相談しづらくなるからです。
1人で就活を進めると、得られる情報が限られるだけでなく、孤立化によって憂鬱な気分に陥ってしまうので非効率です。身近な親しい人に悩みを相談したり、エージェントやハローワークなどで就活の進め方を聞いたり、周りの助けを借りながら就活を進めましょう。

キャリアアドバイザー
1人で就活を進めると、間違った進め方に気づけないので、ミスマッチな企業を選んでしまったり、なかなか内定がもらえないという事態につながってしまいかねません。
キャリアアドバイザーからあなたにメッセージ既卒就活ならではのもう一つの注意点
既卒ならではの魅力を大きなアピールポイントにして内定獲得を目指そう
既卒就活でよくある失敗例として、既卒ならではの魅力が伝えきれていないケースが挙げられます。既卒は同じ就業経験のない新卒と比較されることも多いので、新卒と差別化していくことが大切です。
たとえば、「既卒期間に就職のために努力した経験」「就活が上手くいかなかった経験に対する反省と改善点」などを伝えることで、就職への意欲をアピールすることができますよ。既卒ならではのアピールポイントを明確にして、内定獲得を目指しましょう。
正社員採用を狙った就活以外の選択肢も視野に入れておこう!

既卒から正社員としての就職をするにはさまざまな道を選択できます。たとえば、初めから正社員としての採用ではなくても、契約社員として入社をして正社員登用を目指す道も選択肢の一つとしてあります。
正社員として就職を目指すよりも非正規の方が選考難易度も下がる傾向にあるので、いきなり正社員はハードルが高いと感じる場合におすすめです。
ほかにも、紹介予定派遣制度を活用すれば、ミスマッチのリスクを抑えながら就職先を見つけることができます。
実際に企業で働くことで自分の希望に合っている仕事かどうか判断できるので、ミスマッチのリスクを軽減できます。

キャリアアドバイザー
ただ通常の派遣とは違い雇用前提になるので、就業前に選考などが設けられているケースもあります。その場合は選考対策も必要になるので、希望する際はまずは派遣会社などに確認してみましょう。
この記事では、「正社員登用」の意味合いについて詳しく解説しています。正社員としての就職先を目指すためのノウハウも掲載しているのでぜひチェックしてみてくださいね。
関連記事
正社員登用とは? リアルな利用実態から状況別の対策リストを大公開
非正規雇用から正社員を目指すことができる正社員登用制度。利用したいと思っても、どんな制度なのかがわからないと、なかなか一歩を踏み出しづらいですよね。この記事では、専門家のアドバイスを交えながら正社員登用制度の基礎知識から対策まで解説。一緒に正社員としての一歩を踏み出しましょう。
記事を読む

派遣社員の概要から、紹介予定派遣制度についての解説をまとめた記事はこちらです。
関連記事
派遣から正社員を目指す4ステップ! 転職成功のカギは軸の明確化
派遣から正社員になるルートは具体的に4つあります。どの選択肢があっているかは状況や目的によって変わるため、まずは詳細を知ること他大切です。この記事ではキャリアアドバイザーが派遣から正社員になる方法を詳しく解説します。
記事を読む

既卒=人生終了と言わせない! 就活の軸を決めて理想の企業に就職しよう
ここまで、既卒は人生終了というほど危機的な状況ではない理由や、危機的な状況を回避するための方法について解説してきました。
既卒での就職は比較的難易度が高いと言われていますが、既卒就活ならではの就職のコツを押さえてしっかり対策していくことで、自分の理想とする企業に就職することができます。
社会人になれば、仕事が1日のほとんどの割合を占めることになります。生き生きと満足感を持って働くためにも、就活の軸をしっかりと定めたうえで、理想の企業への就職に向けて選考対策を進めていきましょう。

 キャリアパーク就職エージェントは、東京証券取引所グロース市場に上場しているポート株式会社(証券コード:7047)が運営しているサービスです。
キャリアパーク就職エージェントは、東京証券取引所グロース市場に上場しているポート株式会社(証券コード:7047)が運営しているサービスです。





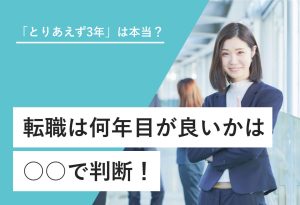








特に混同されがちなのが、「既卒」と「第二新卒」の違い。似ているようで明確な違いがあるので、応募時に間違えてしまわないように一緒にみていきましょう。