目次
- 就活で失敗しないために仕事を選ぶ基準を定めよう
- 自分に合った仕事を選ぶ10の基準
- ①自分が好きな仕事
- ②得意が活かせる仕事
- ③人に誇れる仕事
- ④社会に貢献できる仕事
- ⑤長く続けられる仕事
- ⑥安定した仕事
- ⑦人に勧められる仕事
- ⑧夢が実現できる仕事
- ⑨好きなことに関わる仕事
- ⑩自分の力を試せる仕事
- 自分に合った仕事を絞り込むためのヒント
- 「Will」「Can」の両軸から考えよう
- 「したいこと」だけではなく「したくないこと」も考える
- 企業理念と自分の価値観を照らし合わせる
- インターンシップなどで体験する
- 足りないスキルを学んでみる
- どんなときに楽しさ・やりがいを感じたか考えてみる
- 自分の長所を活かして成果が出た経験をリスト化する
- 仕事選びで落とし穴になりがちな注意点
- 「好き」だけで選んでしまう
- 給与や待遇だけで選んでしまう
- 人からの評価だけで選んでしまう
- 仕事選びについてよくある質問に回答!
- 人生に満足感が得られる自分らしい仕事を探そう
就活で失敗しないために仕事を選ぶ基準を定めよう
こんにちは。キャリアアドバイザーの北原です。
就活は活動を開始してから内定を手に入れるまでに早い人でも数カ月以上、人によっては半年以上はかかる場合もあります。「自分はこの道でいきたい」と思って進めていて、後半になって気持ちが揺らいだり、内定をもらったあとに「こんなはずではなかった」と思ったりしても、軌道修正するのは非常に大変ですよね。
そんな事態を避けるためにも、まずは就活を始める前に「本当に自分にあった仕事なのか」を見極めておきたいですよね。途中で迷いが生まれたときにも明確な基準があれば、それに沿って考え直し自信を持つことができます。
そこで、就職を成功させるためにぜひ知っておきたい、仕事を選ぶ基準についてご紹介します。
まずはあなたが受けないほうがいい職業を確認しましょう
自分に合った職業・合わない職業を見つけることは、就活の成功に不可欠です。しかし、見つけることが難しいと感じる人も多いでしょう。
そんな時は「適職診断」を活用して、志望する職業と自分の相性をチェックしてみましょう。簡単な質問に答えるだけで、あなたの強みや性格が分析され、向いている職業・向いていない職業が診断できます。
自分の適職・適さない職業を今すぐチェックしてみてください。
また、業界も含めてより向いている職業を知りたい場合は「業界&職種マッチ度診断」がおすすめです。
自分に合った仕事を選ぶ10の基準
- ①自分が好きな仕事
- ②得意が活かせる仕事
- ③人に誇れる仕事
- ④社会に貢献できる仕事
- ⑤長く続けられる仕事
- ⑥安定した仕事
- ⑦人に勧められる仕事
- ⑧夢が実現できる仕事
- ⑨好きなことに関われる仕事
- ⑩自分の力を試せる仕事
「良い仕事」と「自分に合った仕事」は違います。たとえば今、テクノロジー業界が注目されています。給与などの待遇面や将来有望なことから就活生にも人気ですが、だからといってテクノロジーに興味がない人にとっては、自分に合った仕事とはなりませんよね。
仕事には、楽しいことややりがいを感じられることだけでなく、つらいことや時間をかけても報われないということがたくさんあります。心が折れてしまいそうなとき、自分に本当に合った仕事でなければ続ける意味がわからなくなってしまうでしょう。
これからいくつかの「仕事を選ぶ基準」を紹介します。自分に合った仕事が何かわからない場合や、今の方向性に迷いが生じたときには、次の基準に当てはめて考えてみてくださいね。
仕事を選ぶ基準は仕事をする目的にもつながりますよね。仕事をする目的を面接で聞かれたときの答え方を知りたい人は、この記事を参考にしてみてくださいね。
関連記事
「仕事をする目的」の正しい答え方とは? 目的例を参考に徹底解説
仕事をする目的は自分なりの考えを準備することが大切です。 この記事では仕事をする目的を探す5つの方法や、3つのタイプ、タイプの例文をキャリアアドバイザーが解説します。仕事をする目的は人それぞれ違うからこそ、自分なりの考えで企業にアピールしましょう!
記事を読む

GATBという検査を受けることで、自分がどんな仕事に向いているかを確認することもできますよ。検査の詳しい概要についてはこちらの記事で詳しく解説しているので、参考にしてみてくださいね。
関連記事
GATBは多角的に適職を導く分析法! 就活への活かし方3ステップ
GATBとは9つの適性脳を測り、仕事の適性を知るために受ける検査です。GATBの受け方から就活への活かし方までキャリアアドバイザーが徹底解説。例題も解説するので、どんな検査なのかイメージし、仕事の適性を知りたい人は受けてみましょう。
記事を読む

【完全無料】
大学生におすすめ!
就活準備で使いたい診断ランキング
1位:適職診断
まずはあなたが受けない方がいい職業を確認してください
2位:業界&職種マッチ度診断
興味のある業界・職種とあなたの相性を診断しましょう
3位:自己分析ツール
あなたの基本的な性格から、就活で使える強み・弱みを診断します
4位:エントリーシート作成ツール
業界特有の質問にも対応! そのまま使えるESが作れます
5位:マナー力診断
あなたのマナーは大丈夫?診断を受けて自分の苦手分野を把握しよう
【併せて活用したい!】
選考前に必ず使ってほしい厳選ツール
①自己PR作成ツール
自己PRがまとまらない人は、ツールを活用して自己PRを完成させよう
②志望動機作成ツール
5つの質問に答えるだけで、受かる志望動機を自動で作成します
キャリアアドバイザーコメント高橋 宙プロフィールをみる
自分に合った仕事を選ぶ基準として10個紹介していますが、10個の中から最適な基準を選ぶのは難しいですよね。
さらに、人によって選ぶべき基準は異なるため「この基準で考えれば大丈夫」といった確約はありません。自分自身の性格や価値観に沿って考え、少しでも自分に合った基準を探していきましょう。
過去の経験を振り返ると基準となるモチベーションの源泉が見えてくる
たとえば、学生時代に何らかの成績でトップになれたときにモチベーションが上がることが多かった人は、得意が活かせる仕事を選ぶと若いうちから周囲よりも活躍できる可能性が高く、仕事を楽しめそうですよね。
もしくは、自分が取り組んだことを通して誰かの役に立っていることで喜びを感じる人は、社会に貢献できる仕事を選ぶとやりがいを感じやすいです。
このように、過去の経験を思い出すことで自分にとって何がモチベーションの源泉になったか考えてみましょう。それに当てはまる基準を優先的にピックアップすると良いですよ。
基準は一つとは限らない! 複数の基準があってもOK
また、仕事を選ぶ基準は1つに絞る必要はありません。自分にとって大切な基準を3つほど決め、もっとも当てはまるものが多い仕事を選ぶ方法もあります。少なくとも「自分にとって譲れない」と思う基準を見極め、優先順位をつけられると良いですね。
①自分が好きな仕事
自分に合った仕事を選ぶ1つ目の基準は「自分が好きな仕事かどうか」ということです。仕事選びをする際には、わかりやすい待遇や「周りにどう映るか」ということをを基準にしてしまいがちです。
しかし、たとえば本当はテーマパークで働きたかった人が、体面や待遇面から金融業界に勤めたとするとどうなるでしょうか。新人の間は勉強しなければならないことがたくさんありますが、金融に興味がなければ努力して覚える気にはなかなかなれないものですし、本当に金融に興味がある同僚に追いつけなくて劣等感を覚えてしまうかもしれません。
たとえ待遇面では劣っていたとしても、興味のある仕事なら自然に興味を持って「もっと知りたい」という気持ちが沸き、無理せず努力することができるでしょう。どちらのほうがより自分らしい毎日を送ることができるかどうかは一目瞭然です。

キャリアアドバイザー
「好きな仕事かどうか」は大前提といえますね。ただ、「就活に成功するため」を目標にし過ぎると、自分が本当に好きなものが何であったか見失ってしまうこともあるので注意しましょう。
②得意が活かせる仕事

自分のやったことを第三者に褒められると充実感や達成感が味わえますよね。得意を活かすことで無理なく企業に貢献し、評価を得ることができます。仕事において相手に評価されることは非常に重要ですので、その分、大切な基準になります。
たとえば、学生時代に文房具店でポップ広告の作成をしていたとします。量販店の販売員として社会人の第一歩を踏み出したとき、わからないことや覚えなければならないことはたくさんありますが「ポップ作成なら、すぐにでも貢献できる!」と思えれば、毎日の業務や研修も頑張って乗り切ることができるのではないでしょうか。
実際に勤務先に貢献できることがあれば、モチベーションの維持・向上につながります。
自分の得意を理解するためには以下の記事を参考にしてくださいね。得意分野についてはこちら。
関連記事
面接で自分の得意分野を聞かれたら? 上手な答え方の例文を紹介
得意分野を通して自分の特性を伝えよう こんにちは。キャリアアドバイザーの北原です。面接を控えた就活生から、 「自分の得意分野がわかりません」「得意分野をどうアピールすればいいのかわかりません」 といった声が寄せられます。 […]
記事を読む

少し言葉は似ていますが、得意なことについてはこちらを読んでみてください。
関連記事
得意なことが必ず見つかる6つの探し方|伝え方や具体例も徹底解説
得意なことを仕事にするには、まず自分の得意なことを見つけるために自己分析をしてみましょう! 今回は、得意なことを見つける6つの方法をキャリアアドバイザーが紹介していきます。得意なことを仕事にするメリットとデメリットも紹介するので参考にしてみてくださいね。
記事を読む

③人に誇れる仕事

就活生
人に自慢できるような仕事って良いですね!

キャリアアドバイザー
ちょっと待ってください。自慢できると誇れるは少し意味が違いますよ。
人に誇れる仕事というのは、見た目が派手で目立つ仕事ということではありません。
仮に「地味な仕事」に見える仕事だとしても、自分が自信をもって取り組むことができる仕事、自尊心を高めることができる仕事なら、つらいことがあっても続けることができます。
自分が誇りを感じられる仕事であれば、人に説明することができるはずです。一方で、友人や周りの人に堂々と説明できない仕事は、将来にわたって長く続けていくことは難しいでしょう。
説明できる仕事というのは、社会的な信用を高めることにもつながります。社会的な信用は周囲の人に信頼されやすいというだけでなく、家を買うときにローンを借りやすいといった現実的な面にも関わってくるのでよく考えておく必要があります。

キャリアアドバイザー
その企業が存在する社会的意義を掘り下げると、人に誇れる点が見えてきます。どんな仕事も必要があるために存在していると考えると、誇れるポイントが見つかりやすいですよ。
④社会に貢献できる仕事
先輩社員の声として「顧客満足度が何より励みになる」ということを耳にしたことがあるのではないでしょうか。このようなことを聞くと、きれいごとなのではと感じるかもしれません。
しかし、実際に仕事を続けていくうえでは、人や社会に貢献しているという人間の基本的な欲求を満たすことが実はとても重要です。
機械メーカーの製造担当など、直接消費者とは接しない場合でも「この機械を導入したおかげで、消費者向けの価格ダウンが実現できそうだ」と取引先企業から感謝されれば、自分の関わっていることが社会に役に立っていることが実感できます。
もちろん厳密には社会に貢献していない企業はありません。自分の中で社会貢献の定義をしっかり定めたうえで考えられるといいですね。
- 利益追求ばかりでなく事業の社会貢献性を大切にしている
- SDGs(持続可能な開発目標)への取り組みに積極的
- CSR(企業の社会的責任)の取り組みに積極的

キャリアアドバイザー
社会人は、「自分が社会に貢献する」ことを意識して日々業務に取り組んでいます。目の前にいる人だけでなく、社会に貢献できていることがわかると、将来にわたるやりがいにつながります。
⑤長く続けられる仕事

転職が当たり前ともいえる時代ですが、1つの仕事に長く携わっていたほうがスキルやノウハウが蓄積された優れた人材に成長できることは間違いありません。入社した会社で長く続けていくには、仕事内容が自分に合っていることや人間関係に加え、キャリアアップのチャンスがあるか、昇給制度が整っているかという点がカギとなります。
たとえば40代の先輩女性社員が出産を経て部長になっている実績があるなど具体的な前例があれば「自分も仕事と家庭を両立させながらキャリアアップや昇給を実現できる」というモチベーションが維持できます。
最近では、フレックスタイム制の導入などで自分のライフスタイルに応じた仕事ができたり、オフィスに行かなくても仕事ができたりする企業も増えてきました。将来、育児や介護に直面した場合でも、働き方に自由度があると心配なく続けていけるでしょう。
- フレックス制度の有無
- リモートワークの導入可否
- 育休・子育て制度の充実度
フレックスタイム制度についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
関連記事
自由に働けるって本当? フレックスタイム制度の仕組みを知ろう
フレックスタイム制度とは労働者が働く時間を指定できる制度です。 この記事ではキャリアアドバイザーがフレックスタイム制度のメリットやデメリットを解説します。フレックスタイム制度が向いている人の特徴も紹介しているので、ぜひ企業選びの参考にしてくださいね。
記事を読む

キャリアアドバイザーコメント長尾 美慧プロフィールをみる
長く仕事を続けられる環境として、仕事内容が合っていることも重要です。
同期よりも成長スピードが早く、若手から活躍できるチャンスもあるかもしれませんし、上司からの評価も上がりキャリアアップにもつながるでしょう。しかし仕事内容が合っていなければ、次第に仕事がつらくなる可能性もあります。
ありがちなのが、業界への憧れが強く、職種は気にせず入社を決めてしまい、結果的にその仕事が自分に合わず苦労するパターンです。せっかく就活で苦労して内定を獲得したにもかかわらず、仕事内容でつまずいてしまうのはもったいないですよね。業界で選ぶことは問題ありませんが、仕事内容との相性も視野に入れておきましょう。
長く続けるためには社員や社風との相性も大きくかかわる
また、社員との相性の良さも同様に大切です。たとえ希望の仕事に就くことができても、人間関係がうまくいかなければ働くこと自体がつらくなってしまうことも大いにあり得ます。実際、転職理由の上位に「人間関係」は例年ランクインしています。
しかし、就活の段階から社風を完璧に理解することはなかなか難しいです。説明会や面接だけでなく、OB・OG訪問も積極的におこない社風に対する理解を出来るだけ深めましょう。
OB・OG訪問についてはこちらの記事でそのやり方を解説しています。興味を持った人はぜひ見てみてくださいね。
関連記事
OB・OG訪問攻略ガイド|企業理解や選考に役立てるコツを解説
OB・OG訪問をして周囲と差をつけよう こんにちは。キャリアアドバイザーの北原です。 「OB・OG訪問って必要なんですか?」「OB・OGってどうやって見つければいいんですか?」 就活生から、こんな声を聞くことがあります。 […]
記事を読む

⑥安定した仕事
- 給与が高い状態を保てる。昇給も可能
- 職場環境が良く離職者が少ない
- 浮き沈みの少ない業界と経営
- ワークライフバランスを保てる
- 他社でも応用できるスキルが身につく
実力を発揮できる環境は人それぞれです。次々と新しいことに挑戦できるベンチャー企業でこそスピーディーに成長できる人もいれば、安心感をもって仕事に打ち込んだほうが結果が出せるという人もいます。

就活生
でもなんだか安定っていうのは守りに入っているみたいで……。

キャリアアドバイザー
そんなことはありませんよ。イメージだけでなくて、しっかりメリットも把握しましょう。
安定を求めることは決して悪いことではありません。自分の力を存分に発揮する上で、「安定」がとても重要となる場合もあることを覚えておきましょう。
若いうちから安定を求めるのはつまらないと感じる人もいるかもしれませんが、その仕事をよく知ってみると、非常にやりがいのある仕事である場合は多々あります。業種でいえば、公務員やインフラエンジニア、大手メーカー、薬剤師や看護師といった資格が活かせる仕事は安定した仕事の代表格といえます。
- 自己資本比率が50%以上
- 上場している など
- 公務員
- インフラ業界
- 金融業界
- 大手メーカー
- 薬剤師・看護師など専門性が高い職種
⑦人に勧められる仕事
仮にその会社に入社したとして、親しい後輩から「先輩の仕事を教えてください」と言われたときに本心から勧められるかどうか、考えてみましょう。
誰かに話すようなつもりでその仕事を人に勧めるときのセリフを考えてみるのも良いでしょう。すぐに言葉に詰まってしまうのであれば、本心から良いと思えていないのかもしれません。
このように「人に勧める」ということは、自分の仕事を客観的に見つめ直すことになります。視点を変えて「この仕事は周りや社会からどんな風に見られているか」「客観的に見てどういった魅力があるか」がわかると、自分の価値観と合っているか判断しやすくなります。

キャリアアドバイザー
仕事選びにおいて、客観的な視点を持つことは非常に重要です。実際に人に勧めることを考えてみることで、わかってはいたものの直視することを避けていた事実に向き合うことができます。
⑧夢が実現できる仕事
起業などの漠然とした将来の夢がある場合、それが実現できる環境なのか、その夢に近づく仕事なのか考えてみましょう。
もちろん、自己実現という意味での夢でも構いません。仕事は自分の強みや自分らしさを発揮して社会に貢献するものであり、勤務先から与えられた仕事をきちんとこなせばそれで終わり、というものではありません。
上司や先輩から学んだことを理解したうえで自分なりに工夫し、「こんな取り組みをすればもっと貢献できる」ということが実践できれば、会社とともに自分も成長することができます。

キャリアアドバイザー
上司やOB・OGに「こんな人になりたい」と思える人がいることも大切です。夢や目標があることで、日々の仕事により励むことができるでしょう。
⑨好きなことに関わる仕事

たとえば映画が大好きという人なら、映画監督になると趣味を仕事にすることの壁に直面することもあるかもしれません。
しかし映画の配給会社の写真として大好きな映画を支える仕事なら、好きなことに仕事として関わることで大きな幸福を得ながら、安定して働くといった希望の働き方も実現できるかもしれないのです。
好きなことをそのまま仕事にするのではなく、その周辺にも目を向けることで、可能性はぐっと広がります。好きなことに関われる仕事であれば、幸福感が得られるだけでなく、「もっと、いろいろなことに挑戦したい」という向上心やアイデアが生まれることでしょう。
⑩自分の力を試せる仕事
最後の基準は、「自分の力を試せる仕事」かということです。人は、自分が得意なことが活かせる仕事や好きな仕事に出会うと、「もっと仕事を通じて成長したい」「もっといろいろなことに挑戦したい」と思うものです。
たとえば、英語が得意な人なら、「将来はもっと語学力を活かして海外との大きなコミュニケーションに関わった仕事を任されたい」と思うでしょう。外資系や大企業など挑戦しがいのある仕事を選択肢に入れることによって、より自分の強みがアピールできたり、自分の将来像についてもイメージしやすくなりますね。
自分のどんな力を試したいのか、どのくらいの規模のフィールドで試したいのかといったイメージも具体的に考えてみることでより明確な基準となります。
キャリアアドバイザーコメント長尾 美慧プロフィールをみる
「安定した仕事」を基準の1つとして紹介しましたが、転職が当たり前になった現在「安定した仕事」はさまざまな意味を含んでいます。
従来、安定とは公務員や大手企業に就職することとされていました。しかし終身雇用制が崩壊しつつある現在、企業に依存せず個人に力をつけることが安定と定義される傾向もあります。
そのため、1つの企業に長く勤めるよりは、転職を通じてスキルアップや年収アップが叶えられる将来を見据え、若手から裁量のある仕事を任せてもらえるような企業を選択する学生が年々増えています。
まずは自分にとっての「安定」を理解して、そのうえで働きたい環境を考えよう
ベンチャー企業はもちろん、大手でもベンチャー精神を大切にしている企業は存在します。 まずは自分にとって「安定」とは何なのか考えることから始めましょう。そのうえで、もしあなたがこのような意味での安定を求め「企業の知名度に頼らず自分自身にスキルを付けたい」と考えている場合は、今説明したような環境も視野に入れてみてはいかがでしょうか。
自分に合った仕事を絞り込むためのヒント

仕事を選ぶ基準が明らかになったところで、10の基準をどう当てはめ、どうやって絞り込んでいけばいいのか難しく感じるかもしれません。
10の基準を全て完璧にクリアさせるのが大変であれば、その中で特に自分が譲れない基準を満たしているかどうかから考えていくといいでしょう。そのほか、自分に合った仕事を絞り込むためのヒントをご紹介します。
「Will」「Can」の両軸から考えよう

自分に合った仕事を絞り込むときは、「Will」と「Can」の双方から絞り込んでいきましょう。「Will」は「社会人になったらこんな仕事をしてみたい」「仕事を通じてこのようなキャリアを進んでいきたい」など仕事を通じてイメージする自分の将来像と言えるでしょう。
これに対して「Can」は「自分ができること」「自分が得意なことや、自分が強みだと思っていること」を表します。ただ、「こんな社会人になりたい」「こんな仕事をしてみたい」という「Will」だけで考えても、「Can」が欠けていると、自分に合った仕事を選ぶことは難しくなります。
まずは事前に自己分析をしっかりとおこない、第三者からのフィードバックも参考にしながら自分の強みをまとめましょう。そうすれば、「Can」と「Will」の両方が満たされた仕事を選べますよ。
「したいこと」だけではなく「したくないこと」も考える
視点を変えて「したいこと」ではなく「したくないこと」をピックアップしてみるのもおすすめです。現場に出て体を動かす仕事は避けたい、数字を扱うのは嫌だなど、何でもかまいません。箇条書きで書き出すことで、自分がしたくないと思っている仕事が明確になってくるでしょう。
希望の仕事があるのであれば、リサーチしてその仕事のマイナスポイントもすべて書き出してみましょう。その中に、先ほど書き出した「自分がしたくないと思っている仕事」の要素が含まれていないでしょうか。

キャリアアドバイザー
どうしてもしたくないことの優先順位をつけておくことで、希望の仕事を客観的に評価することができます。
企業理念と自分の価値観を照らし合わせる
「企業理念」とは、企業の価値観と重要に考えている「軸」のことです。これをじっくりと読み込み、理解することで、自分の価値観とのマッチ度が高いかどうかを確認するのも重要です。
価値観というのは、物事や取り組みに対する考え方のことです。企業理念は社会にどう貢献するかという視点で書かれていることが多いですが、これから就活する側にとっては「働く上で大切にしたいこと」と置き換えることができます。
- 企業のホームページの企業理念・ビジョンを読む
- 社長などのSNSや書籍、インタビューを読む
- 中期経営計画を読む
自己分析をしっかりやっておくと「目標達成のために努力を惜しまない」「周りと協力して取り組むことを大事にする」といったような「自分が大切にしていること」がわかってきます。その上で、企業の価値観と離れていないかどうか、よく照らし合わせてみることをおすすめします。
自分が働く上で大切にしたいことの考え方は、こちらの記事で詳しく解説しています。ぜひ事前に把握しておきましょう。
関連記事
働く上で大切なことの回答で仕事に取り組む姿勢をアピール|例文付き
働く上で大切なことを聞かれたらどのように回答しますか? 今回は面接を勝ち抜くための「働く上で大切なこと」の回答方法をご紹介します! 企業が働く上で大切なことを聞く理由や、答えるときの心構えをキャリアアドバイザーが徹底解説します!
記事を読む

インターンシップなどで体験する
実際に就労体験をしてみると、漠然としたイメージしかわからなかったときよりも、仕事内容がよりはっきりと理解できるようになります。最近ではインターンシップを実施している企業が数多くありますから、時間を見つけて積極的に参加してみましょう。
コロナ禍で対面でのインターンシップを見送っている企業もありますが、Webで一日の様子のダイジェスト版を配信しているところもあります。日頃から積極的に情報収集し、入社後のイメージをより明確にする体験があればぜひ挑戦してみましょう。
足りないスキルを学んでみる
実際に仕事をした経験がないと、「やってみたい」というイメージだけが先行してしまっているかもしれません。
もし希望の仕事があって、そのために自分に今足りないスキルがあると思うなら、勉強してみるのも1つの手です。コンサルや営業など人を説得する必要がある仕事に就きたいと思っていても、実は人前で話すのが苦手だという人であれば、ディベート講座に参加してみるのもいいでしょう。
新しい学びを吸収することによって視野が広がるだけでなく、殻を破るのはそれほど難しいことではないことに気づけるため、就活により積極的になれるかもしれません。
- 事務仕事がしたい…簿記を勉強する
- 商社に就職したい…TOEICで高得点を目指す
- 社会人としての基礎力を付けたい…ビジネスマナーが学べる秘書検定を受けてみる
対りないスキルに学ぶための資格を取得するのもおすすめです。以下の中から選んでみましょう。
関連記事
就職に有利な資格は3軸で判断! 役立つ27の資格を業界別に大公開
これから就活をひかえている人のなかには「就活に有利な資格を取得してライバルと差をつけたい」と考える人もいますよね。この記事では、就活に有利になりやすい資格やどの資格が今の自分に必要なのかをキャリアアドバイザーが解説します。
記事を読む

どんなときに楽しさ・やりがいを感じたか考えてみる

自分の経験を振り返って自分の価値観を見つけますが、この振り返りのプロセスを思い起こしてみましょう。たとえば、モチベーショングラフや自分史を作るのも良いですね。
学校生活やアルバイトなどで、どんなときに楽しさややりがいを感じたでしょうか。実際にやりがいを感じた経験を紙に書き出してみると、自分がどんなことにやりがいを感じるのかがはっきりしてきます。
たとえば根気強くコツコツと細かいことを積み上げていったことが楽しかった、チームであれこれ相談しながら作り上げていったのが良かったなど、自分がやりがいを感じた理由が見えてくると、仕事選びの軸として活用できます。
自分史の作り方は以下の記事に詳しいので、ぜひ挑戦してみましょう。
関連記事
自分史の書き方3ステップ|記入例や就活に役立つ自己分析方法を解説
自分史を作成することは、就職活動を効率的に進めるのに役立ちます。 この記事では、自分史の作成方法と自己分析の仕方をキャリアアドバイザーが解説します。 自分史を活かせる質問例や回答例も紹介しているので、自己分析の際の参考にしてみてくださいね。
記事を読む
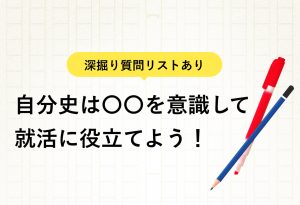
自分の長所を活かして成果が出た経験をリスト化する

自己分析で掘り起こした「自分の経験」は貴重な仕事選びの参考になります。どんな成功体験があったのか、それはどうしてか。どんな努力をしたから成功したのか。これらをリスト化してみましょう。
あなたにとっては当たり前にできることなので、前述のポイントのように特にやりがいは楽しさは感じていないという場合もあります。しかし、自分にとっては当たり前でも、仕事として人から評価されればそれがやりがいにつながります。
大勢の仲間と一緒に物事を作り上げていくという全体を見渡す力や、細かいことを時間や手間を惜しまずに成功するまでやり遂げる粘り強さなど、「自分の長所や強み」が明確になると、自分らしさが発揮できる仕事を見つけるヒントになります。
キャリアアドバイザーコメント上村 京久プロフィールをみる
WillだけでなくCanの視点から考えることは、自分に合った仕事を見つけるためには避けて通れません。新卒はポテンシャル採用のため「入社後何を成し遂げたいか」といったWillに焦点が当てられがちですが、入社して活躍できそうな学生を採用したい思いを企業は少なからず持っています。
活躍できる人とは、自分自身が持つスキルや志向性を活かせる環境に身を置き、努力ができる人です。その環境選びを就活でおこなうため、まずは自分の武器を理解をし、それを活かせる仕事内容や社風を的確に見極められると、選考も通過しやすくなるうえに入社後活躍できる企業や仕事が見つかるでしょう。
Canがわからない場合は「楽しいこと」や「褒められたこと」にも注目しよう
しかし、自分にとってのCanが何かわからないという学生も多いです。そんなときは、得意なことだけでなく「褒められたことがあること」「やっていて楽しいこと」も含め、何でも良いのでひたすら紙に書き出しましょう。「コンビニのアルバイトでレジが少し早く打てる」など、小さいことでも構いません。
いくつか書き出すことで共通点が発見できたり「これだ」と思える武器がきっと見つかります。それを人に説明できるほど言語化すれば、心から魅力的に思える企業や仕事に出会えますよ。
自分に合った仕事の見つけ方についてはこちらの記事も参考にしてください。
関連記事
自分に合った仕事の見つけ方4ステップ|理想の働き方別の適職も解説
自分に合った仕事を見つけるには、自己分析と希望・スキルがマッチする点を見つけることが大切です。 この記事では自分に合った仕事探しの見つけ方をキャリアアドバイザーが解説します。 解説動画も参考に、自分に合った仕事を見つけてくださいね!
記事を読む

あなたが受けないほうがいい職業は?
3分でできる適職診断で確認してみよう
入社後の早期離職を避けるためには、自分に適性のある職業を選ぶことが大切です。しかし、それがどんな職業なのかが分からず悩む人も多いでしょう。
そんな人におすすめなのが「適職診断」です。40の質問に答えるだけで適性のある職業や受けないほうがいい職業を診断できます。
自分に適性のある職業を早めに知って、就活を成功させましょう。
仕事選びで落とし穴になりがちな注意点

ここからは、仕事選びで注意してほしいポイントについてご紹介します。あまり深く考えずに直観に頼ってしまうと、昔から知っている企業や、身近な人が勤めている企業が自分にとっても良い企業だと勘違いしてしまったり、SNSでの評判に流されたりしがちです。
特に、次に紹介する3点は就活生がよく陥ってしまう落とし穴。希望の仕事がある人は、以下の点に当てはまらないかぜひチェックしてみてください。
「好き」だけで選んでしまう
「好き」というのは大事な仕事選びの基準ではありますが、よくリサーチもしないで「なんとなく好き」と思って突き進むとズレが生じてしまいます。
仕事であれば「好き」なことだけやっていればいいというものではなく、努力をしなければならないことや、やりたくないこともやらなければならないときがあります。「好き」だけで選んでしまうと、仕事がイメージと違ったことで、好きなことまで嫌いになってしまう可能性もあります。
給与や待遇だけで選んでしまう
次に陥りやすいのが「給与」や「待遇」だけに目を奪われてしまうことです。

就活生
仕事内容ではA社のほうが魅力的だけど、初任給ではB社のほうが高いし、研修制度も充実しているからB社の方が良さそうだな。
このような就活生をよく見かけますが、成功するにはどんな会社でも「自分で努力しなければならないところ」が必要です。
企業は学校ではないので、「仕事を通じて自分から学んでいく」姿勢が維持できるかどうかが問われます。また初任給はあくまでも入社1年目の給与です。自分の努力次第で大きく変えることができますよ。
人からの評価だけで選んでしまう
つい先輩や周りの人の意見を鵜呑みにしてしまうと、後から「こんなはずではなかった」ということになりかねません。
「先輩が言っているのだから間違いない」とか「親が言っているんだからきっとそうだ」最近では「SNSでこんな風に言われているのだから」という理由で、自分で確認せずにそのまま受け入れてしまうのは危険です。周りの意見はあくまで「参考」だと考えましょう。
最終的には自分の人生にかかわることですから、自分が本当にそう思っているのか、さまざまな角度から検討し、自分で納得して決めるようにしましょう。
仕事選びについてよくある質問に回答!
多種多様な企業がある中で、仕事を選ぶ基準が定まらない人やどうやったら定まるのか悩む人もいますよね。ここでは、そのような学生の悩みに対して、キャリアアドバイザーが回答していきます。
-
自分だけの仕事を選ぶ基準を持つためにはどうすれば良いですか?
自分だけの仕事を選ぶ基準を持つためには、自己分析をして、自分がどういう人物であるのか、自己理解を深めることが欠かせません。人はさまざまな経験や周囲の人々との人間関係を通じて、いろいろな価値観や考え方を身につけていきます。同じ体験をしたとしても、価値観や思考の仕方が異なれば行動も変わるため、おのずとその結果も違ってくるでしょう。
そこで、学校生活やサークル活動、アルバイトなどでの経験をできるだけ多く書き出し、どういう取り組みをしたのか、その理由は何か、そのときの考えや感情はどうだったのかなどと、自問自答を繰り返し深掘りしていきましょう。そこから、自分の共通する行動特性や物事の判断基準、価値観、志向などが見えてくるはずです。
これらはあなたの人柄を形づくっている基盤であるため、仕事を選ぶ基準として重要なものだといえます。
-
仕事を選ぶ基準を定めるときに注意すべきことを教えてください。
仕事を選ぶ基準を定めるときは、企業側の要素だけでなく、自分がどうしたいか、どう貢献できるかをふまえて決めるようにしましょう。たとえば、給与や待遇、福利厚生の充実度は仕事を選ぶ際には重要な要素の1つですが、企業の経営状況によって変わる場合もあります。
また、企業の規模の大きさ、知名度、安定性、自宅からの通勤時間の短さ、都会のオフィス街にあるといった立地条件などだけで選ぶのも避けましょう。またSNSに書き込まれた企業の評判などは、あくまでも個人の感想であって事実とは限りません。その内容を鵜呑みにすることをせず、参考程度に留めておくと良いでしょう。
人生に満足感が得られる自分らしい仕事を探そう
いろいろ紹介してきましたが、一番大切なポイントは、自己分析を通じて掘り起こした経験から「もっとも自分らしくいられるのは、何をしているときか?」という「自分の価値観」を基準にすることです。
待遇や世間のイメージなどで選択しても、これからの人生、自分の仕事と常に向き合っていくのは自分自身。今回の記事で確認したことを振り返り、ぜひ充実した人生を送れるよう、自分らしく輝くことのできる仕事を見つけられるといいですね。

 キャリアパーク就職エージェントは、東京証券取引所グロース市場に上場しているポート株式会社(証券コード:7047)が運営しているサービスです。
キャリアパーク就職エージェントは、東京証券取引所グロース市場に上場しているポート株式会社(証券コード:7047)が運営しているサービスです。












キャリアアドバイザーコメント高橋 宙プロフィールをみる
仕事を選ぶ基準を持つにあたって押さえておきたいのは「仕事をするうえで譲れないものは何か」といった観点から考えることです。企業の知名度やイメージといった表面的な部分だけに捉われず、自分の価値観にあった企業を見つけられる一歩となります。
また、実際に面接で仕事を選ぶ基準が何か質問されることも多々あります。その際に面接官が納得できるような基準とその理由を述べ、その企業のどういった点が基準に当てはまるか伝えられれば、自然と志望動機にもつながりますね。
仕事を選ぶ基準を決めることはミスマッチの防止にもつながる
さらに、自分にとって働きやすい企業を見つけやすくなること、その結果就活がスムーズに進むこと以外にも、企業を選ぶ基準を設定することで得られるメリットがあります。
たとえば、入社後のミスマッチの防止が挙げられます。入社後、基本的に数年以上、もしくは定年まで腰を据えて働く人もいるでしょう。にもかかわらず「思っていた仕事と違った」と感じてしまうのはもったいないですよね。就活中だけでなく、入社後の社会人生活を活き活きとしたものにするためにも、仕事を選ぶ基準はしっかりと定めましょう。