目次
- エントリー数は就活の方針によって異なる
- エントリーの定義とは
- 平均の本エントリーは9.3社
- 文系は平均10.7社
- 理系は平均6.3社
- 10社のうち2~3社で内定
- エントリー数に関する3つの傾向
- プレエントリーしてもES提出しない人も多い
- 売り手市場でエントリー数は減少
- 3月と4月が本エントリーのピーク
- エントリーが多い場合のメリット・デメリット
- メリット:視野を広く持ち経験も積める
- デメリット:スケジュール管理が難しくなる
- 注意点:エントリー前に最低限の準備をしよう
- エントリーが少ない場合のメリット・デメリット
- メリット:1社に掛けられる時間が増える
- デメリット:手持ちの駒が少ない
- 注意点:一社ごとの精度を高める
- 4つの注意点
- ①タイミングを逃さない
- ②効率的なES提出の準備を
- ③プレエントリーは迷った場合、エントリーしよう
- ④エントリー数にとらわれすぎない
- 自分に合ったエントリー数で有利に進めよう
エントリー数は就活の方針によって異なる
こんにちは。キャリアアドバイザーの北原です。
「就活エントリーは何社くらいが適切でしょうか」
「何月ごろにエントリーすればいいでしょうか」
といった就活生の声を聞きます。平均のエントリー数などはほかの就活生の活動量を知ることができます。その目安を知ることで安心感を得られたり就活の方針を決めるのに役立ちます。一方で、「特定の業界に絞った就活をする」「とりあえずエントリーをして志望業界や職種を固めていく」と就活生ごとの活動方針によって適切なエントリー数は異なってくるのも事実です。
エントリー数が多すぎたり少なすぎたりしても、それぞれメリットとデメリットがあります。ここでは文系・理系別のエントリー数、面接や内定通過率などの就活メディアなどが公表している調査結果を紹介し、エントリー数を決める際の注意点をお伝えします。

港くん

キャリアアドバイザー
志望業界ややりたい仕事は決まっていますか?

港くん
いえ、サイトや説明会からフィーリングが合いそうな企業を受けようと思っています。

キャリアアドバイザー
手探りで就活を始める場合、10社では手札が少なすぎますね。まずは就活仲間がどれくらいエントリーしているのか知っておきましょう。
就活のエントリー数はどうすべき?就活のプロが解説します
【完全無料】
大学生におすすめ!
就活準備で使いたい診断ランキング
1位:適職診断
まずはあなたが受けない方がいい職業を確認してください
2位:業界&職種マッチ度診断
興味のある業界・職種とあなたの相性を診断しましょう
3位:自己分析ツール
あなたの基本的な性格から、就活で使える強み・弱みを診断します
4位:エントリーシート作成ツール
業界特有の質問にも対応! そのまま使えるESが作れます
5位:マナー力診断
あなたのマナーは大丈夫?診断を受けて自分の苦手分野を把握しよう
【併せて活用したい!】
選考前に必ず使ってほしい厳選ツール
①自己PR作成ツール
自己PRがまとまらない人は、ツールを活用して自己PRを完成させよう
②志望動機作成ツール
5つの質問に答えるだけで、受かる志望動機を自動で作成します
エントリーの定義とは
エントリーシート(ES)の提出時、企業に自分の情報を登録した時などに「企業にエントリーした」となんとなく使っているけど、エントリーの定義を知らない人も多いのではないでしょうか。エントリーは大きく分けて2段階があり、プレエントリーと本エントリーがあります。
プレエントリーは就活情報サイトから希望する企業を登録することを指します。プレエントリーすることで、企業の説明会の開催情報やエントリーシートの受付期限などの選考情報が届くようになります。
本エントリーはESなどの応募書類を提出し、選考に進みたい応募の意思を企業側に表明することです。就活サイトによってはプレエントリーをエントリーと表記するなど表現がまちまちなので、注意する必要があります。
エントリーについては、こちらの記事でも詳しく解説しているので、スムーズに就活をスタートするための参考にしてみてくださいね。
関連記事
就活のエントリーとは最初の意思表示! 準備~完了までの6ステップ
就活におけるエントリーは、就活開始前に知っておくべき基本事項です。この記事では、就活におけるエントリーの説明から、平均エントリー数、エントリーの流れなどをキャリアアドバイザーが徹底解説します。
記事を読む

まずはあなたが受けないほうがいい職業を確認しましょう
自分に合った職業・合わない職業を見つけることは、就活の成功に不可欠です。しかし、見つけることが難しいと感じる人も多いでしょう。
そんな時は「適職診断」を活用して、志望する職業と自分の相性をチェックしてみましょう。簡単な質問に答えるだけで、あなたの強みや性格が分析され、向いている職業・向いていない職業が診断できます。
自分の適職・適さない職業を今すぐチェックしてみてください。
また、業界も含めてより向いている職業を知りたい場合は「業界&職種マッチ度診断」がおすすめです。
平均の本エントリーは9.3社
全国求人情報協会の「2025年卒学生の就職活動の実態に関する調査(2024年卒・2025年卒比較)」によると、2025年卒のプレエントリー数は14.8社。前年の16.8社から2.0社減少したことがわかります。
また、本エントリーに当たる「ES提出」は9.3社でした。ただし、エントリー数は文系理系によっても異なります。ES通過後の数字を見ていきましょう。
文系は平均10.7社
同じく全国求人情報協会の「2025年卒学生の就職活動の実態に関する調査(2024年卒・2025年卒比較)」によると、文系の本エントリー数は平均よりも多い10.7社、プレエントリー数は17.2社とされています。文系の中でも特に多いのは文系・国公立学生で、プレエントリー22.6社、本エントリーが13.4社という結果でした。
文系学生のエントリー数が多いのは、学業が比較的忙しい理系よりも就活を活発におこない、内定後も活動を継続する人が多いことが関連していると言えます。見方を変えれば、文系に人気のある企業や職種は競争率が激しくなるとも言えるでしょう。
理系は平均6.3社
一方の理系はプレエントリー9.9社・エントリー6.3社と少なく、もっとも多い文系・国公立学生の約半数でした。一見文系学生よりも就活の活動量が少なく見える理系学生ですが、理系ならではの就活スタイルもあります。
応募方法としては、企業や就職サイトなどから応募する自由応募に加えて、教授推薦・学校推薦・後付推薦といったスタイルがあります。
- 学校推薦…学部や学科ごとに設けられた推薦枠に応募する
- 教授推薦…研究室ごとに設けられた推薦枠に応募する
- 後付け推薦…自由応募で選考に申し込み、選考の途中で推薦状を提出する
理系学生は多くの学生が推薦形式を活用しており、合格率は比較的高く、内定辞退率は低い傾向にあることが、エントリー数が文系よりも少ない理由といえそうです。
学校推薦について詳しくはこちらの記事を読んでみてくださいね。
関連記事
学校推薦による合格率はどれくらい? 確実に受かるための注意点まとめ
学校推薦による合格率は100%ではないので、受かるための努力も必要です。今回は種類別に合格率を紹介するとともに、合格率を上げる4つの方法をキャリアアドバイザーが解説します。学校推薦を利用する際の注意点も紹介しているので、参考にしてみてください。
記事を読む

理系学生に人気の職業はこちらに一覧でまとめてあります。
関連記事
理系の職業一覧! 学部別のおすすめや職業選びの基準も解説
理系の学生向けの職業は数多くあります。この記事では、理系の学生の持つ能力を活かせる職業や職種、業界をキャリアアドバイザーが紹介していきます。自分に合う職業の見極め方なども解説していくので、理系の学生はぜひチェックしてみてくださいね。
記事を読む
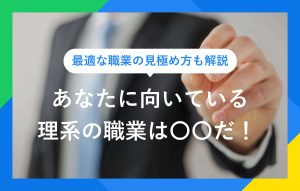
キャリアアドバイザーコメント吉田 実遊プロフィールをみる
一番はESのクオリティをあげていくことが大事です。上記にもあるように、ES提出後、選考の最後まで使われることがあるので、客観的な目線のチェックも入れて提出するといいでしょう。
一方で、人気業界であるとES通過率が下がることもあるため、必ずしも数を打てば当たるとも言い難いです。ご自身の希望業界も大事ですが、親和性のある業界や別の角度から見て、自分に合いそうな業界も合わせて受けていくことで、心理的にもゆとりを持って進められるようにしていくのがベターだとおもいます。
ESで落ちてしまう場合はこちらの記事を参考に書き方や内容を見直してみてくださいね。
関連記事
就活の書類選考で落ちる理由とは|通過率をあげるための対策
書類選考に落ちる人は、書き方や内容を見直す必要があります。 この記事では書類選考で落ちる理由、通過率を上げるポイントをキャリアアドバイザーが解説します。 解説動画も参考に、熱意が伝わる応募書類で選考を通過しましょう!
記事を読む

10社のうち2~3社で内定
同調査によると、ESを提出した9.3社のうち、内々定の獲得は2.4社となり、エントリー数に対する内々定獲得社数は約25.8%でした。つまり10社エントリーしたうち、2~3社の内々定をもらえる計算になります。
余裕を持った内定を目指すためには、10社程度エントリーするのが安心です。
内定がなかなかもらえない場合はこちらの記事も参考にしてみてください。
関連記事
内定がもらえない人の特徴23選|原因別に今するべきことを徹底解説
内定がもらえない人は、就活を振り返って新たなアプローチを取ることをおすすめします。 この記事では内定がもらえない人のための23のチェックリストと対策をキャリアアドバイザーが解説します。 動画も参考にして、現状を検証し一歩を踏み出してくださいね。
記事を読む

エントリー数に関する3つの傾向
いざ就活を本格的にはじめるとなってエントリー数は、活動量を測るうえでの大きな目安となります。最近のエントリー数に関してどのような傾向があるのでしょうか。
プレエントリーしてもES提出しない人も多い
プレエントリーしてもESまで提出するのは半数~6割程度。14.8社のプレエントリーのうち、ES提出は9.3社となっています。プレエントリーをする人は「企業の説明会、選考の情報を知りたい」という人が多数ですが、本エントリーになると「実際に企業に就職したい」という志望意向が強くなるからです。
また、プレエントリーは個人情報に加え、簡単な自己PRや志望動機を添えるだけなので、比較的簡単にできます。一方、本エントリーではより詳細な事項を書き込み、それを基本的には手書きで作成しなければなりません。志望度の高さと忙しさの兼ね合いで見送ったり、プレエントリーをしてみて企業の詳細な情報を知るにつれ興味が薄れたという例が見られます。
売り手市場でエントリー数は減少
近年、企業の好業績と人手不足があいまって、売り手市場が続いています。そうした背景から学生の就活における活動量は年々減っており、エントリー数は減少しています。
たとえば2015年の本エントリー数は、内々定保有・活動継続者で28.4社、未内定者で17.5社と現在の倍ほどの企業にESを提出していました(マイナビ学生就職モニター調査[2015年卒6月の活動状況])。
ただしAIの発展など今後も社会情勢によって採用状況が変化することが想定されます。最近は売り手市場だからと安心しきらずに、ニュースなどで最新動向を把握しながらエントリー数を適切に決めることをおすすめします。
3月と4月が本エントリーのピーク
マイナビの「2025年度(2026年卒版)新卒採用・就職戦線総括」によると、ESの提出時期は3月が4.6社と最も多く、次点で2月までが3.9社となっています。18年卒ではピークが4月(5.7社)だったことを考えると、前倒し傾向が顕著になっていると言えます。
エントリーが多い場合のメリット・デメリット

エントリー数を多くする人は、「なるべく多くの企業を見てみたい」「少ないのは不安。可能性を広げたい」といった意向があるのではないでしょうか。エントリーが多い場合のメリット・デメリットを注意点とともに解説します。
メリット:視野を広く持ち経験も積める
「自分の思い込みで業界を絞り、就活に理解が深まった後で、実は違う業界の方が自分に向いていそう」。そのように後悔する就活生も少なくありません。いろいろな業界、企業の説明会に参加したり選考を受けることで、視野を広めることができます。実際に業界・企業とコミュニケーションをとるなかで、業界・企業像がより具体的になります。
また、ESの作成数や面接回数は多くなるので、経験を積み、ブラッシュアップにつなげることができます。大本命の企業の選考の前に、1社も面接を受けていない人と何十社も受けている人とでは面接の完成度が異なるのは当然ですよね。
デメリット:スケジュール管理が難しくなる
多くエントリーしすぎると、もちろんデメリットもあります。プレエントリーを何十社もおこなった人は毎日のように多くのメールが届くでしょう。志望度の高い企業からの連絡が埋もれてしまって見逃してしまうこともあるかもしれません。
ESの締め切りや面接日の調整に関しても、しっかりスケジュール管理をしなければ、ダブルブッキングや忘れてしまうこともあるでしょう。一社一社の企業研究に使える時間は少なくなってしまうので、手薄な状態で面接を受けにいくといった事態も考えられます。
注意点:エントリー前に最低限の準備をしよう
あまりに多くの企業にエントリーしてしまうと、情報収集やスケジュールの面で管理が難しくなってしまいます。エントリーの前には企業のサイトなどを読み込み、できる限りの企業研究をしておきましょう。エントリー前にチェックしてほしいのは、ES提出日などのスケジュール関連の項目です。提出日や面接日が重複するとスケジュール管理がより難しくなるので、志望度にあわせてある程度は選別するようにしましょう。
志望度が高いからといってESなどの選考書類の期限に追われて、面接対策や企業研究がおろそかになってしまうのは本末転倒です。また、スケジュール管理の方法も確立しておく必要があります。大学の講義やアルバイト、プライベートの予定も含めて一括して管理できる体制を整えておくことが望ましいでしょう。
キャリアアドバイザーコメント持田 伊織プロフィールをみる
エントリーが多すぎる人の残念な特徴は、「目的を持たずにエントリーをしている人」です。エントリーをしている周囲に焦ってむやみに応募してしまうこともありますが、エントリーしたことで満足して最終的にはスケジュール管理ができず自分を苦しめることになってしまいます。
さらに、何のために参加しているのかが分からないため、説明会などの参加後には企業が自分に合っているか振り返りをすることが難しくなり選考への意欲も低くなってきてしまうと思います。
エントリーが少ない場合のメリット・デメリット

「行きたい業界・企業がここだけ」「企業研究をみっちりしたい」などと考えてエントリー数が少ない人もいるかもしれません。一点集中突破ができればそれに越したことはありませんが、少ない場合のメリット・デメリット、注意点をおさえておきましょう。
メリット:1社に掛けられる時間が増える
一社ごとの企業研究がより深くできるようになるので、求めている人材や社風などをしっかり理解したうえESや面接対策の内容を練ることができます。多すぎる人にありがちなスケジュール管理ができないといった心配もなくなり、余裕を持ったうえでESを作成したり、面接に訪問することができるようになります。
デメリット:手持ちの駒が少ない
エントリー数が少なすぎる人で最大のデメリットは、エントリーした企業にすべて落ちてしまうリスクがあること。すべて落ちた後にエントリーし直しても、周回遅れ感は否めません。企業研究を進めたり内定をもらった後で、「やっぱり自分に合わない」「もっといろいろな企業をみておけばよかった」と後悔することもありえます。
また、面接の経験回数も少なくなるので、回数を踏んでいる人よりは面接慣れしません。過度に緊張したり回答がぎこちなくなってしまうこともありえます。
注意点:一社ごとの精度を高める
とにかく自己分析と企業研究を綿密にやることをおすすめします。「違う業界や企業がよかったかも」と後々後悔しないように、自分の仕事選びの軸や価値観を把握し、企業とマッチしていると絶対の自信を持って臨めるようになる必要があります。
全落ちを避けるために、難易度が過度に高い企業だけを受けるのはおすすめしません。いきなり大本命の選考ということを避けることも含めて、ひとつの業界に絞るにしても大企業だけでなく、比較的競争率が低い中小企業も受けましょう。
自己分析を突き詰めるにはノートへアウトプットするのもおすすめです。
関連記事
自己分析ノートの活用術を伝授! 基本の作り方から徹底解説
自己分析をするときはノートを活用すると、しっかり整理できるので就活の成功につながりますよ。 この記事では自己分析に効果的な自分史の作り方やノートの活用方法をキャリアアドバイザーが解説します。 解説動画も参考に、分析により自分の強み・弱みや適性を把握してくださいね。
記事を読む

また、仕事選びの軸はこちらの記事で明確にしておきましょう。
関連記事
仕事を選ぶ基準10選! 幅広い視野で後悔しない仕事選びの秘訣
就活で失敗しないために仕事を選ぶ基準を定めよう こんにちは。キャリアアドバイザーの北原です。 就活は活動を開始してから内定を手に入れるまでに早い人でも数カ月以上、人によっては半年以上はかかる場合もあります。「自分はこの道 […]
記事を読む

キャリアアドバイザーコメント吉田 実遊プロフィールをみる
エントリーが少なすぎる状態だとなかなか比較もできないので、面接においても説得力に欠けるところがあります。面接官の視点からすると「どういったポイントを比較して見ているのか?」「この会社しか見ていないから良いと思っているんじゃないか?」と感じてしまうこともあります。
志望度が高い企業さんに挑んでいくためには自分の目で多くの企業を見て、比較した上で、より説得力のある志望動機を語れるようにするのがいいでしょう。一方で、多ければ多いというわけでもありません! 増やしすぎて自分のキャパシティは超えないように様子を見ながら持ち駒をコントロールしていきましょう。
4つの注意点
エントリーする際におさえておきたい注意点について把握しておきましょう。就活生が失敗しがちなポイントや、疑問が生まれやすいポイントについて解説します。
①タイミングを逃さない
同じプレエントリーの期間でも早めにエントリーをすれば、企業側の印象はよくなります。「プレエントリーの時点でリクルーターから連絡が来てリクルーター面談が始まる」という可能性もあります。また、プレエントリーが早いほど企業研究の時間にあてられるメリットもあるでしょう。
プレエントリーは3月、本エントリーは3~4月がそれぞれピークとなります。その前に自己分析や業界研究など、エントリーをスムーズにできる準備を進められるようにしておきましょう。
ちなみに、リクルーター面談についてはこちらの記事で詳しく解説してあります。
関連記事
リクルーター面談は目的の把握が不可欠|異なる注意点を徹底解説
リクルーター面談は選考の一環であることが多い こんにちは。キャリアアドバイザーの北原です。 「リクルーター面談の案内が初めて来ました」「リクルーター面談って選考の一環なんでしょうか……」 このような相談をされることがあり […]
記事を読む

②効率的なES提出の準備を
エントリー数が特に多い人に当てはまりますが、ESの作成は負担の大きな活動のひとつです。手書きが大変なのは仕方ないといえますが、良質で多くのESを提出するには骨格の部分で共通の回答を用意しておくと効率的に進められます。
ESは共通の質問も多くあります。よくある質問の回答の骨格をあらかじめ用意し、文字数や尋ね方、企業の求める人材によってアレンジするという方法です。共通の質問に回答・執筆する時間が大幅に短縮されます。キャッチフレーズや「あなたを漢字一文字にするなら」といったイレギュラーの質問だけ企業ごと時間を割くことができます。
- 自分自身のことや経験
自己PR
学生時代に力を入れたこと
強み・弱み
学生時代の成功/挫折体験 - 志望動機・業界動向
◯◯業界を志望する理由
企業選びの軸・ポイント
業界の現状への意見 - 将来のキャリア
- その他
最近気になったニュース
最近読んだ本と感想
こちらの記事では、趣味と特技の書き方について紹介しています。なかなか思いつかない人に向けた見つけ方や書き方の例文を紹介しているので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
関連記事
ESで面接官の印象に残る「趣味・特技」の書き方|見つけ方も解説
ESの趣味・特技の書き方がわからない就活生は多い こんにちは。キャリアアドバイザーの北原です。ESを作成している就活生から 「趣味・特技欄に何を書いていいのかわからない」 「評価されるような内容が思いつかない」 といった […]
記事を読む

また、企業によっては手書きのESが求められることもあります。こちらの記事では手書きのエントリーシートの書き方やコツについても解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
関連記事
エントリーシートを手書きするべき企業とは? 書き方や注意点も解説
エントリーシートを手書きする際は、修正液や二重線で訂正することがないように下書きをして丁寧に作成しましょう。今回はエントリーシートを手書きで作成するメリットや、企業が手書きのエントリーシートをもとめる理由をキャリアアドバイザーが紹介します。エントリーシートを手書きするコツや注意点、作成時のチェックポイントも紹介しているので、手書きで作成する前にチェックしてくださいね。
記事を読む
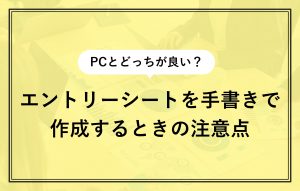
③プレエントリーは迷った場合、エントリーしよう
プレエントリーの時点で絞りすぎるのは危険と考えてもいいでしょう。プレエントリーをすることで、企業から採用情報のほか、説明会・ESの情報が提供されます。企業に関する情報を知ることで志望度が下がることは多々ありますし、その場合はESを提出しなければいいだけです。
当たり構わずプレエントリーしてスケジュール管理ができなくなるのも考え物ですが、「迷ったらプレエントリー」の方針をおすすめします。
④エントリー数にとらわれすぎない
エントリーの平均数を紹介してきましたが、こうした数はあくまで目安に過ぎません。「平均6社以上なので、是が非でも6社にエントリーしよう」などという姿勢では本来の目的からはずれてしまいます。
最終目的は、内定を獲得すること。そのことを忘れずに自分の就活の軸や志望業種などを加味し、エントリー数の多すぎる・少なすぎるメリット・デメリットを踏まえたうえで、自分にとって適切なエントリー数を目指しましょう。
キャリアアドバイザーコメント塩田 健斗プロフィールをみる
効率的にESを準備するのはとてもいいと思います。余談ですが、ごく稀に手書きの学校指定の履歴書を要求してくる企業もあるので、データの場合であれば一枚手書きで履歴書を記入し(日付と志望動機を省く)そちらをコピーして数枚用意しておくと、志望動機だけを埋めて提出することができるため便利です。
ただ、この方法はデータでのスキャンのみに活かせる方法なので注意が必要です。直接持参したり、郵送する場合はコピーしていることがわかってしまいます。
また、闇雲にエントリーするのも失敗してしまう可能性があります。理由としては、自分が行きたいと思う企業の選考情報などを見逃してしまう可能性があるからです。ナビサイトなどで登録すると、メールでたくさんの情報が送られてくるので、あらかじめメールの設定などで志望度が高い企業様からの連絡をすぐに確かめられるようにしておくと効率的に就活を進められると思います。
エントリー数などの就活方針を決める際には公務員との併願を視野に入れる人も多いのではないでしょうか。下の記事では公務員と民間企業を併願する場合の注意点を記しています。
関連記事
公務員と民間の併願で注意すべき点|スケジュールやメリットも解説
公務員と民間の併願はメリット・デメリットを理解し、自分に合った対策を練る必要があります。 この記事では就活スケジュール、併願を成功させる秘訣、対策などをキャリアアドバイザーが解説します。 事前準備が重要なので解説動画も参考に対策を講じてくださいね。
記事を読む

自分に合ったエントリー数で有利に進めよう
平均エントリー数は、必ずしも自分に合ったエントリー数とは限りません。一方で、就活市場や就活仲間の動向を知り、エントリー数を把握していくことは就活を有利に進められる情報のひとつになります。自分なりに適切なエントリー数のバランスを考えながら、賢く就活を行いましょう。

 キャリアパーク就職エージェントは、東京証券取引所グロース市場に上場しているポート株式会社(証券コード:7047)が運営しているサービスです。
キャリアパーク就職エージェントは、東京証券取引所グロース市場に上場しているポート株式会社(証券コード:7047)が運営しているサービスです。

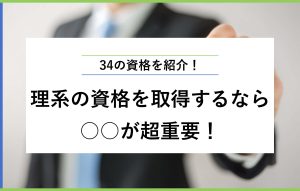










最近は売り手市場なので、10社くらい受ければどこか受かりますよね