目次
- 就活スケジュールを押さえることが就活対策の第一歩! すべきことを理解しよう
- まずはチェック! 毎年共通の一般的な就活スケジュール
- 卒業前々年の4月:就活準備開始
- 卒業前々年の6月:就活イベント開始
- 卒業前年の3月:選考のエントリー開始
- 卒業前年の6月:選考開始
- 自分の就活開始時期はいつ? 卒業する年別の就活スケジュール
- 26卒の場合
- 27卒の場合
- 実際は3月より前に始める人が多い! 知っておくべき就活スケジュールの3つの事実
- ①一部の企業は3月のエントリー前に選考を開始する
- ②3月のエントリー後はすぐ選考が本格的に進む
- ③6月以前に1つ以上は内定をもらっているケースが多い
- 就活は今後も早期化が予測される! 差を付けるカギは注力ポイントの理解
- まずはココに注力! じっくり取り組みたい5つの就活準備
- ①インターンに参加して働くイメージを持つ
- ②自己分析をして自分について深く理解する
- ③業界分析をして就きたい仕事を見つける
- ④企業研究をしてキャリアビジョンを描く
- ⑤OB・OG訪問をして選考対策に役立つ情報を得る
- エントリーまで3カ月を切ったら実践! 選考直前にやるべき3つのこと
- ①自己分析や企業研究の内容をもとにESや履歴書を作成する
- ②SPIや玉手箱などの適性検査の勉強をする
- ③本番を想定した面接の練習をする
- 自分に合うスケジュールの理解が大切! 就活を走りきるための心構え
- ①就活のゴールは「自分に合う」企業を見つけること
- ②無理に複数内定を目指す必要はない
- ③他人の就活の進み具合は自分とは関係ない
- 就活スケジュールをもとに計画的に就活を進めて着実に前に進もう
就活スケジュールを押さえることが就活対策の第一歩! すべきことを理解しよう
こんにちは、キャリアアドバイザーの北原です。就活スケジュールについて気になっている学生から、
「就活っていつから始めたらいいですか?」
「実際はスケジュールよりも早く就活が始まるって本当ですか?」
といった声が寄せられています。就活スケジュールを押さえることは、就活対策の第一歩です。周りよりスタートが遅れてしまうと内定が遠のいてしまうこともあるので、今からしっかり理解しておきましょう。
この記事では、毎年共通の一般的な就活スケジュールや26〜27卒の卒業年別スケジュールなどを紹介します。就活に向けた準備の進め方についても解説しているので、いつから何をすれば良いか迷ったときの参考にしてくださいね。
【完全無料】
大学生におすすめ!
就活準備で使いたい診断ランキング
1位:適職診断
まずはあなたが受けない方がいい職業を確認してください
2位:業界&職種マッチ度診断
興味のある業界・職種とあなたの相性を診断しましょう
3位:自己分析ツール
あなたの基本的な性格から、就活で使える強み・弱みを診断します
4位:エントリーシート作成ツール
業界特有の質問にも対応! そのまま使えるESが作れます
5位:マナー力診断
あなたのマナーは大丈夫?診断を受けて自分の苦手分野を把握しよう
【併せて活用したい!】
選考前に必ず使ってほしい厳選ツール
①自己PR作成ツール
自己PRがまとまらない人は、ツールを活用して自己PRを完成させよう
②志望動機作成ツール
5つの質問に答えるだけで、受かる志望動機を自動で作成します
まずはチェック! 毎年共通の一般的な就活スケジュール


就活生

キャリアアドバイザー
本当はいつから始めても良いのですが、選考が活発におこなわれる時期に合わせて内定を獲得するなら、早めの対策が必要です。

就活生
そうなんですね。私は早いタイミングで内定がほしいので、これから準備しようと思います。
一般的な就活スケジュールは、上記の画像の通りです。
長期インターンシップなどの就活イベントが卒業前々年の6月頃から始まるケースが多いため、インターンに参加したい人は卒業前々年の4月頃から就活に取り組む必要があります。
ここからは、毎年共通の一般的な就活スケジュールを紹介します。自分がいつから就活を始めればいいか考える際の参考にしてくださいね。
就活開始のベストタイミングについては以下の記事でも解説しているので、こちらも参考にしてみてくださいね。
関連記事
就活はいつから開始? ベストタイミングを年間スケジュールから逆算
就活が始まる時期やいつから始めるべきか気になる人もいますよね。この記事ではキャリアアドバイザーが、一般的な就活スケジュールを説明したうえで就活をいつから始めるべきかを解説します。スケジュールを立てるコツも紹介するので参考にしてみてください。
記事を読む

卒業前々年の4月:就活準備開始
就職活動の準備は、卒業する前々年の4月からスタートしましょう。学部生の場合は3年生の4月、大学院生の場合は1年生の4月です。
6月以降に始まる夏のインターンに向けて、まずは自己分析に取り組みます。自己分析で取り組んだ内容をもとに就職したいと思う業界や就きたい職種、企業の特徴などを整理してください。6月に近づいてくると夏のインターンの選考情報が出るので、自分の希望の業界や企業の選考に応募する流れになります。
この時期はまだ業界や企業を絞り込まず、むしろ広く浅くいろいろな仕事について情報収集することが大切です。就活初期の段階で多様な可能性を検討できていれば、終盤になって「こんな業界や企業もあったのか」と知って後悔するのを防ぐことができるからです。

キャリアアドバイザー
就活は多方面から情報を集めることが重要であるため、学部の友人やサークル仲間など周囲の人と一緒に始めるのがおすすめですよ。
卒業前々年の6月:就活イベント開始
卒業前々年の6月になったら、インターンや就職セミナーなどの就活イベントが始まります。インターンはすべての企業が実施するわけではなく、選考倍率が非常に高くなる企業もあります。また、必ずしもインターンに参加しなければいけないわけでもありません。
しかしインターンは内定に直結するケースもあり、参加するメリットは多いです。インターンに参加しない場合も、この期間にOB・OG訪問をしたり企業が開催している就職セミナーなどに参加したりして、就活を進めることが大切です。
この時期は、さまざまな経験を通して自分の理想の将来像を明確にすることが一番大切です。どんな生き方や働き方がしたいかをじっくり考えて、その理想をかなえられる仕事の条件を洗い出しておくと、選考エントリーが始まってから迷わず企業を選ぶことができます。

キャリアアドバイザー
この段階で希望の業界や職種が明確に決まっている場合は、就活に有利な資格の取得などをこの時期に進めておくとより内定に近づきますよ。
卒業前年の3月:選考のエントリー開始
卒業前年の3月になったら、本選考のエントリーが開始されます。エントリーがスタートしたら、まずは企業のホームページや応募用サイトの情報を見て企業説明会に参加する流れになります。その後、選考を受けたいと思ったら、選考に向けて履歴書やエントリーシート(ES)の準備を進めましょう。
この時期は、集中的に説明会に参加する時期になります。どの企業の説明会にいくか迷わないために、この時期までに自分の希望の条件に近い企業を数十社程度に絞り込んでおくことをおすすめします。同じ業界や地域の企業が共同で開催している合同説明会に参加して一度に多くの企業の説明を受けるのも効率的です。

キャリアアドバイザー
この時期からスケジュールが埋まって非常に忙しくなるため、自己分析や業界分析など3月までに進められる準備はすべて終わらせておくのが理想ですね。
卒業前年の6月:選考開始
卒業前年の6月になったら、エントリーした企業の選考を受け始めます。
- ①書類選考:ESや履歴書を提出する
- ②適性検査・筆記試験:SPIなど企業が指定した試験を受ける
- ③面接:内定まで一次面接・ニ次面接・最終面接の3回程度おこなわれる
選考開始から内定が出るまでの期間は企業の採用スケジュールによって異なりますが、1〜2カ月程度が目安です。
企業や職種などによっては、選考の過程で成果物を作成して提出するなど、面接以外の方法で適性を審査されることもあります。そのため、3月の企業説明会の時点で選考フローや選考のおおまかな内容について確認しておけると安心ですよ。

キャリアアドバイザー
卒業前々年の4月から始まり、1年数カ月の就活期間を経て早ければ卒業前年の夏ごろまでに内定があるというスケジュール感です。
キャリアアドバイザーコメント塩田 健斗プロフィールをみる
上記は一般的な就活スケジュールであり、この通りに行動することができれば順調に就活を進められますが、準備は早いに越したことはありません。就活ではやるべきことがたくさんあるため、準備が早ければ早いほど、余裕を持って就活に取り組むことができます。
まだ就活のシーズンではない大学1~2年生の場合、どのような業界や仕事があるのかといった業界研究や、自分の興味や強みを知る自己分析を通じて、卒業後の進路やキャリアについて考えておくことが重要です。書類作成や面接対策など実践的な準備は、本格的な就活が始まってからでも問題ありません。
とはいえ、まだ就活シーズン前の段階ですので、具体的な志望業界や職種などを絞り込む必要はありません。業界や職種について把握しつつ、自己分析で自分自身について理解しておくだけでも、就活開始時の大きなスタートダッシュにつながるでしょう。
まずはあなたが受けないほうがいい職業を確認しましょう
自分に合った職業・合わない職業を見つけることは、就活の成功に不可欠です。しかし、見つけることが難しいと感じる人も多いでしょう。
そんな時は「適職診断」を活用して、志望する職業と自分の相性をチェックしてみましょう。簡単な質問に答えるだけで、あなたの強みや性格が分析され、向いている職業・向いていない職業が診断できます。
自分の適職・適さない職業を今すぐチェックしてみてください。
また、業界も含めてより向いている職業を知りたい場合は「業界&職種マッチ度診断」がおすすめです。
自分の就活開始時期はいつ? 卒業する年別の就活スケジュール
ここからは、26卒(2026年3月に卒業する予定の人)と27卒(2027年3月に卒業する予定の人)の就活スケジュールをそれぞれ紹介します。
まだ時間に余裕がある場合でも、カレンダーやスケジュールに書き込むなどして、忘れないようにしましょう。就活を始めるうえでのコツや注意点なども解説するのでぜひ参考にしてくださいね。
26卒の場合
- 2024年4月:就活準備開始
- 2024年6月:就活イベント開始
- 2025年3月:選考のエントリー開始
- 2025年6月:選考開始
26卒は2025年3月から選考のエントリーが開始されます。夏や冬におこなわれたインターンや就活セミナー、自己分析などの内容をもとに、3月までに業界を3つ程度、企業を数十社程度まで絞り込んでおきましょう。また、エントリーの開始までにSPIなどの適性試験対策も進めておくと安心です。
しかし、後ほど解説しますが近年就活スケジュールの早期化が進んでいるため、上記よりも早く選考を進める企業も出てくると考えられます。そのため、万全の状態で選考開始の時期を迎えられるように早めの準備を心掛けましょう。
参考として、24卒や25卒の就活スケジュールや進み具合がどうだったのかを調べるのも有効です。

キャリアアドバイザー
自己分析や企業研究、選考対策をバランス良く並行して進めることが大切です。
26卒の就活に乗り遅れてしまったかもしれないと焦る人は、こちらの記事を参考にしてみてください。今すぐ取り組むべき対策について詳しく解説しています。
関連記事
26卒の就活がやばい4つの理由! 今日からすべき6対策で選考突破
就活をするなかで「26卒の就活はやばい」という言葉を聞き、不安になった人もいるのではないでしょうか。この記事では、26卒の就活の進め方をキャリアアドバイザーが解説します。
記事を読む

27卒の場合
- 2025年4月:就活準備開始
- 2025年6月:就活イベント開始
- 2026年3月:選考のエントリー開始
- 2026年6月:選考開始
27卒は、2025年4月から自己分析や業界研究などの就活準備をスタートしましょう。就活が本格化してくるとひとつひとつの準備に時間をかけることが難しくなるため、この時期から少しずつ準備を進めておけるとスケジュールの面でも精神的な面でもゆとりを持って就活に臨めますよ。
しかし、学業より就活を優先する必要はありません。学業の合間をぬって、空いた時間に自己分析などに取り組めば大丈夫です。
就活というと自己分析や面接対策など特別な準備を多くしなければならないイメージがあって気が重い人もいるかもしれません。その場合は就活情報のサイトや動画を見るなど、取り組みやすいことから始めてみるのもおすすめです。

キャリアアドバイザー
「将来どんなふうに暮らしていたいか」と考える良い機会だと捉えて前向きに就活に取り組みましょう。
実際は3月より前に始める人が多い! 知っておくべき就活スケジュールの3つの事実

これまで一般的な就活スケジュールについて、卒業前年の3月から選考にエントリーすると解説してきました。しかし、近年は一般的なスケジュールよりも早く採用活動を開始する企業もあり、学生も3月より前倒して選考を受ける人が多いです。
そこでここから、就活スケジュールの近年の傾向について解説します。希望の会社が早期の採用スケジュールで動く可能性もあるので、就職活動の事前知識として早期化の傾向は理解しておきましょう。
①一部の企業は3月のエントリー前に選考を開始する
就活スケジュールの近年の傾向として、一部の企業が卒業前年の3月を待たずに選考を開始するケースがあります。
株式会社リクルートの就職みらい研究所が新卒採用の実態を調査した「就職白書2024」によると、約2割の企業が卒業前年の2月以前に面接選考を始めています。
現在の新卒採用は売り手市場で、企業の求人数に対して学生が足りていない状況です。そのため、新卒採用に力を入れている企業は優秀な人材を獲得するために周囲よりも早く採用活動に取り組む傾向があります。
だからこそ、希望の業界や企業がある程度決まったら企業の採用サイトや新卒求人サイトなどで選考開始時期を早めにチェックすることをおすすめします。

キャリアアドバイザー
3月から選考が始まると思っていて対策が間に合わず本領を発揮できなかった、とならないよう早めに準備しましょう。
選考の早期化についてはこちらの記事で詳しく解説しています。対策を怠らず、志望度の高い企業の内定を狙いましょう。
関連記事
早期選考に勝ち残るには対策が必須! 受ける方法や対策を解説
早期選考はメリット・デメリット、必要な準備を理解したうえで臨むことで就活を有利に進められますよ! この記事では、早期選考のメリット・デメリット、受け方、対策などをキャリアアドバイザーが解説します。 早期選考を勝ち抜き、心に余裕のある就活にしましょう。
記事を読む

②3月のエントリー後はすぐ選考が本格的に進む
一般的なスケジュールでは卒業前年の3月にエントリーして6月から選考が始まりますが、近年の就活スケジュールでは3月のエントリー後にすぐ選考が始まる傾向があります。これも、企業が優秀な人材を早めに確保するための策です。
そのため、早期の選考をおこなっている企業にエントリーした場合、3〜6月でその企業の選考を受けつつ、ほかの企業の説明会に参加する形になり、非常に忙しい3カ月になります。
6月までの3カ月間でゆっくり選考対策をしようと考えていても、実際は時間の余裕がなく、十分な準備ができないまま面接本番を迎えるというケースも少なくありません。そのため、心配な人は卒業前年の3月までにひととおりの選考対策は済ませておくと安心ですよ。

キャリアアドバイザー
早めに対策を始めると本番までに細かい部分までブラッシュアップできるので内定獲得により近づくことができます。
③6月以前に1つ以上は内定をもらっているケースが多い
一般的な就活スケジュールでは卒業前年の6月以降に内定が出ますが、3月のエントリー後すぐに選考が始まる企業が多いため、実際には6月を待たずに内定が出ることも珍しくありません。
上記でも紹介した株式会社リクルートの就職みらい研究所が発表した「就職白書2024」によると、2024卒の6月1日時点の就職内定率は79.6%でした。約8割の学生が6月までに1つ以上の内定をもらったことがわかります。
6月以降も選考をおこなっている企業は多くあるため必要以上に焦る必要はありませんが、例年の傾向として「6月までに内定1つ」を目安として就活スケジュールを考えておくと気持ちの余裕が持てますよ。

キャリアアドバイザー
「早く内定が決まるほど良い」というわけではないので、あくまで全体の傾向として頭に入れておきましょう。

キャリアアドバイザーコメント堀内 康太郎プロフィールをみる
ここ数年、上記のような就活の早期化は全体の傾向として強まっています。特に知名度や人気で劣る中小企業やベンチャー企業では、大手企業より先に優秀な人材を確保するため、早期選考や選考直結型のインターンをおこなう傾向にあります。
ただ、だからといってすべての企業が早期化に当てはまるわけではありません。人気のある大手企業を中心に、一般的な就活スケジュールに沿って選考を進める企業もたくさんあるため、必ずしも早期化に合わせた準備をする必要はないのです。
「周りが早期化に合わせて準備しているから自分も準備しなくちゃ」と焦る気持ちもわかりますが、周りに合わせる必要はありません。自分の希望業界や企業について個別に選考スケジュールを調べ、そのスケジュールに合わせて準備を進めることが重要です。
なお、各企業の選考スケジュールを把握するには、公式サイトで調べるほか、インターンに参加したり、面談などで担当者から直接聞く方法もあります。インターンに参加できなった場合は、就活サイトや口コミサイトで過去の選考情報を調べるのもおすすめですよ。
就活は今後も早期化が予測される! 差を付けるカギは注力ポイントの理解

就活の開始時期は今後さらに早くなると予想されています。そうなると就活準備に取り組む時間が少なくなりますよね。一つひとつの準備が十分にできないまま就活をスタートしなければならなくなる可能性が高いです。
そのため、限られた時間のなかで効率的に対策をする必要があります。効率を上げるうえで大切なのは「注力ポイント」の理解です。希望の会社から内定をもらうというゴールに向けて、どの工程に集中的に時間や労力を割くべきか考えることで、周囲よりも効率的に就活を進められるようになりますよ。
こちらの記事では就活を長期化させないためのポイントを解説しているので参考にしてみてくださいね。
関連記事
就活がいつまで続くかは4パターンで判断! 4対策で長期化を阻止
就活はいつまで続くのか、いつ頃終えることができるのか不安になることもありますよね。この記事では、就活を始めた時期別の就活スケジュールや就活を長期化させないコツについて、キャリアアドバイザーが解説します。
記事を読む

まずはココに注力! じっくり取り組みたい5つの就活準備

就職してから後悔しないためには、就活準備の段階で「自分自身を理解すること」と「社会を理解すること」の両方が大切です。この2つがそろわないと、自分の能力や希望に合わない仕事を選んでしまったり、情報不足によって就職先の選択肢が狭くなったりする可能性があります。
ここからは、限られた時間のなかで効率的に対策するために注力すべきポイントを5つ紹介します。就活の進め方を考える際に活用してくださいね。
①インターンに参加して働くイメージを持つ
就活で注力すべきことの1つ目は、インターンに参加して働くイメージを持つことです。インターンでは、職場の様子が見学できたり実際の業務の一部を任せてもらえたりするため、社会に出て働くイメージを持ちやすくなりますよ。
クリアなイメージが持てれば、自己分析や企業研究などほかの就活準備をする際により具体的に自分のキャリアや理想の職場を考えることができ、自分に合う企業を選びやすくなります。
インターンは、短期間で体験できるものから数週間以上かかるものまで、さまざまな期間のプログラムがあります。会社で働くイメージをつかむためには、長期間参加できるプログラムがより効果的ですよ。

キャリアアドバイザー
インターンに関する情報は各企業の採用サイトや新卒向けの採用情報サイトなどに掲載されているのでチェックしてみましょう。
②自己分析をして自分について深く理解する
就活で注力すべきことの2つ目は、自己分析をして自分について深く理解することです。
就活を効率的に進めるためには、仕事を選ぶ「自分なりの就活軸」を見つける必要があります。軸がはっきりしていれば、それに合致する企業だけに集中して選考対策ができますよね。自己分析は就活軸を明確にするための作業になります。
自己分析にはさまざまな方法があるため、取り組みやすいものや興味を持ったものから取り組んでみましょう。
- Webや書籍に掲載されている自己分析ツールを活用する
- モチベーショングラフを書いて上下している部分について振り返る
- 生まれてから現在までの自分史をまとめる
- マインドマップを作って思考を整理する
- 心理学モデル「ジョハリの窓」で他者から見た自分を理解する
インターンに参加したり将来についてじっくり考えたりする過程で、自分の希望や価値観も変化することがあります。そのため、自己分析は一度ではなく就活を進めるなかで定期的に取り組みましょう。

キャリアアドバイザー
自己分析は一人で取り組むと行き詰まりやすいので友人などと複数人で取り組むのがおすすめです。
質の高い自己分析をおこなうことは選考突破の第一歩になります。こちらの記事では自己分析の質を上げる4つの方法を解説しているので、確認してみましょう。
関連記事
就活スケジュールは実際と違うことも! 早期の計画と選考対策が重要
早期かしていると言われている就活スケジュール。この記事では実際いつから対策を進めたら良いのかなど卒年に合わせて解説しています。キャリアアドバイザーからのアドバイスや対策のコツなども併せて確認してみてくださいね。
記事を読む

③業界分析をして就きたい仕事を見つける
就活で注力すべきことの3つ目は、業界分析をして就きたい仕事を見つけることです。業界によってビジネスモデルや業務の流れ、給与水準、キャリアの積み上げ方などが左右されるため、就活の早めの段階でどの業界に進みたいかを検討しておけると希望の就職先を見つけやすくなりますよ。
また、業界分析をすれば「この業界は成長産業だからコツコツ技術を磨けば将来的に大きな活躍ができそう」など仕事の将来性についても考えやすくなるため、長い目で自分のキャリアを検討する良い機会になります。
- 業界団体のサイトをチェックする
- 業界ごとの特色をまとめた書籍や就活情報サイトで勉強する
- 業界別の企業説明会に参加する
志望業界は、企業の本選考にエントリーする時点(一般的な選考スケジュールで卒業前年の3月)で3つ程度に絞れていれば大丈夫です。そのため、その時点までに数ある業界のなかから自分が進みたい業界を選べるように分析を進めましょう。

キャリアアドバイザー
自分の進みたい分野が今の時点ではっきりしていて就活の軸になっている場合は、無理にほかの業界まで視野に入れる必要はありません。
業界分析はノートを使っておこなうのもおすすめです。以下の記事では業界研究ノートの作り方を解説しているので、参考にしてみてください。
関連記事
周りと差がつく業界研究ノートの作り方|状況別の活用法まで解説
業界研究ノートは就活成功に近づくツールです!今回は周りと差をつける業界研究ノートの作り方を紹介していきます。キャリアアドバイザー監修のもと、業界研究ノートに書くべき7つの項目や業界研究ノートの例も紹介しているので、業界研究ノート作成の参考にしてください。
記事を読む

④企業研究をしてキャリアビジョンを描く
就活で注力すべきことの4つ目は、企業研究をして就職後の自分のキャリアビジョンを描くことです。自己分析や業界分析の内容をもとに企業をピックアップして、個々の企業に対する理解を深めましょう。
一つひとつの企業について掘り下げて調べることで、仮に入社した場合にどんなキャリアを歩めるのか想像でき、自分の希望とどれくらい合致しているか判断しやすくなりますよ。
- 会社概要(設立年・売上高・従業員数・取引先など)
- 事業内容(商品・サービスの独自性や注力分野など)
- 職場環境(離職率・有給消化率・平均残業時間など)
- 会社の雰囲気(風通しの良さ、社員の性格など)
企業研究は、インターネットや書籍に公開されている情報だけでは不十分なこともあります。特に、会社の雰囲気は実際に会社の人と話す機会がないとわからないですよね。そのためインターンに参加したり次で紹介するOB・OG訪問をしたりして、実際に自分で体験して情報を集めることも大切です。

キャリアアドバイザー
企業研究を進めれば自分のどのような強みをアピールすれば良いか検討をつけやすくもなりますよ。
企業研究のコツはこちらの記事で解説しているので、併せて確認してみましょう。
関連記事
就活の企業研究を効果的にする4ステップ! 見本つきで実施法を解説
就活では企業研究により自分に合う企業を見つけ、説得力のある志望動機を作成することで内定に近づきます。この記事では企業研究の目的、おすすめの方法、注意点などをキャリアアドバイザーが解説します。 具体的な活用方法も紹介するので、ポイントを絞ったアピールで周囲と差をつけましょう!
記事を読む
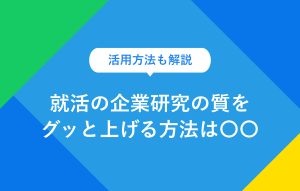
⑤OB・OG訪問をして選考対策に役立つ情報を得る
就活で注力すべきことの5つ目は、OB・OG訪問をして選考対策に役立つ情報を得ることです。志望業界や職種がある程度絞れてきたら、自分の希望の会社や理想に近い仕事をしている先輩社会人に話を聞いてみましょう。
実際にどのような立ち回りで仕事をするのか、どんな方法で仕事を進めるのかなど、就職後のイメージが具体的になり、応募書類や面接で伝えるべき内容なども検討しやすくなります。
- 大学のキャリアセンター経由で紹介してもらう
- 大学のサークルや部活動のつながりを探す
- OB・OG訪問専用サービスを活用する
- 企業の人事部に問い合わせる
訪問の機会を得ることができたら、業務内容や1日のスケジュールなど自分が聞きたい内容を事前に整理し、失礼のないよう準備万端の状態で臨みましょう。

キャリアアドバイザー
OB・OG訪問をすること自体が、志望度の高さを企業に示す材料にもなりますよ。
OB・OG訪問についてはこちらの記事で詳しく解説しているので、参考にしてみてくださいね。
関連記事
OB・OG訪問の質問リスト一覧|質問力アップの秘訣やNG例も解説
OB・OG訪問は質問を準備しておくことで、充実した時間になります。 この記事ではOB・OG訪問の目的、充実させるコツ、質問すべきこと、よくある質問などをキャリアアドバイザーが解説します。 OB・OG訪問で得たリアルな情報は企業選びや選考対策に役立ちますよ!
記事を読む

キャリアアドバイザーコメント高橋 宙プロフィールをみる
仕事は、実際に業務を経験してみないとわからない部分があるのも事実です。また、自分自身で調べないと向き不向きや興味が判断できない部分もあるため、「人気だから」「人から勧められたから」で業界や職種を絞り込むのはおすすめしません。
インターンやOB・OG訪問などの「行動」、業界研究や企業研究といった「調査」、そして自分自身の理解を深める「自己分析」を繰り返しながら、自分の希望や興味について少しずつ絞っていきましょう。
就活準備はいずれも地道な努力が必要となるため、途中でモチベーションが下がってしまう可能性も十分に考えられますが、あきらめずに取り組むことができれば、本当に自分に合った企業に出会える確率も格段に高まるため、粘り強く続けることが大切ですよ。
あなたが受けないほうがいい職業は?
3分でできる適職診断で確認してみよう
入社後の早期離職を避けるためには、自分に適性のある職業を選ぶことが大切です。しかし、それがどんな職業なのかが分からず悩む人も多いでしょう。
そんな人におすすめなのが「適職診断」です。40の質問に答えるだけで適性のある職業や受けないほうがいい職業を診断できます。
自分に適性のある職業を早めに知って、就活を成功させましょう。
エントリーまで3カ月を切ったら実践! 選考直前にやるべき3つのこと

これまで、就活開始に向けてじっくり時間をかけて取り組みたい対策を5つ解説しました。ここからは、本選考のエントリーまで3カ月を切った後の対策について解説します。
エントリーまで3カ月を切ったら、応募書類の作成や面接練習など、選考直前の対策に取り組むべきタイミングです。これから解説する3つの対策を計画的に実施して、スムーズな内定獲得を目指しましょう。
①自己分析や企業研究の内容をもとにESや履歴書を作成する
1つ目にやるべきことは、ESや履歴書の作成です。過去に取り組んだ自己分析や業界分析、企業研究などの内容をもとに、内容を作成しましょう。
- 基本情報(氏名・住所など)
- 学歴・職歴
- 自己PR
- 志望動機
- 学生時代に打ち込んだこと
ESや履歴書で最も力を入れるべきなのは、志望動機です。企業は志望動機の内容から、自社とどれくらいマッチしているか、志望度がどれくらい高いかなどを判断します。企業研究の内容を振り返り、自分が将来進みたい方向と会社の方向性が同じであることが伝わるように記載しましょう。

キャリアアドバイザー
最初の選考はESなどの書類選考であることが多いため、面接選考に進むために応募書類は丁寧に作成しましょう。
ESと志望動機の違いや効果的な使い分け方について知りたい人は、こちらの記事も併せて確認しましょう。
関連記事
エントリーシートと履歴書5つの違い|企業のチェックポイントも解説
エントリーシートと履歴書の違いは企業側の目的や学生側の目的にあります。今回はエントリーシートと履歴書の7つの違いを紹介していきます。また、それぞれを記入する際のポイントや注意点もキャリアアドバイザーが解説しているので、参考にしてみてください。
記事を読む

②SPIや玉手箱などの適性検査の勉強をする
2つ目にやるべきことは、SPIや玉手箱などの適性検査の勉強をすることです。適性検査は学生の強みが企業で活かせるかを確認したり、既存社員とのマッチ具合を図るためにおこなわれます。人気企業では応募者を絞り込むためにおこなわれることもあります。
適性検査の中でも能力検査については、試験の結果が良くなければ次の選考に進めない可能性が高くなってしまいます。試験本番で本来の力を発揮できるように、選考の3カ月前くらいから準備を始めましょう。
- 言語分野
- 非言語分野
- 構造的把握力
- 英語力
適性検査は問題に慣れておくことが成功の一番のカギであるため、自分にとって説明がわかりやすい問題集や対策本を一冊選んで徹底的にやり込むことをおすすめします。

キャリアアドバイザー
性格検査では特別な準備は必要ありません。ありのままの回答をしたほうが企業との適性がわかりやすくなります。
SPIの対策を具体的にどのように始めたら良いのかわからない人はこちらの記事で確認しましょう。
関連記事
SPI対策はいつから? 本番より3カ月前以上前に始めるのがベスト
選考の中でよく実施されるSPI。実際いつから対策を始めたら良いのかわからない人に向けてキャリアアドバイザーの解説を交えながら、対策スケジュールや対策法について解説します。
記事を読む

③本番を想定した面接の練習をする
3つ目にやるべきことは、本番を想定した面接練習をすることです。面接では、限られた時間内で自分の志望度の高さや企業との適性をわかりやすく伝えなければなりません。本番を想定した練習を何度もすることで、自分が言いたいことをスラスラと説明できるようになりますよ。
- 志望動機を教えてください
- ◯分で自己PRをしてください
- 学生時代に打ち込んだことは何ですか?
- 入社後にどんな仕事をしたいですか?
- 弊社が第一志望ですか?
- 最近のニュースで気になったことを教えてください
- 自分を動物に例えると何だと思いますか?
面接の回答を考えるうえで大切なのは、話の構成です。聞かれた質問に対して、まず端的に結論を伝えるようにしましょう。その後で結論に至った背景や具体的なエピソードなどを続けることで、自分の意見の趣旨を面接官に構造的に理解してもらいやすくなりますよ。

キャリアアドバイザー
話をわかりやすく伝える力は、社会人になってからも非常に大切です。就活の段階から意識的に伝え方を工夫するようにしましょう。
面接でよく聞かれる質問への答え方についてはこちらの記事で解説しているので、対策に活用してみてくださいね。
関連記事
【例文付き】面接で必ず聞かれる6つの質問リスト|回答のコツも紹介
面接でよく聞かれる質問はおもに6つあると言われています。面接で何を聞かれるかは業界・企業によって異なりますが、どの企業でも聞かれる可能性の高い「頻出質問」については、事前に回答を準備しておきましょう。この記事では、面接で聞かれやすい6つの質問と回答例をキャリアアドバイザーが解説していきます。ぜひチェックしてみてください。
記事を読む
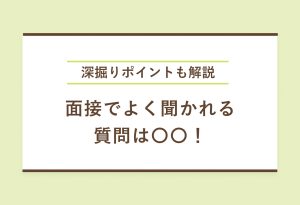
キャリアアドバイザーコメント吉川 智也プロフィールをみる
就活では業界や企業によって選考内容に多少の違いはありますが、書類選考や筆記試験、面接などについては、ほぼすべての企業が実施しています。そして、筆記試験や面接などを突破するには、「慣れ」が大切です。
「慣れ」を身に付けるためには、量をこなすしかありません。厳しいようですが、ただ参考書を読むだけの筆記試験対策や、想定問答を暗記し、面接マナーなどノウハウを覚えるだけの面接対策では、「慣れ」を身に付けることはできないのです。
筆記試験であれば大学や専門業者がおこなう模擬試験を受ける、面接対策であれば大学キャリアセンターなどを活用した模擬面接のほか、多くの企業の面接で本番経験を積むなど、常に実践を意識し、自分自身を慣れさせる工夫をしておきましょう。
自分に合うスケジュールの理解が大切! 就活を走りきるための心構え

大学に入る目的が人それぞれ違うように、社会に出て働く目的も人によって違います。そのため、周囲に流されず自分のペースで就活を進め、自分の考え方に従って行動することが重要ですよ。
ここからは、最後まで自分らしく就活を進めるために必要な3つの心構えを解説します。心から入社したい、働きたいと思える企業を探すうえで大切な考え方になるため、ぜひ覚えておいてくださいね。
①就活のゴールは「自分に合う」企業を見つけること
まず、就活のゴールは内定獲得や有名企業への就職ではなく「自分に合う」企業を見つけることです。これを忘れないようにしましょう。
- 自分が目指すキャリアや人生の方向性と企業の業務がつながっている
- 自分の価値観や性格が企業の考え方や社員の雰囲気とマッチしている
- 給与や年間休日数など、自分の生活が成り立つ労働条件で働ける
就活では、不安や焦りから「どんな会社でもいいから早く内定をもらいたい」と考えて、とにかくたくさん選考を受ける学生がいます。また、知名度がある企業や高収入の企業など、多くの学生が憧れる企業に入りたいと考える人も少なくありません。
しかし、そのような気持ちで企業を選んで内定をもらったとしても、自分が目指すキャリアや人生の方向性と違う会社であれば、入社してから「こんなはずじゃなかった」「もっと考えて就職活動をすれば良かった」という後悔につながってしまいます。

キャリアアドバイザー
実際、新卒で入社した学生の約3割は3年以内に退職しています。入社1年未満で辞める人も珍しくはありません。
②無理に複数内定を目指す必要はない
就活では、一社から内定をもらうのも決して簡単ではないため「複数の企業から内定をもらう人がすごい」と捉えられるケースがあります。その雰囲気に焦りや羨ましさを感じて「自分ももっと内定を持っておいた方が良いのかな?」と考える学生も少なくありません。
複数の内定があれば、内定承諾の時期まで吟味してより自分が入りたい企業を選ぶことができますよね。その意味で、複数内定を狙うのは就活の一つの戦略です。
しかし、いくつも内定を持っていても自分が目指す方向性と違う会社であれば、就活のゴールは達成できないですよね。また、内定が何個あっても最終的に入社できるのは一社であるため、自分の理想に近づける会社から内定がもらえたら無理にほかの企業から内定をもらおうとする必要はありません。

キャリアアドバイザー
複数内定はあくまで就活の戦略の一つです。自分の就活の目的に合わせて判断することが何より大切です。
③他人の就活の進み具合は自分とは関係ない
就活を始めると、ほかの学生と情報交換をする過程で、自分よりも順調に就職活動が進んでいる人の話を見聞きすることがあります。
そのときに、「自分は就職や仕事に向いていないのかも」「周りよりも能力が低いのかもしれない」と考えて自信を失う学生はとても多いです。就活そのものに対するモチベーションが下がって、選考を受けるのをうやめてしまう人もいます。
しかし、就活のゴールは先ほど解説したように「自分に合う企業」に出会うことです。誰よりも早く内定をもらうことや多くの企業から内定をもらうことではありません。周囲と比べて落ち込んでも「自分は自分」と気持ちを切り替えて諦めずに就活を続けることが大切です。

キャリアアドバイザー
じっくり選考を進めるなかで自分の考えを整理し直し、本当に納得して入社できる企業に出会えることもありますよ。
就活スケジュールをもとに計画的に就活を進めて着実に前に進もう
この記事では、一般的な就活スケジュールや近年の早期化の傾向、就活準備の進め方などを解説しました。就活は今後の社会人としての人生を大きく左右するため、月単位、年単位で計画的に準備を進めましょう。
早めに準備に取り組むことで、周囲に流されず、気持ちにも余裕をもって就活に臨むことができます。しっかり就活に取り組んで「早く働きたい」と思える企業や仕事を見つけてくださいね。

 キャリアパーク就職エージェントは、東京証券取引所グロース市場に上場しているポート株式会社(証券コード:7047)が運営しているサービスです。
キャリアパーク就職エージェントは、東京証券取引所グロース市場に上場しているポート株式会社(証券コード:7047)が運営しているサービスです。












就活って4年生から始めればいいわけじゃないのですね……。