目次
- 「就活ができない」から脱却するには原因と対処法を知ることが大事!
- 大前提! 就活ができないと感じるのはあなただけじゃない
- 対処法も解説! 「就活ができない」と感じてしまう9つの要因
- ①すべきことがわからず動けないため就活ができない
- ②そもそも面倒に感じていて就活ができない
- ③働くことに疑問を感じ就活ができない
- ④自分に自信がなく勇気が持てないため就活ができない
- ⑤「不合格=人格否定」のような気がして就活ができない
- ⑥学業やサークルが忙しく就活ができない
- ⑦必要なお金が足りずに就活ができない
- ⑧志望企業が採用活動をおこなっておらず就活ができない
- ⑨ケガや病気が原因で就活ができない
- なぜ対処が必要? 「就活ができない」状況が続いたときの3つの影響
- ①好条件の求人を逃す可能性がある
- ②在学中に就活を終えられない可能性が高まる
- ③ますます精神的につらくなる可能性がある
- まずは原因解明から! 就活ができない原因を明らかにする3ステップ
- ステップ①現在における就活の進捗を確かめる
- ステップ②どこでつまづいているのか明確にする
- ステップ③なぜ手が止まっているのかを考える
- どうしても動き出せないときに少しでも前に進むための3つの方法
- ①1日30分でも就活にかかわることに取り組む
- ②就活のゴールを定めていつまでに何をすべきかを逆算する
- ③将来のなりたい自分像を想像する
- どうしても就活ができない…そんな人への4つの選択肢
- 就活ができない原因と対処法応を理解して自分のペースで就活を進めよう
「就活ができない」から脱却するには原因と対処法を知ることが大事!
こんにちは。キャリアアドバイザーの北原です。就活に関して悩んでいる人から、
「モチベーションが上がらず、就活ができません」
「忙しくて就活ができないんです」
といった声を聞くことがあります。無意識的に周囲と比較して焦りを感じてしまったり、疲労が溜まっていたりすると、なかなかやる気にはなれないですよね。
この記事では、就活ができない原因と向き合う方法を解説します。原因と向き合い、理解したうえで「就活ができる」状態になるためのステップを進めていきましょう。
【完全無料】
大学生におすすめ!
就活準備で使いたい診断ランキング
1位:適職診断
まずはあなたが受けない方がいい職業を確認してください
2位:業界&職種マッチ度診断
興味のある業界・職種とあなたの相性を診断しましょう
3位:自己分析ツール
あなたの基本的な性格から、就活で使える強み・弱みを診断します
4位:エントリーシート作成ツール
業界特有の質問にも対応! そのまま使えるESが作れます
5位:マナー力診断
あなたのマナーは大丈夫?診断を受けて自分の苦手分野を把握しよう
【併せて活用したい!】
選考前に必ず使ってほしい厳選ツール
①自己PR作成ツール
自己PRがまとまらない人は、ツールを活用して自己PRを完成させよう
②志望動機作成ツール
5つの質問に答えるだけで、受かる志望動機を自動で作成します
大前提! 就活ができないと感じるのはあなただけじゃない
さまざまな事情があって就活ができていないせいで、焦りばかりが募り、結果精神的につらくなってしまうこともあるかもしれません。
そこでまず理解してほしいのは、就活ができないと感じているのは、決してあなただけではないということです。
「自分だけダメなんだ」と責めてしまうようなことがあれば、それはただ自分を追い詰めてしまうだけで、さらにモチベーションが下がることになってしまいます。
多くの人が就活ができないと悩み、そしてその悩みに向き合い、悪循環を脱して就活を成功させてきました。自分もそれができるんだと信じることが、悩みを解消する最初の一歩になりますよ。

キャリアアドバイザー
まずはあなたが受けないほうがいい職業を確認しましょう
自分に合った職業・合わない職業を見つけることは、就活の成功に不可欠です。しかし、見つけることが難しいと感じる人も多いでしょう。
そんな時は「適職診断」を活用して、志望する職業と自分の相性をチェックしてみましょう。簡単な質問に答えるだけで、あなたの強みや性格が分析され、向いている職業・向いていない職業が診断できます。
自分の適職・適さない職業を今すぐチェックしてみてください。
また、業界も含めてより向いている職業を知りたい場合は「業界&職種マッチ度診断」がおすすめです。
対処法も解説! 「就活ができない」と感じてしまう9つの要因

就活生
何をすればいいのかわからないし、やる気もないしで就活がまだできていません……。

キャリアアドバイザー
動き出せないときは、「なぜできないのか」と原因を掘り下げて対策を知ることが大切ですよ。
就活ができない状況に悩んでいたとしても、その根本の原因は案外自分では理解しづらいものです。
その結果、「できない」という状況の放置につながっている人もいるのではないでしょうか。
まずはよくある要因を9つ挙げるため、その中から自分に近しい状況のものを探してみてください。その対処法も併せて解説するため、「できない」状況から脱却する手掛かりにしましょう。
①すべきことがわからず動けないため就活ができない
「就活ができない」という気持ちの裏には、「すべきことがわからないから不安」という思いがあるケースも多いです。
自己分析や企業分析、面接対策など、いろいろな用語は聞いたことがあっても、それがどのような内容なのかはいまいちピンとこないことが原因で、手が止まっている人は実は多くいます。
そのようなときに「誰に頼れば良いのか」「次に進むにはどのようなステップを踏めばよいのか」がわからずに、「就活ができない」という結論に至ってしまいがちなのです。

キャリアアドバイザー
多くの人とって就活は初めての経験だからこそ、何をすべきかわからなくなるケースが多いんですよ。
「就活がわからない」という思いは就活初心者が抱きがちです。この記事から、就活に対する解像度を高めましょう。
関連記事
わからないだらけの就活を脱却! やるべき対策を時期ごとに解説
就活はやるべきことが多く何からすればいいのかわからない人は、優先順位をつけて取り組めば必ず結果は付いてきますよ! この記事では時期ごとに就活でやるべきことをキャリアアドバイザーが解説します。 何がわからないかを明確にしてゴールまでの算段を立てましょう!
記事を読む

対処法:専門家や経験者に就活の進め方を聞く
就活の進め方に迷ったときは、キャリアアドバイザーなどの専門家に頼るのが一番です。また、就活をすでに経験した先輩に話を聞いてみるのも良いでしょう。
- 「就活ですべきことがわからないのですが、まず初めになにをしたら良いのでしょうか」
- 「自己分析がよくわかっていないのですが、どのような方法がありますか」
- 「企業研究って、どのようにすれば良いのですか」
このように、「わからない」ということを正直に伝えてみてください。キャリアアドバイザーなら多くの学生を見て得た知見を、経験者なら自分の経験を通しての学びを共有してくれるでしょう。
②そもそも面倒に感じていて就活ができない
就活では、自己分析や企業分析、面接練習や実際の選考など、やるべきことがたくさんあります。
そうしたタスクに取り組もうとするなかで、「やりたくない」「面倒くさい」と感じることもありますよね。
実際に、そのような気持ちから就活に対して重い腰が上がらず、「就活ができない」と悩む人も少なくありません。

キャリアアドバイザー
どうしても面倒なイメージが付いているからこそ、就活を後回しにしたくなる気持ちもよくわかります。
就活が面倒に思ってしまう人は、この記事も見てみてください。
関連記事
就活が面倒でやる気が出ない人必見! 効率化の方法や便利サービスを紹介
就活が面倒に感じるときは適切な対応で解決を目指しましょう。就活が面倒に感じるのは準備でやることが多すぎたり、行動や過程に正解がないためです。今回は就活から面倒を取り除く方法や効率化する方法を紹介していきます。キャリアアドバイザーがおすすめする、就活を効率化するサービスも紹介しているので、チェックしてみてください。
記事を読む

対処法:就活にいま力を注ぐメリットにフォーカスする
今就活に着手することで、どのような準備ができるのかを考えてみましょう。早めに動き出すことで、自己分析や企業分析に時間を割くことができたり、好条件の求人と出会いやすくなるかもしれません。
早めの動き出しは、将来の選択肢を広げることにもつながるため、できるだけ先延ばしにしないのがポイントです。

キャリアアドバイザー
早めに動き出せることで、心にも余裕が出やすくなりますよ。
③働くことに疑問を感じ就活ができない
「そもそも大学を卒業したら働かないといけないのか」「働かないと生きていけないわけではない」というように、働くこと自体に疑問を感じている人もいますよね。
「この企業でこういうことを成し遂げたい」「将来的にはこのような立場に就きたい」という明確なビジョンがないと、働く意義をなかなか見い出せないものです。

キャリアアドバイザー
これまでの学生気分からいきなり社会人モードに切り替えるのも、気持ちが追い付かないですよね。
働くことに疑問があるゆえに、就活を「くだらない」と思う人もいるでしょう。そのような人はこの記事も参考にしてください。
関連記事
「就活がくだらない」から脱却! 前向きに捉える5つの方法
就活がくだらないと感じてしまったときは、その理由を知ることで前向きに捉えましょう。今回は就活がくだらないと感じてしまう人の特徴や理由3つを紹介します。またそこから脱却する方法もキャリアアドバイザーが紹介しているので、就活をくだらないと感じてしまう人はチェックしてみてください。
記事を読む

対処法:自分史を作成して将来の見通しを立てる
働くことに疑問を感じてしまうのは、「将来自分が何をしたいか」「どのような人間になっていたいか」に対して明確な答えを持てていないからではないでしょうか。
そのため、まずは自分の将来について見通しを立てることが大切なのです。はじめの一歩として「自分史」を作成してみることをおすすめします。
- 生まれてから現在までに印象に残っている出来事や、そのときに感じたことなどを振り返り、自分にとって大切な考えや価値観を洗い出していく自己分析法
自分の過去を振り返ると、今後も大切にしていきたい考え方や、興味があることの一貫性が見えてきます。そこから、「将来どうありたいか」に対する考えを深めていきましょう。

キャリアアドバイザー
過去を振り返ることも自分をより深く知る手段になりますよ。
自分史の作成方法は、この記事が参考になりますよ。
関連記事
自分史の書き方3ステップ|記入例や就活に役立つ自己分析方法を解説
自分史を作成することは、就職活動を効率的に進めるのに役立ちます。 この記事では、自分史の作成方法と自己分析の仕方をキャリアアドバイザーが解説します。 自分史を活かせる質問例や回答例も紹介しているので、自己分析の際の参考にしてみてくださいね。
記事を読む
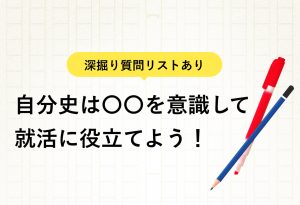
④自分に自信がなく勇気が持てないため就活ができない
就活は、いかにその企業に自分がふさわしいかをアピールする場です。しかし、自分に自信を持つのはなかなか難しいですよね。
「どうせ落ちてしまうのだろう」「自分の経験は通用しないのではないか」と、どうしても就活に対しプレッシャーを感じてしまい、一歩を踏み出せないこともあるのではないでしょうか。

キャリアアドバイザー
とはいえ、具体的な成果が無くても、十分に自分をアピールすることは可能ですよ。
「自己PRやガクチカが無い」という人は、これらの記事から自分だけのアピールポイントを見つけましょう。
自己PRすることがない学生必見! テーマの見つけ方と書き方を伝授
学生時代頑張ったことがない…見つける3つの方法と面接での答え方
対処法:小さな目標を積み上げるスモールステップを意識する
就活をやり遂げる自信を持つための方法として、日々のなかで小さな目標を立て、それを着実に達成していくようにしましょう。
小さなことでも良いので目標を達成できれば、「達成できた」という結果から自信を得ることができます。
また、目標達成の過程において「このタスクをおこなうのに〇分短縮できた」「昨日よりも〇人多くの顧客に商品を売った」というように、目に見える成果も把握しやすくなるはずです。

キャリアアドバイザー
小さな目標を着実にこなせると「目標達成力」もアピールできそうですね。
ここでコツコツと積み上げができると、「行動力」が強みとして話せるようになるかもしれません。この記事から、行動力のアピール方法について学んでみましょう。
関連記事
自己PR「行動力」の差がつく伝え方|企業が評価する回答例文も紹介
行動力は自己PRのベストな伝え方を、例文と合わせてキャリアアドバイザーが解説します。ポイントは「具体的なエピソード」と「入社後どのように貢献したいか」。NG例も添削付きで紹介します。
記事を読む
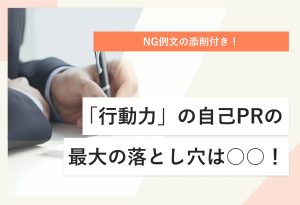
⑤「不合格=人格否定」のような気がして就活ができない
就活を続けていくと、なかなか内定が出ずに、気分が落ちこんでしまう人もいますよね。
一社や二社から選考に落とされたならまだしも、何度も連続して落ち続けると精神的につらくなることもあるでしょう。
「自分の能力は社会で活かせない」「自分は求められていない」とネガティブな思考になっていき、就活ができなくなるケースも実は多いのです。

キャリアアドバイザー
いくら自分に自信を持てていても、選考に落ち続けてしまうと気分が滅入りますよね。
対処法:「合わない会社で働かずに済んだ」と切り替える
まず押さえておいてほしいのは、「選考に落ちた=人格を否定している」というわけではないということです。
選考の機会は、「企業と学生のマッチングの場」であり、落ちたとしても相性の問題なのであなたの人格を否定しているわけではありません。
そのため、選考に落ちてしまった場合は「この企業と自分は合わなかったんだな」と、気持ちを切り替えていくことが大切です。

キャリアアドバイザー
選考を受けるうちに、あなたの個性や強みが活かせる企業にきっと出会えるはずです。
内定がもらえずに、落ち込んでしまうこともありますよね。そのようなときは、この記事から内定のためのヒントを得てみてください。
関連記事
内定がもらえない人の特徴23選|原因別に今するべきことを徹底解説
内定がもらえない人は、就活を振り返って新たなアプローチを取ることをおすすめします。 この記事では内定がもらえない人のための23のチェックリストと対策をキャリアアドバイザーが解説します。 動画も参考にして、現状を検証し一歩を踏み出してくださいね。
記事を読む

⑥学業やサークルが忙しく就活ができない
多くの学生は、大学3年生までに卒業に必須の単位は取り終えており、就活が本格化する4年生の前半は「就活に専念できる」状態のはずです。また、部活やサークル活動も3年生の秋頃には引退している人が多いでしょう。
しかし、なかには卒業に必要な単位が足りていなかったり、サークル活動を継続しているせいで就活まで手が届かなかったりする人もいるのではないでしょうか。
そのため、なかなか就活だけに時間を割けず、両立が難しくなってしまうケースもあるのです。

キャリアアドバイザー
学業やサークル活動も大学生ならではのことであるがゆえに、就活との両立が難しくなりがちです。
対処法:先にゴールを決めて必要な対応を月別で整理する
学業やサークルが忙しく、就活と両立できないと感じてしまうのは、「それぞれに対するゴールが決まっていない」ということが原因の一つと言えます。
「いつまでにこれを終える」という目標が決まっていないからこそ、ズルズルと終わりの時期を引き延ばしてしまいがちになるのです。
- 「4年の上半期のうちには単位を取り終える」
- 「4年の9月までには就活を終える」
- 「4年の夏休みにはアルバイトを再開する」
ゴールを決めてから「4年の5月には自己分析を終える」「7月には選考への応募を開始して、面接を受ける」というように、月ごとにすべきことを整理できると、計画的に物事を進めることができますよ。
⑦必要なお金が足りずに就活ができない
学生のなかには、今いる地域とは別の地域への就職を考えている人もいることでしょう。とはいえ、遠方への就活は、移動費や宿泊費など、多大なお金がかかります。
就職みらい研究所が2024年卒の学生を対象に、就活にかかった費用に関して調査した「就職プロセス調査」によると、2024年卒の学生が移動費に使った金額の平均は21,312円、宿泊着に使った金額の平均は18,544円と、併せて4万円程の費用がかかっていることがわかります。
その費用は企業で受け持ってくれないことも多いため、自分で工面するのが難しいとして就活ができないと考えている人もなかにはいるでしょう。

キャリアアドバイザー
移動費や宿泊費にかかる費用は決して安くないからこそ、志望企業を諦めざるを得ないケースもありますよね。
大学やキャリアセンターに今の状況を正直に相談する
金銭面で不安があるときは、正直に今の状況を大学やキャリアセンターに相談してみましょう。一人で悩むよりも、就活に対しての知見を持っている人に相談したほうが、解決に向かいやすくなるかもしれません。
また、地域によっては、その地域への就職希望者を対象に交通費や宿泊費の補助をしてくれる「自治体別地方就活助成・支援制度」が適応されています。
基本的に地方を対象にした制度のため、「生まれ育った場所に戻って就活をしたい」「地方への就活を目指している」という人は利用してみてください。
- 北海道:AIRDO就活応援割引
- 福島県:ふくしま移住希望者支援交通費補助金
- 群馬県:Gインターンシップ(交通費補助制度有り)
- 長野県:NAGANOインターンシップ補助金
- 三重県:インターンシップ参加奨励補助金(伊勢市)
- 島根県:IT技能習得促進インターンシップ、IT技能習得促進仕事体験
- 高知県:高知県大学生等就職支援事業(県外在住学生向け交通費補助制度)
- 福岡県:地方就職学生支援事業

キャリアアドバイザー
悩みがあるときは一人で抱え込まないのもポイントです!
⑧志望企業が採用活動をおこなっておらず就活ができない
企業によっては、毎年採用活動をおこなっているわけでなく、各年ごと、数年ごと、という場合もあります。
新卒採用をおこなわない要因としては、費用削減やリスク軽減が挙げられます。新卒採用にもコストがかかるため、別のところに費用を割くためにも新卒採用をおこなわない企業もあるのです。

キャリアアドバイザー
ひとまず自己分析や業界分析に時間を割くのも良いかもしれませんね。
将来的にその企業に行ける方法をキャリアパスとともに考える
志望する企業が新卒採用をおこなっていないとしても、中途採用や第二新卒採用など、どこかの機会で就職のチャンスがある場合もあります。
そのため、今すぐとは言わなくても、将来的にその企業に行ける方法をキャリアパスとともに考えてみてください。
たとえば、以下のような流れでキャリアパスが考えられます。
- 新卒時:不動産業界に入社、営業職に対するノウハウを身に付ける
- 3年目:第二新卒採用枠を利用して広告業界に入社、広告業界の常識を身に付ける
- 4~5年目:広告業界にて営業職を経験
- 6年目:今までのノウハウを活かして総合広告代理店へ中途入社
このように、数年後の見通しを立てたうえで志望企業へ入社する方法を考えられると、現時点で行くべき企業の選択肢が広がるはずです。

キャリアアドバイザー
近くないと思っていた業界からも、志望企業へ就職するためのヒントが得られるかもしれません。
「より詳しく将来の見通しを立てたい」という人はこの記事を参考に、自分のビジョンを明確にしてみてくださいね。
関連記事
キャリア形成とはなりたい自分に近づくためのステップ! 考え方を徹底解説
キャリア形成とは仕事の経験やスキルを計画通りに積んでいくことです。このビジョンが明確だと周囲と差別化できますよ。 この記事ではキャリア形成のために必要な力や方法などをキャリアアドバイザーが解説します。 解説動画も参考に、学生のうちから考えを深めておきましょう。
記事を読む

⑨ケガや病気が原因で就活ができない
ケガや持病が原因で、なかなか就活を思うように進められないという人もいるでしょう。
そのような状態で無理に就活を進めてしまうと、選考で本来の実力を発揮できなかったり、ケガや病気が悪化してしまうことも考えられます。

キャリアアドバイザー
「人より就活が遅れてしまう」と思うかもしれませんが、無理は禁物です!
体調を万全にすることを最優先にする
体調が振るわない場合は、まずは体調を万全にすることから始めてください。
「いつ体調が良くなるかわからない」という場合でも、無理をしてしまっては本末転倒です。体調を整えたうえで、自分のペースで就活ができるようにしましょう。

キャリアアドバイザー
選考に参加しなくても、自己分析や企業分析などの「できそう」と思うことから始めてみてくださいね。
キャリアアドバイザーの体験談就活ができない理由に多いのは「不十分な自己分析」
広い視野を持って就活に挑むことが大切
「就活ができない」と感じる学生の多くは、自己分析がきちんとできていない印象です。自分の強みを明確に把握できておらず、その結果として自己PRが不十分になり、面接でうまくアピールできないケースがよく見られます。
また、自分の強みが活かせる企業や業界を理解できていないことも一因です。どうしても志望企業ばかりに目が向いてしまい、実は強みが活かせる企業の選考を逃してしまう、といったケースもあります。
たとえば、エンタメ業界、出版業界、ゲーム業界といった人気業界ばかりに目を向け、漠然とした憧れで選考を受けているうちに、実は自身の強みに合致する他の企業の採用が終了し始めている……といった状況に陥り、結果的に難易度が上がってしまうこともあるでしょう。
こうした問題は視野が狭くなると起こりがちなため、広い視野で就活に挑むことが大切です。
なぜ対処が必要? 「就活ができない」状況が続いたときの3つの影響
就活ができない状況を変えるためには、その状況を放置した先に何が待っているのかを知るのも効果的です。将来的に起こり得る影響を知れば、今どうすればいいのか逆算的に考えることができますよ。
ここからは「就活ができない」という状況を放置してしまったときの、考えられる3つの影響を確認していきましょう。
①好条件の求人を逃す可能性がある
就活に関する情報は日々更新されていきます。そのため、動き出しができていないと、更新される情報を見逃してしまいかねません。
たとえば「初任給が高い」「年間休日が多い」と言った好条件の求人応募の機会を失ってしまうことが考えられます。
「就活再開のタイミングで、希望に合わない求人ばかりが残り、納得いかないまま就活を進めるはめになってしまった」という事態に遭いやすくなる可能性もあるのです。

キャリアアドバイザー
今現在の自分の就活状況を振り返っておきましょう!
②在学中に就活を終えられない可能性が高まる
一般的には、大学4年の4~6月頃が就活のピークと言われています。その時期までに企業は、好条件の求人や、最新の情報を提供しています。
しかし、その時期を過ぎると、翌年3月に卒業する学生向けの求人が減ってしまい、希望に合う求人を探すのに苦労してしまうのです。
その結果、内定を獲得するのが卒業ギリギリになってしまったり、進路が決まらないまま卒業を迎える可能性も考えられますよ。

キャリアアドバイザー
開始時期が遅れるほど、在学中に就活を終えられない可能性は上がるのです。
③ますます精神的につらくなる可能性がある
「精神的に今は就活をする気になれない」と感じ、開始時期をどんどん後回しにしてしまうと、「気が付いたら周りのみんなは就活を終えていた」という状況にショックを受けてしまう可能性があります。
そうすると余計に周囲との遅れや孤独感を実感し、ますますつらくなってしまうことが考えられるのです。

キャリアアドバイザー
「周りは終えているのに自分は終わっていない」という状況は、なかなかつらいものですよね。
まずは原因解明から! 就活ができない原因を明らかにする3ステップ


就活生
そもそもなぜ自分が「就活ができない」という状況なのかがつかめていませんでした……。

キャリアアドバイザー
それだとどのような対処法を試せば良いのかもわかりづらいですよね。そんなときは3ステップで「就活ができない原因」を明らかにできます。
就活ができない理由を理解できなければ、対処法の試しようがないですよね。
そのような人は、ここで解説する3ステップから就活ができない原因を明らかにして、とるべき選択肢をつかむ手掛かりにしてください。
ステップ①現在における就活の進捗を確かめる
まずは現状を把握することが「就活ができない原因」を理解するコツです。自分の現状がわかっていないと、「何が引っかかって就活ができなくなっているのか」ということの判断ができません。
大まかにでも良いため、今自分が就活においてどの段階にいるのかを明らかにしておきましょう。
- まったく手を付けていない
- 自己分析は終えた
- エントリーをするだけで終わっている
- 最終面接で落ちる

キャリアアドバイザー
現状を無視してとりあえず初めからやり直すと、同じところで引っかかってしまう可能性があります。
ステップ②どこでつまづいているのか明確にする
自分の進捗を確かめたら、「就活のどこでつまづいているのか」を明らかにしてみましょう。
- まったく手を付けていない⇒スタートの時点で止まっている
- 自己分析は終えた⇒企業分析、業界分析で手が止まっている
- エントリーをするだけで終わっている⇒選考対策をする前段階で手が止まっている
- 最終面接で落ちる⇒最終面接対策で止まっている
どこでつまづいているかを把握すると、就活ができないと感じている原因が見えてきます。原因がわかれば対処法も見えてくるので冷静に振り返ってみましょう。
そこから、「次にどのようなことをすべきか」と行動指針を考えられるとその後の就活を進めやすくなりますよ。

キャリアアドバイザー
できるだけ細かく現状を理解し、そのうえで具体的な次のステップを把握しましょう。
ステップ③なぜ手が止まっているのかを考える
就活で手が止まっている部分を洗い出せたら、なぜそうなってしまうのかを考えてみましょう。
手が止まっている部分からその原因を考えることで、表面的でなく、自分のなかにある根本的な問題に向き合うことができます。
そこから対処法を理解することで、次に何をすべきかが見えてきやすくなりますよ。
- スタートの時点で止まっている
⇒すべきことがわからないから - 企業分析、業界分析で手が止まっている
⇒そもそも就活が面倒で「なんとなく自己分析はした」という状況だから - 選考対策をする前段階で手が止まっている
⇒就活のための費用が足りず、「とりあえずエントリー」という思考になっているから - 最終面接対策で止まっている
⇒選考に落ちるごとに気分が落ち込み、就活に手を付けられる状況ではなくなるから
「手が止まっている部分はわかっても、なぜ手が止まっているのかがわからない」という場合は、「対処法も解説! 「就活ができない」と感じてしまう9つの要因」の項目から逆算的に原因を洗い出す方法もおすすめします。

キャリアアドバイザー
自分に正直になって、就活ができない原因と向き合うのが再開への近道です!
どうしても動き出せないときに少しでも前に進むための3つの方法

就活生
就活ができていない状況を放置するのはマズイとわかりつつも、それでもなかなか動き出すことができなくて……。

キャリアアドバイザー
それは困りましたね……。でも大丈夫。どのようなことをすれば良いか一緒に確認しましょう!
「解決策を知ってもいまいち動き出せず、まだ就活ができていない」
このような状況にあり放置していると、周りと差を付けられたり、どんどん自信を失ったりして、あとで就活を始めたとしても思い通りに進められなくなる可能性があります。
新卒での就職を目指すためにも、少しでも前に進む方法を試してみてください。
①1日30分でも就活にかかわることに取り組む
1日のうちの短時間でも就活にかかわることに触れるだけで、就活へのモチベーションを維持できます。
いきなり本腰を入れて動こうとすると、心理的負担が大きく、かえってやる気が下がりかねません。たとえば1日30分だけならば就活に対してのハードルが下がり、取り掛かりやすくなるでしょう。
- そのとき思っていることを書き留めておく
- 志望企業の情報をスマートフォンで軽く調べてみる
- 就活サイトで最新の求人情報をチェックする
簡単にできることを積み重ねていくと、「やればできる」という成功体験につながりますよ。

キャリアアドバイザー
小さなことでもコツコツと続けることで、習慣化しやすくなります。
②就活のゴールを定めていつまでに何をすべきかを逆算する
どうしても就活ができないというときには、ゴールが決まっていると「それまでの辛抱だ」という気持ちで乗り越えられるかもしれません。
それまでに何をすべきかをわかりやすくするため、まずはゴール設定をしてみることをおすすめします。
- 大学4年7月:就活終了(ゴール)
- 大学4年5~6月:ほとんどの企業で最終面接の段階に移行
- 大学4年4月:一~二次面接をひたすら受ける
- 大学3年3月:OB・OG訪問を通して働くことへの解像度を高める
- 大学3年1~2月:企業分析・業界分析をしていきたい方向性を定める
- 大学3年11~12月:自己分析をして自分の興味関心を理解する
- 大学3年10月:就活サイトに登録して、就活がどのようなものなのかを押さえる
このように考えれば、「大学3年の10月から就活を始めれば良い」という、大まかなスケジュールの目安が明確になります。

キャリアアドバイザー
反対に、それまでは好きに過ごすことができるため、精神的にも切り替えがしやすくなりますよ。
「スケジュール設計がうまくできない」という人は、こちらの記事を参考にしながら就活スケジュールを立ててみてください。
関連記事
就活スケジュールは実際と違うことも! 早期の計画と選考対策が重要
早期かしていると言われている就活スケジュール。この記事では実際いつから対策を進めたら良いのかなど卒年に合わせて解説しています。キャリアアドバイザーからのアドバイスや対策のコツなども併せて確認してみてくださいね。
記事を読む

③将来のなりたい自分像を想像する
「とりあえず就活をしなければ」「みんながやっているから」という気持ちで就活に臨んでいると、うまく進められなくなったときにモチベーションを保てません。
就活そのものにとらわれずに、その先にある社会人としての姿を見越して就活をおこないましょう。就活を、「なりたい自分像をかなえるための手段」として捉えることでやる気も湧いてくるはずです。
また、この考え方は「志望業界や企業がわからない」という人にも役立ちます。まずは将来どんな社会人になっていたいかを考えましょう。
- 組織のリーダーになって多くの人をまとめたい
- 人に「ありがとう」と言われる存在でありたい
- 家庭を持ってプライベートと仕事とを両立したい
なりたい社会人像ができたら、それをかなえるための手段を逆算して考えてみましょう。
年を重ねても第一線で活躍していたい
↓
廃れることのない仕事に就く必要がある
↓
社会の流行に左右されない業界を探す
プライベートも家庭も充実させたい
↓
家庭や個人でもできるような仕事
↓
会社にこだわらないようなスキルを身に付ける必要がある
↓
プログラミングのスキルを得られる企業に就職しよう
志望業界が決まっていなくても、将来の自分に合わせてみることでおのずとエントリーすべき業界が見えてきますよ。
将来の自分像を考える際はこちらの記事を参考にしてみてください。
関連記事
「将来の自分」を明確にするための6つの考え方|例文付きで解説
面接で「将来の自分像」を聞かれることは少なくない こんにちは。キャリアアドバイザーの北原です。面接で志望動機と並んでよく聞かれる質問項目が「将来の自分像について」です。具体的に、「5年後、10年後の自分の姿をどう想像して […]
記事を読む

キャリアアドバイザーは実際にこうアドバイスしています!就活ができないと感じるときはキャリアアドバイザーに頼ろう
他者の力を借りて自分らしい進路を見つけよう
どうしても「就活ができない」と感じるときは、キャリアアドバイザーに頼ることをおすすめします。就活に前向きになれない人の場合、興味のある業界だけを見て視野が狭くなりがちです。そういったときに、アドバイザーの力を借りることで、客観的に自分を見つめ直し、より現実的な選択肢を見つけやすくなります。
実際に私は、就活に行き詰っている学生に対して「なぜこの高校に進学したのか」「このときどのくらいしんどかったのか」というように、一緒に人生を振り返ることがあります。そこから強みの再認識をおこない、学生が自信を持てるように気持ちを立て直しました。
一人で取り組むと難しく感じるかもしれませんが、一緒に自己分析を進めることで、自分の強みや価値観を再確認でき、自信の回復にもつながります。活躍できる企業を早い段階で見つけるうえで、非常に心強い存在になりますよ。
あなたが受けないほうがいい職業は?
3分でできる適職診断で確認してみよう
入社後の早期離職を避けるためには、自分に適性のある職業を選ぶことが大切です。しかし、それがどんな職業なのかが分からず悩む人も多いでしょう。
そんな人におすすめなのが「適職診断」です。40の質問に答えるだけで適性のある職業や受けないほうがいい職業を診断できます。
自分に適性のある職業を早めに知って、就活を成功させましょう。
どうしても就活ができない…そんな人への4つの選択肢
ここまで就活ができるようになるための解決策を解説してきましたが、どうしても就活を継続できない人もなかにはいるはずです。そんなときは無理するのではなく、就活以外の選択肢に目を向けるのも良いでしょう。
- 就職留年をする
- 大学院に進学する
- フリーランスになる
- インターンとして働く
これらの選択肢を取れば、より柔軟に就職活動ができる可能性も上がります。
- 就職留年をする
⇒通常の新卒よりも就活に費やせる時間を確保しやすくなる - 大学院に進学する
⇒院卒でしか応募できない企業もあるため、志望先の範囲が広がる - フリーランスになる
⇒企業に属さないため就活をする必要がなく、自由な働き方が可能になる - インターンとして働く
⇒インターンに参加中に内定をもらい、社員として働けるケースもある
これらのようにうまくいけば良いですが、なかなかうまくいかないこともあるものです。
- 就職留年をする
⇒留年をした分の学費がかかる - 大学院に進学する
⇒同い年の人よりも社会人経験が遅れてしまう - フリーランスになる
⇒依頼がなければ収入もなく、生活が不安定になりがち - インターンとして働く
⇒有償インターンは求人が少なく、そのまま社員になるケースは稀

キャリアアドバイザー
とはいえ、いきなりフリーランスとして働くのはかなりチャレンジングな選択です。まずは企業に就職して、社会人としての基礎や仕事の進め方を学ぶ機会を作るのをおすすめします。
就活ができない原因と対処法応を理解して自分のペースで就活を進めよう
新卒での就活は、将来へのキャリアを決める第一歩です。だからこそ何よりも優先度を上げてしっかりと取り組んでほしいものです。
しかし、さまざまな理由から就活ができない人もいるのも事実です。
就活にきちんと取り組むためには、まずは就活ができない理由を理解することから始めましょう。そして、その理由に沿った対処法を実践して、自分のペースで就活を進めてみてくださいね。

 キャリアパーク就職エージェントは、東京証券取引所グロース市場に上場しているポート株式会社(証券コード:7047)が運営しているサービスです。
キャリアパーク就職エージェントは、東京証券取引所グロース市場に上場しているポート株式会社(証券コード:7047)が運営しているサービスです。



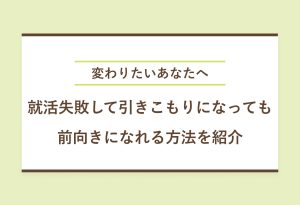









そのための方法は続く内容で解説するので、さっそくチェックしていきましょう。